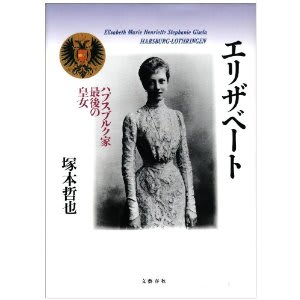 NHK大河ドラマ「江」よりも、比較にならないほどはるかにおもしろかったのがハプスブルク家最後の皇女エリザベートの波乱万丈の生涯。読み始めたらとまらない、これぞ読書の醍醐味である。エリザベートと言っても、ヴィスコンティの映画『ルートヴィヒ』のバイエルンの狂王ルートヴィヒ2世が従兄の息子という関係で親しかったエリザベート・アマーリエ・オイゲーニエではなく、このオーストリア皇后のひとり息子、映画『うたかたの恋』にもなった男爵令嬢マリー・フォン・ヴェッツェラと「マイヤーリング事件」にて謎の死を遂げたルドルフ皇太子の一人娘のエリザベートである。
NHK大河ドラマ「江」よりも、比較にならないほどはるかにおもしろかったのがハプスブルク家最後の皇女エリザベートの波乱万丈の生涯。読み始めたらとまらない、これぞ読書の醍醐味である。エリザベートと言っても、ヴィスコンティの映画『ルートヴィヒ』のバイエルンの狂王ルートヴィヒ2世が従兄の息子という関係で親しかったエリザベート・アマーリエ・オイゲーニエではなく、このオーストリア皇后のひとり息子、映画『うたかたの恋』にもなった男爵令嬢マリー・フォン・ヴェッツェラと「マイヤーリング事件」にて謎の死を遂げたルドルフ皇太子の一人娘のエリザベートである。1883年、オーストリア・ハンガリー帝国の栄華を誇るハプスブルク家の皇女として生まれ、広大で美しいシェーンブルン宮殿で育った現在ではありえない究極のお姫さまなのだが、一般庶民とは違ったかたちで社会の変化の悲運の波をかぶるのもやんごとなき高貴な身分の方たち。5歳で父であるルドルフ皇太子が今でも謎が解明されていない「マイヤーリンク事件」で亡くし、15歳の時には自由闊達で欧州一の美貌で知られた同じ名前の祖母エリザベートがアナーキストによって暗殺されるという体験をする。優雅でありながら、かすかな憂いが繊細な美しいベールのようにおおっているようで、それが尚いっそう美貌がひきたつのも、ハプスブルク王朝の皇女として生まれてしまった彼女の数奇な運命を予言しているようでもある。それは、まさに中欧の激動の現代史を体現しているかのようであった。世紀末文化の花開くウィーンは、同時に20世紀ヨーロッパの運命を左右する政治思想のショーウインドーさながらで、また実験場でもあった。
いみじくも、1953年9月22日、70歳の誕生日を迎えたエリザベートが自分の館がフランス軍に接収されて狭くて荒れた小さな住居に仮住まいをしていることについて、新聞にはこう書かれていた。
「欧州でもっとも贅沢に慣れた王室の娘であるエリザベート皇女の運命は、現在のオーストリアの立場を象徴している。この15年間オーストリアは占領され続け、自分の国の住人として、自らの意志で生きることができなかった。オーストリアはなんという運命だろうか。」
美しい女性として、また何でも望むものは手に入る立場の女性として、エリザベートは3度の(うらやましい限りの!)激しい恋をした。
最初の夫オットー・ヴィンディッシュ=グレーツは、宮廷舞踏会での初対面で彼女の一目ぼれ。今で言えば、イケ面サッカー選手か大リーグでも活躍できるプロ野球選手。その後、全ヨーロッパ馬術競技会で見事に優勝したオットーの勇姿と再会して恋の炎は燃え盛り、お祖父さまのフランツ・ヨーゼフ皇帝におねだりをして、婚約者からオットーを強引に奪って、皇位継承権は放棄するが持参金300億円と一緒に結婚する。しかし、幼い頃から教養を積んできて社会や政治にも関心の強い知性的なエリザベートにとっては、体育会系の夫は見栄えはよいがものたりない凡庸で虚栄心の強いただの飾り物。3男1女に恵まれながらも夫婦仲は後の冷戦時代のごとく冷え切った。淋しいエリザベートの心に登場したのが、端整な容姿を海軍の軍服で着こなす少尉エゴン・レルヒだった。ウィーン社交界の暗黙のルールなどおかまいなしに、堂々と若く颯爽とした年下の軍人を尊敬し、情事にのめりこむエリザベート。しかし、つかのまの逢瀬も、第一次世界大戦によるレリヒの戦死で悲恋と散る。そして第3の男は、その後の夫とのこどもの養育権をめぐって泥沼の離婚劇に突入した時に、こどもとともに彼女を救った社会民主党の指導者レオポルト・ペツネックだった。これまでの容姿端麗、皇女にはとても及ばないが身分もそれなりに高い男性だったのが、今度のペツネックは、素朴な容貌で貧農出身でしかも孤児院育ち。人生の辛酸をなめ陰影を知ったおとなの恋は、ゆっくりと時間をかけてお互いの人間性を知って近づき少しずつ育んでいくもの、、、そんなふたりの最後の恋だった。
 エリザベートの恋愛と実母との確執、孫娘を愛した祖父との繋がり(この祖父は精神分析学者フロイトのファザー・コンプレックスの父親像だそうだ)、あんなにも愛情をそそいだこどもたちの離反と和解など、女子的にも還流ドラマよりも華麗でドラマチックな世界に酔いしれる。残されたわずかな写真からも、父方の長身で美形の血筋を感じさせる整った容姿が想像され、ありえないくらい細いウエストのくびれや、現代では製作不可能ではないかと思われる絹のドレスのレースの芸術的な美しさと豪華さにひきよせられる。物語の主人公として最高の素材である。著者の塚本哲也さんの整然とした文章にも登場人物に感情移入した会話には情緒がただよい、乙女心のツボをいい感じでついてくる。しかし、それは本書の白眉ではない。エリザベートの波乱な生涯は、そのまま中欧の20世紀の苦悩の歴史に重なる。著者が書きたかったテーマーは、エリザベートというひとりの女性の生涯を中心にすえた、ふたつの大戦、スターリンやヒトラーの台頭と支配、ハンガリー動乱、鉄のカーテンといった中欧の政治的背景と苦難の歴史そのものにある。歴女でなくても、単なるお姫様の恋愛物語以上におもしろい。そして旧ハプスブルク王朝時代は、まがりなりにも多民族が共存、共栄していた事実から多民族を統治するモデル国家だったという意見もあり、英国のチャーチル首相は「ハプスブルク王朝が滅亡しなければ、中欧の諸国はこれほど永い苦難の歴史を経験しなくてもすんだであろう」と嘆いたそうだ。
エリザベートの恋愛と実母との確執、孫娘を愛した祖父との繋がり(この祖父は精神分析学者フロイトのファザー・コンプレックスの父親像だそうだ)、あんなにも愛情をそそいだこどもたちの離反と和解など、女子的にも還流ドラマよりも華麗でドラマチックな世界に酔いしれる。残されたわずかな写真からも、父方の長身で美形の血筋を感じさせる整った容姿が想像され、ありえないくらい細いウエストのくびれや、現代では製作不可能ではないかと思われる絹のドレスのレースの芸術的な美しさと豪華さにひきよせられる。物語の主人公として最高の素材である。著者の塚本哲也さんの整然とした文章にも登場人物に感情移入した会話には情緒がただよい、乙女心のツボをいい感じでついてくる。しかし、それは本書の白眉ではない。エリザベートの波乱な生涯は、そのまま中欧の20世紀の苦悩の歴史に重なる。著者が書きたかったテーマーは、エリザベートというひとりの女性の生涯を中心にすえた、ふたつの大戦、スターリンやヒトラーの台頭と支配、ハンガリー動乱、鉄のカーテンといった中欧の政治的背景と苦難の歴史そのものにある。歴女でなくても、単なるお姫様の恋愛物語以上におもしろい。そして旧ハプスブルク王朝時代は、まがりなりにも多民族が共存、共栄していた事実から多民族を統治するモデル国家だったという意見もあり、英国のチャーチル首相は「ハプスブルク王朝が滅亡しなければ、中欧の諸国はこれほど永い苦難の歴史を経験しなくてもすんだであろう」と嘆いたそうだ。1963年3月16日、エリザベートはモーツァルトがその鬱蒼とした森に囲まれた幻想的な館をみて「魔笛」の曲想がうかんだというエピソードが残る通称「エリザベートの館」で、79歳の生涯を閉じた。愛する夫ペツネックはすでにこの世を去り、愛犬に囲まれた静かだが孤独な晩年だったそうだ。ハプスブルク家のすべての美術品は国に返却すべきだという故人の意志に基づいた遺言に従い、国宝級のコレクションはすべてオーストリア共和国に寄贈された。観光客の足のたえない歴代のハプスブルク家の柩が安置されているカプチーナ教会の荘厳なにぎわいとは離れ、彼女は郊外の小さな墓地にペツネックとひっそりと眠っている。歴史のもうひとつの裏舞台ともなった愛の館も、今では優雅な昔日の面影はすっかりなくなっているそうだ。
■アーカイヴ
・最後の皇太子オットー・ハプスブルク氏の葬儀
・「ウィーン愛憎」中島義道著
・「続・ウィーン愛憎」中島義道著



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます