昨年、益川敏英博士がノーベル物理学賞を受賞した時のインタビューで、開口一番「大して嬉しくない」と口をへの字に結んで言い切った時、益川先生は言わば物理学会のちょっとした「アイドル」になったと思う。崇高な響きすらあり、世界最高の”権威”あるノーベル賞を蹴散らかすようなものいいから感じられる、なんとなくお茶目なへそまがりに私は共感も覚えたりした。益川博士は、殺到するマスコミの競走曲ぶりから窺える彼らの権威主義をばっさり斬った。
読売新聞に連載されている「本当ですか 益川先生」では、独特の益川節が更にこぶしが効いていて絶好調、おもしろい!
先の受賞時の発言は、「ノーベル賞を目標にやってきたわけではないから」というのが理由だそうが、「でも、こんなこと言うと社会通念上良くないなと感じたら、意識的に口にしてしまう、へそ曲がりなところがある」と素直に白状している。僕はそれほど変人ではないと自己分析されているが、それほどではなくともそこそこには充分変人であると私は見た。
私がブログを書く時や、普段の会話で禁句なのが「絶対」という単語である。およそ、日頃から科学的に思考することをこころがけたら、「絶対」という表現は無理というもの。ところが、物理学者の益川先生の会話には「絶対」という言葉なしには成立しない。。天才的な優秀な頭脳からの発言が、お魚屋のお兄さんのようなざっくばらんなイキのよい会話であるのがなかなか妙でもある。
「音楽は、バッハにベートーベン、バルトーク。モーツァルトは絶対聴かない」
その理由は、モーツァルトは天才だろうが、やりっぱなしで推敲なんかきっとしなかったんだろう。そういうのは、好きじゃないそうだ。
「ベートーベンのピアノソナタの『月光』全曲は、絶対聴くまいと思った」
映画のBGMで「月光」の第一楽章を聴いた時、これはお子様向けだと思ったからだ。ところが、4年くらい前にテレビの天気予報のBGMで第二・三楽章を聴いていい曲だな、、、と思ってしまったためにベートーベンの「月光」を聴くようになったのだが、ピアニストの中村紘子さんに、月光の第二・三楽章は盛り上がりますねと申し上げたら、「第一楽章がないと、成り立たないでしょう」と諭されて以来、ちゃんと全楽章を聴くようになったそうだ。こんな音楽好きな益川先生は、湯川秀樹氏からも「科学者は、絶対という言葉を絶対に使ったらいかんのや」と言われていたが、クラシック以外は絶対に聴かないと宣言している。
「ビートルズ?勿論聴きません」
益川先生、ビートルズの音楽にはクラシックの要素も入っているのですが・・・。
バッハはいろいろな可能性を調べていて「フーガの技法」という作品では、フーガを極め尽くそうとしているし、バルトークは、メロディよりもリズムが重要な役割を果たしていてなんともいえぬ感情をわき立たせる精神性の高さと緻密につくられているところがお好みらしい。そういえば、バルトーク好きの元首相からバルトーク好きの性格分析をブログで書いたことがあるが、益川先生はこの中の⑤の「知的であるがゆえに本性を隠したがり、それでいて感性豊かなためについ本音が皮肉となる」に該当しそうだ。
そんな益川先生の蔵書は1万冊。京都市の自宅、研究室だけでなく、昨年建てた琵琶湖北岸の書庫件住居に分散されているそうだが、その書庫件住居はリスニングルームもかねているらしい。私は、音楽を聴きながら本を読むことができない。以前は、ほぼ毎日音楽だけを聴く時間や家事をしながら音楽を聴く時間もあったのだが、最近はそれも忙しくてなかなか。。。オーディオに凝るcalafさまや珈琲を入れたりブランデーを呑みながら眠る前に音楽を聴くromaniさまに比べ、夜15分の時間があったら読書になってしまうため、近頃益々耳が衰えていると感じる。ゆっくり音楽だけをぼんやりと聴く時間が欲しいと願っていたのだが、益川先生のこんな言葉を読んで思わず体がざわざわとするような感覚を覚えた。
「あるのは安物のステレオなんだけど、そこそこ音が出て、僕の耳ぐらいだったら間に合う。謙遜ではない。僕は、それほど高音が聞こえるわけではなく、音の艶みたいなものをとらえられないので。冬は薪(まき)ストーブを焚(た)いてクラシックを聴き、ボケーッと考えている。至福の時ですね」
薪ストーブを焚(た)いてクラシック!!ある意味、最高の聴き方である。
読売新聞に連載されている「本当ですか 益川先生」では、独特の益川節が更にこぶしが効いていて絶好調、おもしろい!
先の受賞時の発言は、「ノーベル賞を目標にやってきたわけではないから」というのが理由だそうが、「でも、こんなこと言うと社会通念上良くないなと感じたら、意識的に口にしてしまう、へそ曲がりなところがある」と素直に白状している。僕はそれほど変人ではないと自己分析されているが、それほどではなくともそこそこには充分変人であると私は見た。
私がブログを書く時や、普段の会話で禁句なのが「絶対」という単語である。およそ、日頃から科学的に思考することをこころがけたら、「絶対」という表現は無理というもの。ところが、物理学者の益川先生の会話には「絶対」という言葉なしには成立しない。。天才的な優秀な頭脳からの発言が、お魚屋のお兄さんのようなざっくばらんなイキのよい会話であるのがなかなか妙でもある。
「音楽は、バッハにベートーベン、バルトーク。モーツァルトは絶対聴かない」
その理由は、モーツァルトは天才だろうが、やりっぱなしで推敲なんかきっとしなかったんだろう。そういうのは、好きじゃないそうだ。
「ベートーベンのピアノソナタの『月光』全曲は、絶対聴くまいと思った」
映画のBGMで「月光」の第一楽章を聴いた時、これはお子様向けだと思ったからだ。ところが、4年くらい前にテレビの天気予報のBGMで第二・三楽章を聴いていい曲だな、、、と思ってしまったためにベートーベンの「月光」を聴くようになったのだが、ピアニストの中村紘子さんに、月光の第二・三楽章は盛り上がりますねと申し上げたら、「第一楽章がないと、成り立たないでしょう」と諭されて以来、ちゃんと全楽章を聴くようになったそうだ。こんな音楽好きな益川先生は、湯川秀樹氏からも「科学者は、絶対という言葉を絶対に使ったらいかんのや」と言われていたが、クラシック以外は絶対に聴かないと宣言している。
「ビートルズ?勿論聴きません」
益川先生、ビートルズの音楽にはクラシックの要素も入っているのですが・・・。
バッハはいろいろな可能性を調べていて「フーガの技法」という作品では、フーガを極め尽くそうとしているし、バルトークは、メロディよりもリズムが重要な役割を果たしていてなんともいえぬ感情をわき立たせる精神性の高さと緻密につくられているところがお好みらしい。そういえば、バルトーク好きの元首相からバルトーク好きの性格分析をブログで書いたことがあるが、益川先生はこの中の⑤の「知的であるがゆえに本性を隠したがり、それでいて感性豊かなためについ本音が皮肉となる」に該当しそうだ。
そんな益川先生の蔵書は1万冊。京都市の自宅、研究室だけでなく、昨年建てた琵琶湖北岸の書庫件住居に分散されているそうだが、その書庫件住居はリスニングルームもかねているらしい。私は、音楽を聴きながら本を読むことができない。以前は、ほぼ毎日音楽だけを聴く時間や家事をしながら音楽を聴く時間もあったのだが、最近はそれも忙しくてなかなか。。。オーディオに凝るcalafさまや珈琲を入れたりブランデーを呑みながら眠る前に音楽を聴くromaniさまに比べ、夜15分の時間があったら読書になってしまうため、近頃益々耳が衰えていると感じる。ゆっくり音楽だけをぼんやりと聴く時間が欲しいと願っていたのだが、益川先生のこんな言葉を読んで思わず体がざわざわとするような感覚を覚えた。
「あるのは安物のステレオなんだけど、そこそこ音が出て、僕の耳ぐらいだったら間に合う。謙遜ではない。僕は、それほど高音が聞こえるわけではなく、音の艶みたいなものをとらえられないので。冬は薪(まき)ストーブを焚(た)いてクラシックを聴き、ボケーッと考えている。至福の時ですね」
薪ストーブを焚(た)いてクラシック!!ある意味、最高の聴き方である。











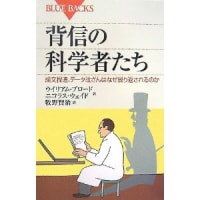

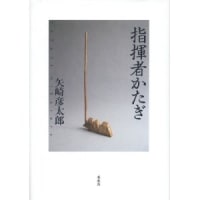
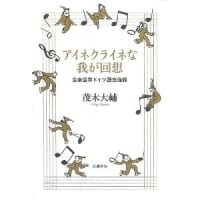
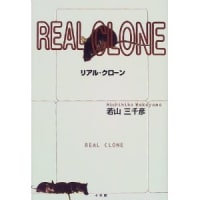
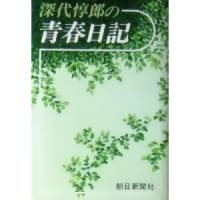
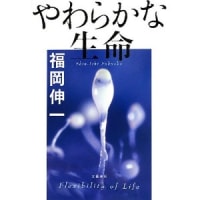
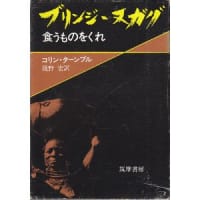
>「モーツァルトは天才だろうが、やりっぱなしで推敲なんかきっとしなかったんだろう」
当然の話ですが、天才だからする必要が無かったのです。
月光の第1楽章を聴いてソナタ全曲を云々するのはまったくもって「普通の人」です。これは私もそうです。月光の第2楽章のスケルツォの粋なリズム、同じ和音を順に弾いているだけなのにあれほどの感情の爆発は・・・。
別件
>オーディオに凝るcalafさま
最近のブログはそうなっていますが、「凝る」というほどではありません。お金がないので自分で作っているだけですが。もとはといえば音楽を多様に聴きたいという欲求から出ています(いいわけがましいですが)
「音楽を聴かないと耳が衰える」とお嘆きですが、耳ではなく聴くのは「感性」ですから読書で十分(それ以上に)研ぎ澄まされていることと思います。
慣れは感激、感動を薄めることはおおいにあり得ます。
「エリーゼのために」を聴いて感動するひとと「第9」を全部聴かなければ納得しない人ではどちらが幸せでしょうか?
益川先生は幸せな音楽の聴き方をなさっています。
バルトークというのが意外であり、新鮮ですね。
また、親しみを感じます。
今夜、ウィーンフィルでオケコンを聴くのですが、「変人」部分が極力表面にでないような仕上がりになるのではと想像しています。
予想が裏切られるほうが、むしろ嬉しいのですが・・・(笑)
自分でも納得できるような「珈琲」を淹れて音楽を聴くのはまさに至福の時間なのですが、最近音楽を聴くにあたって集中力・質が鈍ってきたような自覚があるので、自戒しているところです。
>益川先生は幸せな音楽の聴き方をなさっています
なんだか心のあたたまる言葉ですね。音楽を好きになればなるほど、音に対する欲求のレベルも高くなる時もあり、シンプルにただひたすら音の美しさと豊饒さに生きている幸福を感じる時もあります。calafさまのようにグールドを熱愛する幸福もあれば、既存の演奏家に満足できない不幸もあり。
>耳ではなく聴くのは「感性」ですから読書で十分(それ以上に)研ぎ澄まされていることと思います。
ああ、そうですね!いつでも新鮮な瑞々しい感性を失いたくないですね。
>今夜、ウィーンフィルでオケコンを聴くのですが
そうなんですよね、今年は騒ぎませんでしたが、ウィーンフィルの演奏会!
最近、チケット売場でウィーンフィルのチケットが殆ど定価で売りに出されていました。悩んだのですが、どの日にちも1枚のみ。。。
結局、千葉ロッテの応援でうさをはらしてきました。来年こそは準備万端整えて、気合を入れてチケットをゲットするため手を尽くします。
romaniさまも幸福な音楽の聴き方をされていますね。今夜も、黄金の月の光のような調べに心をゆだねられているのでしょうね。
>最近音楽を聴くにあたって集中力・質が鈍ってきたような自覚があるので
これって、トシのせい?なんていわせないようにしましょう、お互いに。^^