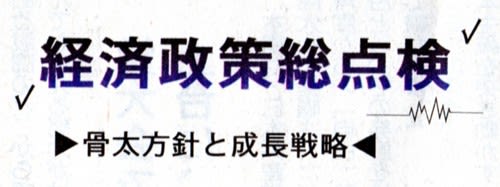法人税減税の実態② 上位20社負担 14%のみ

不公平な税制をただす会共同代表・税理士 菅隆徳さん
上場企業は3年連続最高益と報道されています(「日経」5月24日付)。2023年度(24年3月期)の純利益は前期比20%増の46兆8285億円。値上げ、販売増、円安が貢献しているといいます。大企業は21年度から23年度まで史上最高益を続けています。
これらの大企業はどれくらい税金を支払っているのか、公開されている22年度の有価証券報告書から分析しました。(表)
税引前純利益の大きい順に上位20社(持株会社、金融業は除く)について、①税引前純利益②法人3税(支払った税金)③法定実効税率(各社が公表している法定税率)④実質負担率(②÷①)―を計算しました。
法人3税というのは、利益の出た法人の支払う税金で、①法人税(国税)②法人住民税(地方税)③法人事業税(地方税)―の合計のことです。
出た利益に対して減税措置などがあるので、利益=所得とはなりませんが、所得に税率をかけて税額が決まります。つまり、利益に税率をかけたものが、ほぼ本来支払うべき税額と考えられます。
主な大企業の法人3税負担率
(注)持株会社、金融業は除く。法人3税(法人税、法人住民税、法人事業税)の負担金額を税引前純利益の金額で除して実際の負担率を計算。法定実効税率は各社の有価証券報告書に記載されている税率。
(出所)各社の有価証券報告書に記載された個別損益計算書から菅隆徳税理士が作成。「連」とある会社は連結損益計算書から作成。個別損益計算書が実質持株会社化している場合などに、連結損益計算書を採用している。
大企業優遇で
トヨタ自動車の場合、税引前利益は3兆5208億円、法人3税は5919億円、法定実効税率は30・1%です。税引前利益に30・1%をかけると1兆597億円となりますが、実際に支払った税金は5919億円でした。そこで実質負担率は、分子に法人3税5919億円、分母に税引前利益3兆5208億円で計算すると16・8%となりました。
なぜこんなに少ない税負担になっているのでしょうか。それは大企業優遇税制による減税があるからです。有価証券報告書の資料からわかる範囲で、「受取配当益金不算入」という減税制度で4401億円、研究開発減税制度で810億円、合計で5211億円の減税になっていると推定されます。
三菱商事の場合、税引前利益は1兆2992億円、法人3税は304億円、法定実効税率は30・6%です。税引前利益に30・6%をかけると3975億円となりますが、実際に支払った税金は304億円でした。実質負担率は2・3%となりました。有価証券報告書の資料からわかる範囲で「受取配当益金不算入」で3755億円の減税になっていると推定されます。
税率半分未満
このようにして上位20社の実質負担率を計算してみると、法定実効税率平均30・4%に対して、実質負担率の平均はわずか14・0%でした。
「法人税の税収力の低下」の理由の第二に、大企業優遇税制で大企業が多額の減税になっていることを述べましたが、これが史上最高益を上げている大企業の減税の実態なのです。消費税導入後、法人税率は半減しました。その半減した法人税の半分も、大企業は支払っていないという実態が明らかになったのです。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年8月8日付掲載
利益に税率をかけたものが、ほぼ本来支払うべき税額と考えられます。
トヨタ自動車の場合、税引前利益は3兆5208億円、法人3税は5919億円、法定実効税率は30・1%。税引前利益に30・1%をかけると1兆597億円となりますが、実際に支払った税金は5919億円。そこで実質負担率は、分子に法人3税5919億円、分母に税引前利益3兆5208億円で計算すると16・8%となりました。
なぜこんなに少ない税負担になっているのでしょうか。それは大企業優遇税制による減税があるからです。有価証券報告書の資料からわかる範囲で、「受取配当益金不算入」という減税制度で4401億円、研究開発減税制度で810億円、合計で5211億円の減税になっていると推定。
消費税導入後、法人税率は半減しました。その半減した法人税の半分も、大企業は支払っていないという実態。

不公平な税制をただす会共同代表・税理士 菅隆徳さん
上場企業は3年連続最高益と報道されています(「日経」5月24日付)。2023年度(24年3月期)の純利益は前期比20%増の46兆8285億円。値上げ、販売増、円安が貢献しているといいます。大企業は21年度から23年度まで史上最高益を続けています。
これらの大企業はどれくらい税金を支払っているのか、公開されている22年度の有価証券報告書から分析しました。(表)
税引前純利益の大きい順に上位20社(持株会社、金融業は除く)について、①税引前純利益②法人3税(支払った税金)③法定実効税率(各社が公表している法定税率)④実質負担率(②÷①)―を計算しました。
法人3税というのは、利益の出た法人の支払う税金で、①法人税(国税)②法人住民税(地方税)③法人事業税(地方税)―の合計のことです。
出た利益に対して減税措置などがあるので、利益=所得とはなりませんが、所得に税率をかけて税額が決まります。つまり、利益に税率をかけたものが、ほぼ本来支払うべき税額と考えられます。
主な大企業の法人3税負担率
| 企業名 | 2022年度 | ||||
| ①税引前純利益(億円) | ②法人3税(億円) | ③法定実効税率(%) | ④負担率②÷①(%) | トヨタ自動車 | 35,208 | 5,919 | 30.1 | 16.8 |
| 日本電信電話 | 連 | 18,176 | 5,249 | 31.5 | 28.8 |
| 三菱商事 | 12,992 | 304 | 30.6 | 2.3 | |
| ソニーグループ | 連 | 11,803 | 2,366 | 31.5 | 20.0 |
| 日立製作所 | 10,324 | 765 | 30.5 | 7.4 | |
| 三井物産 | 8,975 | 176 | 31.0 | 2.0 | |
| KDDI | 7,589 | 1,933 | 30.6 | 25.5 | |
| 伊藤忠商事 | 7,057 | 759 | 31.0 | 10.8 | |
| 本田技研工業 | 6,474 | 711 | 30.2 | 11.0 | |
| 任天堂 | 6,299 | 1,582 | 30.5 | 25.1 | |
| 日本郵船 | 6,244 | 13 | 28.6 | 0.2 | |
| 東京エレクトロン | 5,855 | 1,088 | 30.6 | 18.6 | |
| 日本製鉄 | 5,333 | 70 | 30.6 | 1.3 | |
| 中外製薬 | 5,192 | 1,609 | 30.5 | 31.0 | |
| ソフトバンク | 4,812 | 1,362 | 30.6 | 28.3 | |
| 商船三井 | 4,654 | 31 | 28.7 | 0.7 | |
| 住友商事 | 4,092 | -17 | 31.0 | -0.4 | |
| 川崎汽船 | 3,960 | -21 | 28.5 | -0.5 | |
| 丸紅 | 3,388 | -11 | 31.0 | -0.3 | |
| 日本たばこ産業 | 3,101 | 177 | 30.4 | 5.7 | |
| 合計・平均 | 71,528 | 24,065 | 30.4 | 14.0 | |
(出所)各社の有価証券報告書に記載された個別損益計算書から菅隆徳税理士が作成。「連」とある会社は連結損益計算書から作成。個別損益計算書が実質持株会社化している場合などに、連結損益計算書を採用している。
大企業優遇で
トヨタ自動車の場合、税引前利益は3兆5208億円、法人3税は5919億円、法定実効税率は30・1%です。税引前利益に30・1%をかけると1兆597億円となりますが、実際に支払った税金は5919億円でした。そこで実質負担率は、分子に法人3税5919億円、分母に税引前利益3兆5208億円で計算すると16・8%となりました。
なぜこんなに少ない税負担になっているのでしょうか。それは大企業優遇税制による減税があるからです。有価証券報告書の資料からわかる範囲で、「受取配当益金不算入」という減税制度で4401億円、研究開発減税制度で810億円、合計で5211億円の減税になっていると推定されます。
三菱商事の場合、税引前利益は1兆2992億円、法人3税は304億円、法定実効税率は30・6%です。税引前利益に30・6%をかけると3975億円となりますが、実際に支払った税金は304億円でした。実質負担率は2・3%となりました。有価証券報告書の資料からわかる範囲で「受取配当益金不算入」で3755億円の減税になっていると推定されます。
税率半分未満
このようにして上位20社の実質負担率を計算してみると、法定実効税率平均30・4%に対して、実質負担率の平均はわずか14・0%でした。
「法人税の税収力の低下」の理由の第二に、大企業優遇税制で大企業が多額の減税になっていることを述べましたが、これが史上最高益を上げている大企業の減税の実態なのです。消費税導入後、法人税率は半減しました。その半減した法人税の半分も、大企業は支払っていないという実態が明らかになったのです。
(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2024年8月8日付掲載
利益に税率をかけたものが、ほぼ本来支払うべき税額と考えられます。
トヨタ自動車の場合、税引前利益は3兆5208億円、法人3税は5919億円、法定実効税率は30・1%。税引前利益に30・1%をかけると1兆597億円となりますが、実際に支払った税金は5919億円。そこで実質負担率は、分子に法人3税5919億円、分母に税引前利益3兆5208億円で計算すると16・8%となりました。
なぜこんなに少ない税負担になっているのでしょうか。それは大企業優遇税制による減税があるからです。有価証券報告書の資料からわかる範囲で、「受取配当益金不算入」という減税制度で4401億円、研究開発減税制度で810億円、合計で5211億円の減税になっていると推定。
消費税導入後、法人税率は半減しました。その半減した法人税の半分も、大企業は支払っていないという実態。