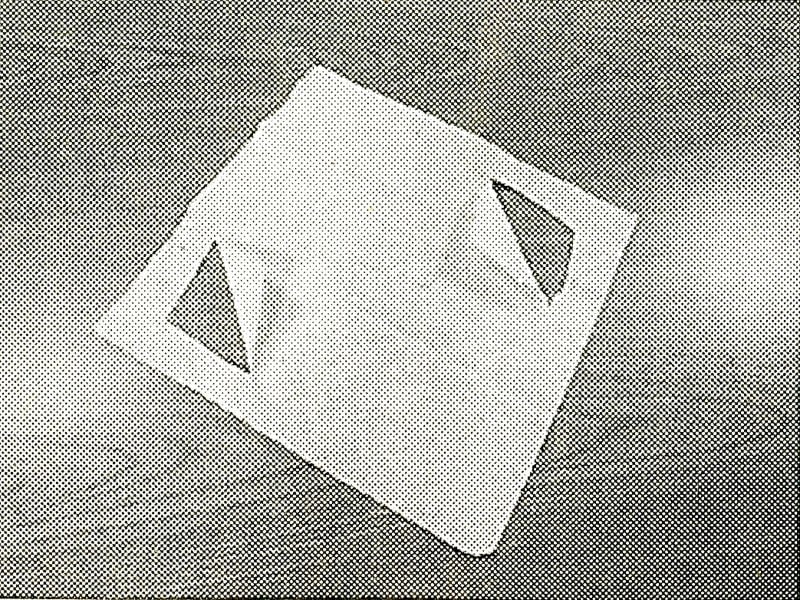西日本豪雨2年 被災地を訪ねて① 岡山・倉敷市真備町 市を動かす「希望の家」
約260人が亡くなり、約1万8100棟が全半壊した西日本豪雨から6日で2年になります。被害が大きかった岡山、広島、愛媛の各県の被災地を訪ねました。
西日本豪雨で市街地がほぼ浸水した岡山県倉敷市真備町に、被災者が戻りつつあります。日本共産党と災害対策連絡会が開く被災者支援センター「ガーベラハウス」に6月下旬、3カ月入院していた女性(59)が訪れました。センターと一緒に市に要請した医療費などの減免が延長されたことを報告し、「すごく助かりました」と喜びました。
被災者と交流し
「希望」の花言葉があるガーベラが壁に大きく描かれた支援センター。現在は週に一度開き、被災者の交流の場になっています。女性はパートの夜勤明け。医療費の心配なく持病の足を手術し、5月に退院できたと語りました。
女性が夫と2人の子ども、犬と暮らしていた自宅は2階まで浸水。胸まで水に漬かり、ポートで救助された後、避難所を転々としました。昨春、リフォームを終え、仮設住宅から戻りました。
「昨年までは急に涙が出たりしていました。今でも雨が多く降ると怖い」と女性。共同代表の須増伸子県議(54)は回復を喜び、「支援制度を活用し、たくましく生きないとね」と励ましました。

支援センター前に集まった(前列右から)須増、伊原、小坂の各氏と田辺牧美市議(後列右)ら=6月下旬、岡山県倉敷市真備町
忘れられない数
国が1年で支援を打ち切った医療費などの減免は、市独自で昨年末まで、さらに今年6月まで延長されました。市を動かしたのは支援センターの署名。人口約2万1千人の真備町で、予想を大きく上回る2367人分を1カ月で集約。支援する真備歯科診療所の小坂勝己・前事務長(62)は「一生忘れられない数。涙が出ました」と言います。
真備町では川が決壊し、5756世帯が全半壊。51人が亡くなりました。仮設住宅に最大で3285世帯が入居。自宅を再建して戻る人が増える一方、5月末現在で1278世帯が仮設住宅に残っています。共同代表の伊原潔さん(67)は「資金調達が困難な高齢者の自宅再建とその後の生活は相当に厳しい」と指摘します。
真備歯科診療所が5月末に被災患者に尋ねたアンケート(79人回答)では、高齢者の多くが「家を建て替えて貯蓄がなくなり、不安」と訴え。「気分が沈みがち」(複数回答、20・5%)、「意欲がわかない」(17・6%)、「よく眠れない」(16・5%)と答えています。
支援センターによく顔を出す60代の女性は車で30分ほど離れたみなし仮設のアパートに一人で暮らし、「知人と会うこともなく、気がめいる」。リフォーム中の自宅は業者の不誠実な対応に悩み、「住みたくなくなってきた」と話しました。
支援センターは餅つきなどの催しを毎月のように開いて交流。被災者を訪ね、要望などを聞く活動も進めています。伊原さんは「コミュニティー再生のお手伝いや被災者の問題解決のために行政とのパイプ役を務めていきたい」と語ります。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年7月4日付掲載
真備町で川が決壊した理由は、支流よりも本流の高梁川の水位がダムの放流に高くなったことが原因だと言われています。
被災した真備町の人たちが、医療費減免を求めて、1か月の間に人口の1割の署名を集めたってすごいパワーです。
それに応える倉敷市も頼もしい。
約260人が亡くなり、約1万8100棟が全半壊した西日本豪雨から6日で2年になります。被害が大きかった岡山、広島、愛媛の各県の被災地を訪ねました。
西日本豪雨で市街地がほぼ浸水した岡山県倉敷市真備町に、被災者が戻りつつあります。日本共産党と災害対策連絡会が開く被災者支援センター「ガーベラハウス」に6月下旬、3カ月入院していた女性(59)が訪れました。センターと一緒に市に要請した医療費などの減免が延長されたことを報告し、「すごく助かりました」と喜びました。
被災者と交流し
「希望」の花言葉があるガーベラが壁に大きく描かれた支援センター。現在は週に一度開き、被災者の交流の場になっています。女性はパートの夜勤明け。医療費の心配なく持病の足を手術し、5月に退院できたと語りました。
女性が夫と2人の子ども、犬と暮らしていた自宅は2階まで浸水。胸まで水に漬かり、ポートで救助された後、避難所を転々としました。昨春、リフォームを終え、仮設住宅から戻りました。
「昨年までは急に涙が出たりしていました。今でも雨が多く降ると怖い」と女性。共同代表の須増伸子県議(54)は回復を喜び、「支援制度を活用し、たくましく生きないとね」と励ましました。

支援センター前に集まった(前列右から)須増、伊原、小坂の各氏と田辺牧美市議(後列右)ら=6月下旬、岡山県倉敷市真備町
忘れられない数
国が1年で支援を打ち切った医療費などの減免は、市独自で昨年末まで、さらに今年6月まで延長されました。市を動かしたのは支援センターの署名。人口約2万1千人の真備町で、予想を大きく上回る2367人分を1カ月で集約。支援する真備歯科診療所の小坂勝己・前事務長(62)は「一生忘れられない数。涙が出ました」と言います。
真備町では川が決壊し、5756世帯が全半壊。51人が亡くなりました。仮設住宅に最大で3285世帯が入居。自宅を再建して戻る人が増える一方、5月末現在で1278世帯が仮設住宅に残っています。共同代表の伊原潔さん(67)は「資金調達が困難な高齢者の自宅再建とその後の生活は相当に厳しい」と指摘します。
真備歯科診療所が5月末に被災患者に尋ねたアンケート(79人回答)では、高齢者の多くが「家を建て替えて貯蓄がなくなり、不安」と訴え。「気分が沈みがち」(複数回答、20・5%)、「意欲がわかない」(17・6%)、「よく眠れない」(16・5%)と答えています。
支援センターによく顔を出す60代の女性は車で30分ほど離れたみなし仮設のアパートに一人で暮らし、「知人と会うこともなく、気がめいる」。リフォーム中の自宅は業者の不誠実な対応に悩み、「住みたくなくなってきた」と話しました。
支援センターは餅つきなどの催しを毎月のように開いて交流。被災者を訪ね、要望などを聞く活動も進めています。伊原さんは「コミュニティー再生のお手伝いや被災者の問題解決のために行政とのパイプ役を務めていきたい」と語ります。(つづく)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2020年7月4日付掲載
真備町で川が決壊した理由は、支流よりも本流の高梁川の水位がダムの放流に高くなったことが原因だと言われています。
被災した真備町の人たちが、医療費減免を求めて、1か月の間に人口の1割の署名を集めたってすごいパワーです。
それに応える倉敷市も頼もしい。