最近、このブログの記事の下に時々「断捨離サイト」とかいうコマーシャルが出てきます。
これは、jesterの意思とは関係なく出てきちゃうのですが、わたしはこの「断捨離」という言葉が、語感も、響きも、好きじゃありません。
すごく『破壊的』な響きがある言葉だと感じます。
インパクトがあるように『破壊的』であることを意図して作られた言葉という気もします。
この言葉を作ったのは
新・片づけ術「断捨離」

この本を書かれた、やましたひでこさんというかたで、一時評判になった本なので読んでみましたが、いわゆる「お片付け本」で、いらないものはどんどん捨てて、家の中をすっきりさせれば心もすっきりする、という、よくある内容です。
そのよくある内容を違う角度から見せようとして生んだ言葉「断捨離」が、仏教の教えから来ているとかなんとかこじつけられていて、そこが精神性に結びつくようで新鮮だったので、マスコミが飛びつき、この言葉が流行ったのかなと思います。
でも「まず捨てなさい」と言っている片付け本を読むと、でもその前提には、「いままでどんどん買っていたものを」「まだ価値があっても」「自分の部屋で邪魔だから」「次の消費のために邪魔だから」「もう興味がないから」という概念が潜んでいる気がします。
そういうのはどんどん捨てちゃえばすっきりしていいのよ、という行為がもてはやされる社会は、はたして真の意味で豊かなのだろうか。
わたしには『破壊的』な気がしてしまいます。
わたしは本だとか、洋服だとか、人からいただいたものとか、なかなか捨てられません。
例えば洋服なら、まだ着られるからもったいない、というのもありますが、それより生産過程を思うと、布を織り、それを裁ち、縫い上げた時間を思うと、その手間と時間がありがたくもったいなくて捨てられないのです。
そのたびに、こんな言葉を思い出します。
『食べ物を自分で育てなくてはいけなかったら、その1/3を無駄にするなんてできないし、机や椅子を自分で作らなければいけないなら、部屋の模様替えをしたとたんに捨ててしまったりはしないだろう。目抜き通りの店で気に入った服も、武装兵士に監視されながら布地を裁断する子供の表情を見ることができたら、買う気が失せることだろう。豚の屠畜処理の現場をみることができたなら。ほとんどの人がベーコンサンドイッチを食べるのをやめるだろう。飲み水を自力できれいにしなければならないとしたら、まさかその中にウンコはしないだろう。
心の底から破壊を好む人間はいない。他人に苦痛を与えて喜ぶ人など、そうそうお目にかかるものではない。それなのに、無意識に行っている日常的な買い物は、ずいぶんと破壊的である。なぜか。ほとんどの人が、自ら生産する側にたたされることはおろか、そうした衝撃的な生産過程を目にすることもなければ、商品の生産者と顔を合わすこともないからだ。p17~18 』
『もし人類が今ただちに衣類の生産をやめても、分かち合いと修繕の方法を知っていれば、おそらくあと10年は困らないだろう。服の生産をやめれば、土壌にとって望ましい休息を与えることにもなる。というのも、たとえば、世界で使用される農薬の25%が、多くの国々で単一作物として大規模栽培される綿花に散布されているのだ。p234』
以前、このブログで、『年収100万円で豊かな節約生活』の記事のなかで、表紙だけご紹介したこの本、
ぼくはお金を使わずに生きることにした


からの言葉です。
ベランダで種をまいて育てたトマトは、残さずに食べきりたいと思うし、夜なべに編んだセーターは、ちょっとカッコ悪くても着たいです。
その生産活動に費やした時間が愛おしいから。
そしてそれが他人がした生産行為であっても、です。
そのものが作られた過程を考えず、あまりに『破壊的』に「いらないなら捨ててすっきり軽くなればいい」という考え方は、これから私たちの子孫がこの地球で生きていくことを支えることにはならない、と思います。
さて、くだんの本を書かれたMark Boyle(マーク・ボイル)氏、この「お金を使わない生活」を始めたのは29歳の時。
その内容は節約というのではなく、哲学、であります。
彼がその生活をするために決めた『カネなし生活』 の大原則は、『丸一年、金銭の授受をしないこと。例外はいっさいなし。必要な物や欲しい物があるときは、現金やそれに類するものを使わずに手に入れなければならない。』「でも、お金を使って暮らしている人を尊重する。」
「化石燃料の世話にならない。例えば車に乗らない。移動は徒歩と自転車。電機は太陽発電など、自然エネルギーを使うだけ。」
「食料は原則自給自足。ただし「スキッピング」(ゴミなどから拾い出す)、「フォレッジング」(山でベリーなど採取する)はしていい。または同じ考えを持つコミュニティの中で交換し合うのはよい。また、労働の対価として食料をもらうのはいい。」
などなどあるのですが、これをおかしいほど真剣に考えて、生活していく中でわいてくる問題を一つ一つ真面目に解決していきます。
その奮闘ぶりがおかしいし、読んでいてワクワクします。
クレジットカードもお金も使わない、というと、
イントゥ・ザ・ワイルド [DVD]
![イントゥ・ザ・ワイルド [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51nAvVnDkNL._SL160_.jpg)

Into the Wildという映画の冒頭シーンを思い出します。
有名大学を卒業した将来を期待された青年が、お金やクレジットカードを燃やしてしまうのです。そして森に入っていきます。
この映画も、現実にいた青年を主人公にしていて、この青年は森に入って一人で暮らそうとして失敗してしまいますが、マーク・ボイルはもっと戦略的です。
ネットワークを築き、どうやったらよいか知恵を絞ります。
たとえば、『服の調達法として、本と同じで、交換すればいいと思いつく。自分で交換会をひらこう。無料で洋服を持ち帰る無料市を作ろう』という風に考えて、それを実行していきます。
こうした活動を通して、人と人のつながりができてきます。
『「一日中働いて25キロのオート麦をもらった」と言うと、「どうかしてるよ、同じ大きさのパックを20ポンドで買えるのに、九時間も労働するなんて」というのがおおかたの反応だ。でも、そう感じるのは、硬直した考え方のせいだ。食べ物の本当のコストについて、ぼくたちはもっと敏感になる必要がある。25キロのオート麦が20ポンドであってはいけないのだ。それだけの量のオートを得るために、種まき、草取り、水やりから、刈り取ってローラーでつぶすまでの一連の作業を、もし自分でやらなければならないとしたら、60時間かかるだろう。だから60時間分の成果が9時間で手に入るならぼくはありがたいと思うし、僕が手伝った相手もありがたいと思ってくれる。そこが素晴らしいところなんだ。こうした関係は、人間どうしの友情をうんと深めてくれる。p65』
本当にそう思います。
洋服だって、畑を耕して綿花を植えて、育てて収穫し、それを糸にして、織って、化石燃料で動く船や飛行機を使って別の国に持って行って、裁って縫って、また運んできて、売る・・・・というのを考えると、本当のコストは莫大なものなんだな~と感じます。
それを肌身で知っていた時代の人たちは、着物がほころびれば繕い、布団に縫い直し、おむつに縫い直し、世代を超えて使い切っていたわけです。
ウールの製品だって同じ。
それが安く手に入り、どんどん売らなくては儲からないから、とばかりに、1年着たらどんどん捨てて、新しいものを買う、とやっていたら、絶対無理が来るのはjesterにもわかります。
さて、普通こういう、真摯な考えから始めても、住んでいる社会の経済サイクルや一般大衆の常識といわれる意識から外れた考え方を持つコミュニティというと、最終的に宗教的になっていったり、イデオロギーに縛られて人間が押しやられた集団生活で破たんしたり、などの失敗例が思い浮かびますが、マーク・ボイルはとても人間的に、暖かいユーモアを交えて、こんな暮らしをしたいからしてみる!と挑戦していくのです。
どうして極端に走らないのか、どうして楽しみながらできるのか、というと、それは知性と大きな視点で周りを見られる力があるから、かな。
さて、マーク・ボイルは1年間のカネなし生活を無事やりおおせるのか、そしてその後は・・・
これはこの本を読んでのお楽しみです。
お金は誰でも欲しい。
お金があれば、もっと幸せなのに、と考える。
でも、南カリフォルニア大学の経済学者、リチャード・イースタンは
『人はお金があればあるほど幸せになれると思い込んでいます。というのも、収入の増加がもたらす影響について考えるとき、「収入が増えれば増えるほどますますお金が欲しくなる」という事実を忘れているからです。』p211
と言っています。
どんどん買って、どんどん捨てて、どんどん消費しなくては、景気が悪くなり、経済が立ち行かなくなる。
そんな経済が支えている社会は、根本がゆがんでいるし、その歪みが地球のどこかに貧しさとして集約されて、地域を破壊している。
そのことに気が付いて、「始末の良い生活」をみんなが始めるとき、未来の地球を支えていく生活ができるようになるのではないかな。
この本を家族Bに紹介したところ、とても感激し、それを友人に見せたそうです。
家族Bも友人もいわば未来の日本をしょって立つような企業に入って働いていますが、人生観が変わった、と言っていたそうです。
「ハワイに行って食堂がしたい」とか計画を立て始めたとか。
jesterが年上の友人にこの本の話をしたところ、
「でもね~~、私は洗濯機のない時代に戻って生活するなんていやだわ」と言われました(爆
とまあ、この本を読んでの反応は人それぞれだと思います。
実際にこの生活をしろ、と言われたら、面白そうだけど、できるかどうかわたしには自信がありません。
体力がないからダメかな。
でも、ドイツ人の女性のハイデマリー・シュヴェルマーさんは年をとってから、お金なし生活に入っています。その様子は
食費はただ、家賃も0円!お金なしで生きるなんてホントは簡単


『食費はただ、家賃も0円! おカネなしで生きるなんてホントは簡単』(アーティストハウス)に書かれています。
(現在絶版らしく、マーケットプレイスで手にはいります。)
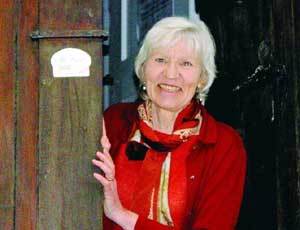
以前は教師で、セラピストでもあった彼女の場合は、テレビの番組で紹介されたこともあるようですが、
「貧富の差をなくしたくてこういうことを始めました。 階級とか、銀行に貯金があって、 どんな仕事をしているかで決まる価値観なんかを」
と、すべての財産を困った人にあげてしまい、使われていない他人の別荘で庭の手入れをし、猫にエサをあげる代わりに住まわせてもらう、洋服はお古をもらい、本は交換し、家庭教師をしてコーヒーをもらい、それを八百屋さんに持って行って、ズッキーニをもらう、という方法をとって、お金なしで生きています。
当時67歳、娘さんも二人いるのに、です。
そして自分一人で始めた活動を次第に広げ、物々交換のコミュニティを作り上げています。
年をとってからでも、自分なりの哲学がある生き方を貫いて生きる、ということは可能なんですね。
(邦題がセンスがなくてずっこけてるのですが、この本もかなり哲学的です。)
「お金なしで生きてゆくと言うことは
恐怖なしで、自由に幸福に生きてゆくと言うことなんです。」
と彼女は言っています。
言い換えれば、お金がなくても幸せに生きていける方法を身につければ、恐怖は感じずに自由に生きていける、ということでしょうか。
ああ、なんか、「年収100万円の豊かな生活節約術」の山崎さんにつながっていきますね~
人間だれしも、生きていれば、次第にものが周りにたまってくるもの。
そして、その中から本当にいるものを見極める力は必要です。
自分が死んだときに、たくさんのくだらないものを残して、残った人に片づけという苦行をさせたくはありません。
だから、いらないものを手放していく、本当にいるものだけを選んで身の回りにおく、という生き方はすがすがしいと思います。
そしてその手放されたものを使う人に渡していく。
例えば亡くなった方のものを大切に伝えていく「形見分け」という言葉があります。
少し前までは成長した子供の服は「おさがり」として使ったものでしたが、日本では今はそれも嫌がられるといいます。
ヨーロッパの友人は長く先祖から伝わる食器や家具を大切にしている人もいました。
また、USAでは不用品を手放すために、ガレッジセールや、NPOがやっているスリフトショップが盛んでした。
まだ使えるものを、使える人に譲って、譲られて、その物の命が尽きるまで使ってあげる。
新品だけがもてはやされるのではなく、古いものでも工夫して使っていく。
そんな手段のあるコミュニティの生活がいいなと思います。
以前に日本で近所の人に声をかけて、自宅や庭を使って、ガレッジセールという名の不用品交換会をやった時、思ったよりたくさんの人が集まり、その中の一人に「こういうこと、普通の人がやっていいって知らなかった」と言われました。
新しいもの好きな人が多い日本人の中には、こんな古いものを出したら恥ずかしいとかいう気持ちもあるのかな?
海外では普通にその辺のおばあちゃんとかが、2~3個のものを台に乗せて「ガレッジセール」とダンボールに書いた看板を出して、のんびりその横に座っていました。
考えれば日本人だって、海外に住んでいるときはみんな気軽にガレッジセールや、引っ越しの前の不用品差し上げ会をやっていました。
それなのに未だに日本ではあまりポピュラーじゃないのが不思議です。
ネット・オークションという手段が浸透してきましたが、それは一部のネットに詳しい人に限られてしまいます。
フリーマーケットみたいに場所代を払ってたくさんの人が集まるような大きな催し物に参加しなくても、ネット・オークションに出さなくても、もっと気軽に、自分ちの前のちょっとしたスペースに物を置いて、本を読んでお茶でも飲みながら通りかかる人と喋りつつ、必要な誰かに廉価または無料で不用品を譲る「ガレッジセール」を、もっと気軽に、気兼ねなくみんながしてくれるといいな。
捨てるのは簡単。
でも、どんどん捨てよう!と説く前に、不用品を上手に流通させられるシステムをもっと考えて作っていってほしい。
そんなに難しいことじゃないし。
「ぼくはお金を使わないで生きることにした」は、マーク・ボイルやハイデマリー・シュベルマーのように、お金を使わない生活がすぐにできるわけではないけれど、少なくとも地球環境に対して『破壊的』な行動をとりそうなとき、冬でも汗をかくほど暖房したりして、限りある化石燃料を垂れ流しのように使っていると思われるとき、必要でもないのにお金を使いたくて消費してしまいそうなとき、また、まだ使えるものを「邪魔だから」捨てようかなと思ったときなどに、ふと立ち止まって知恵を絞るきっかけになりそうな『考えるヒント』をたくさん提供してくれる本だったのでした。
さて、マーク・ボイルはこの生活を始めるにあたって、彼女に振られてしまい、新しい彼女が欲しくて・・・と書いていましたが、もし、マーク・ボイルみたいな男性に惚れてしまった女性はどうなるのか。
それがこの本
食べることも愛することも、耕すことから始まる ---脱ニューヨーカーのとんでもなく汚くて、ありえないほど美味しい生活


に書いてありました。
長くなってしまったので、また今度ご紹介しますね。
これは、jesterの意思とは関係なく出てきちゃうのですが、わたしはこの「断捨離」という言葉が、語感も、響きも、好きじゃありません。
すごく『破壊的』な響きがある言葉だと感じます。
インパクトがあるように『破壊的』であることを意図して作られた言葉という気もします。
この言葉を作ったのは
新・片づけ術「断捨離」

この本を書かれた、やましたひでこさんというかたで、一時評判になった本なので読んでみましたが、いわゆる「お片付け本」で、いらないものはどんどん捨てて、家の中をすっきりさせれば心もすっきりする、という、よくある内容です。
そのよくある内容を違う角度から見せようとして生んだ言葉「断捨離」が、仏教の教えから来ているとかなんとかこじつけられていて、そこが精神性に結びつくようで新鮮だったので、マスコミが飛びつき、この言葉が流行ったのかなと思います。
でも「まず捨てなさい」と言っている片付け本を読むと、でもその前提には、「いままでどんどん買っていたものを」「まだ価値があっても」「自分の部屋で邪魔だから」「次の消費のために邪魔だから」「もう興味がないから」という概念が潜んでいる気がします。
そういうのはどんどん捨てちゃえばすっきりしていいのよ、という行為がもてはやされる社会は、はたして真の意味で豊かなのだろうか。
わたしには『破壊的』な気がしてしまいます。
わたしは本だとか、洋服だとか、人からいただいたものとか、なかなか捨てられません。
例えば洋服なら、まだ着られるからもったいない、というのもありますが、それより生産過程を思うと、布を織り、それを裁ち、縫い上げた時間を思うと、その手間と時間がありがたくもったいなくて捨てられないのです。
そのたびに、こんな言葉を思い出します。
『食べ物を自分で育てなくてはいけなかったら、その1/3を無駄にするなんてできないし、机や椅子を自分で作らなければいけないなら、部屋の模様替えをしたとたんに捨ててしまったりはしないだろう。目抜き通りの店で気に入った服も、武装兵士に監視されながら布地を裁断する子供の表情を見ることができたら、買う気が失せることだろう。豚の屠畜処理の現場をみることができたなら。ほとんどの人がベーコンサンドイッチを食べるのをやめるだろう。飲み水を自力できれいにしなければならないとしたら、まさかその中にウンコはしないだろう。
心の底から破壊を好む人間はいない。他人に苦痛を与えて喜ぶ人など、そうそうお目にかかるものではない。それなのに、無意識に行っている日常的な買い物は、ずいぶんと破壊的である。なぜか。ほとんどの人が、自ら生産する側にたたされることはおろか、そうした衝撃的な生産過程を目にすることもなければ、商品の生産者と顔を合わすこともないからだ。p17~18 』
『もし人類が今ただちに衣類の生産をやめても、分かち合いと修繕の方法を知っていれば、おそらくあと10年は困らないだろう。服の生産をやめれば、土壌にとって望ましい休息を与えることにもなる。というのも、たとえば、世界で使用される農薬の25%が、多くの国々で単一作物として大規模栽培される綿花に散布されているのだ。p234』
以前、このブログで、『年収100万円で豊かな節約生活』の記事のなかで、表紙だけご紹介したこの本、
ぼくはお金を使わずに生きることにした

からの言葉です。
ベランダで種をまいて育てたトマトは、残さずに食べきりたいと思うし、夜なべに編んだセーターは、ちょっとカッコ悪くても着たいです。
その生産活動に費やした時間が愛おしいから。
そしてそれが他人がした生産行為であっても、です。
そのものが作られた過程を考えず、あまりに『破壊的』に「いらないなら捨ててすっきり軽くなればいい」という考え方は、これから私たちの子孫がこの地球で生きていくことを支えることにはならない、と思います。
さて、くだんの本を書かれたMark Boyle(マーク・ボイル)氏、この「お金を使わない生活」を始めたのは29歳の時。
その内容は節約というのではなく、哲学、であります。
彼がその生活をするために決めた『カネなし生活』 の大原則は、『丸一年、金銭の授受をしないこと。例外はいっさいなし。必要な物や欲しい物があるときは、現金やそれに類するものを使わずに手に入れなければならない。』「でも、お金を使って暮らしている人を尊重する。」
「化石燃料の世話にならない。例えば車に乗らない。移動は徒歩と自転車。電機は太陽発電など、自然エネルギーを使うだけ。」
「食料は原則自給自足。ただし「スキッピング」(ゴミなどから拾い出す)、「フォレッジング」(山でベリーなど採取する)はしていい。または同じ考えを持つコミュニティの中で交換し合うのはよい。また、労働の対価として食料をもらうのはいい。」
などなどあるのですが、これをおかしいほど真剣に考えて、生活していく中でわいてくる問題を一つ一つ真面目に解決していきます。
その奮闘ぶりがおかしいし、読んでいてワクワクします。
クレジットカードもお金も使わない、というと、
イントゥ・ザ・ワイルド [DVD]
![イントゥ・ザ・ワイルド [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51nAvVnDkNL._SL160_.jpg)
Into the Wildという映画の冒頭シーンを思い出します。
有名大学を卒業した将来を期待された青年が、お金やクレジットカードを燃やしてしまうのです。そして森に入っていきます。
この映画も、現実にいた青年を主人公にしていて、この青年は森に入って一人で暮らそうとして失敗してしまいますが、マーク・ボイルはもっと戦略的です。
ネットワークを築き、どうやったらよいか知恵を絞ります。
たとえば、『服の調達法として、本と同じで、交換すればいいと思いつく。自分で交換会をひらこう。無料で洋服を持ち帰る無料市を作ろう』という風に考えて、それを実行していきます。
こうした活動を通して、人と人のつながりができてきます。
『「一日中働いて25キロのオート麦をもらった」と言うと、「どうかしてるよ、同じ大きさのパックを20ポンドで買えるのに、九時間も労働するなんて」というのがおおかたの反応だ。でも、そう感じるのは、硬直した考え方のせいだ。食べ物の本当のコストについて、ぼくたちはもっと敏感になる必要がある。25キロのオート麦が20ポンドであってはいけないのだ。それだけの量のオートを得るために、種まき、草取り、水やりから、刈り取ってローラーでつぶすまでの一連の作業を、もし自分でやらなければならないとしたら、60時間かかるだろう。だから60時間分の成果が9時間で手に入るならぼくはありがたいと思うし、僕が手伝った相手もありがたいと思ってくれる。そこが素晴らしいところなんだ。こうした関係は、人間どうしの友情をうんと深めてくれる。p65』
本当にそう思います。
洋服だって、畑を耕して綿花を植えて、育てて収穫し、それを糸にして、織って、化石燃料で動く船や飛行機を使って別の国に持って行って、裁って縫って、また運んできて、売る・・・・というのを考えると、本当のコストは莫大なものなんだな~と感じます。
それを肌身で知っていた時代の人たちは、着物がほころびれば繕い、布団に縫い直し、おむつに縫い直し、世代を超えて使い切っていたわけです。
ウールの製品だって同じ。
それが安く手に入り、どんどん売らなくては儲からないから、とばかりに、1年着たらどんどん捨てて、新しいものを買う、とやっていたら、絶対無理が来るのはjesterにもわかります。
さて、普通こういう、真摯な考えから始めても、住んでいる社会の経済サイクルや一般大衆の常識といわれる意識から外れた考え方を持つコミュニティというと、最終的に宗教的になっていったり、イデオロギーに縛られて人間が押しやられた集団生活で破たんしたり、などの失敗例が思い浮かびますが、マーク・ボイルはとても人間的に、暖かいユーモアを交えて、こんな暮らしをしたいからしてみる!と挑戦していくのです。
どうして極端に走らないのか、どうして楽しみながらできるのか、というと、それは知性と大きな視点で周りを見られる力があるから、かな。
さて、マーク・ボイルは1年間のカネなし生活を無事やりおおせるのか、そしてその後は・・・
これはこの本を読んでのお楽しみです。
お金は誰でも欲しい。
お金があれば、もっと幸せなのに、と考える。
でも、南カリフォルニア大学の経済学者、リチャード・イースタンは
『人はお金があればあるほど幸せになれると思い込んでいます。というのも、収入の増加がもたらす影響について考えるとき、「収入が増えれば増えるほどますますお金が欲しくなる」という事実を忘れているからです。』p211
と言っています。
どんどん買って、どんどん捨てて、どんどん消費しなくては、景気が悪くなり、経済が立ち行かなくなる。
そんな経済が支えている社会は、根本がゆがんでいるし、その歪みが地球のどこかに貧しさとして集約されて、地域を破壊している。
そのことに気が付いて、「始末の良い生活」をみんなが始めるとき、未来の地球を支えていく生活ができるようになるのではないかな。
この本を家族Bに紹介したところ、とても感激し、それを友人に見せたそうです。
家族Bも友人もいわば未来の日本をしょって立つような企業に入って働いていますが、人生観が変わった、と言っていたそうです。
「ハワイに行って食堂がしたい」とか計画を立て始めたとか。
jesterが年上の友人にこの本の話をしたところ、
「でもね~~、私は洗濯機のない時代に戻って生活するなんていやだわ」と言われました(爆
とまあ、この本を読んでの反応は人それぞれだと思います。
実際にこの生活をしろ、と言われたら、面白そうだけど、できるかどうかわたしには自信がありません。
体力がないからダメかな。
でも、ドイツ人の女性のハイデマリー・シュヴェルマーさんは年をとってから、お金なし生活に入っています。その様子は
食費はただ、家賃も0円!お金なしで生きるなんてホントは簡単

『食費はただ、家賃も0円! おカネなしで生きるなんてホントは簡単』(アーティストハウス)に書かれています。
(現在絶版らしく、マーケットプレイスで手にはいります。)
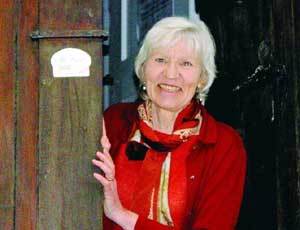
以前は教師で、セラピストでもあった彼女の場合は、テレビの番組で紹介されたこともあるようですが、
「貧富の差をなくしたくてこういうことを始めました。 階級とか、銀行に貯金があって、 どんな仕事をしているかで決まる価値観なんかを」
と、すべての財産を困った人にあげてしまい、使われていない他人の別荘で庭の手入れをし、猫にエサをあげる代わりに住まわせてもらう、洋服はお古をもらい、本は交換し、家庭教師をしてコーヒーをもらい、それを八百屋さんに持って行って、ズッキーニをもらう、という方法をとって、お金なしで生きています。
当時67歳、娘さんも二人いるのに、です。
そして自分一人で始めた活動を次第に広げ、物々交換のコミュニティを作り上げています。
年をとってからでも、自分なりの哲学がある生き方を貫いて生きる、ということは可能なんですね。
(邦題がセンスがなくてずっこけてるのですが、この本もかなり哲学的です。)
「お金なしで生きてゆくと言うことは
恐怖なしで、自由に幸福に生きてゆくと言うことなんです。」
と彼女は言っています。
言い換えれば、お金がなくても幸せに生きていける方法を身につければ、恐怖は感じずに自由に生きていける、ということでしょうか。
ああ、なんか、「年収100万円の豊かな生活節約術」の山崎さんにつながっていきますね~
人間だれしも、生きていれば、次第にものが周りにたまってくるもの。
そして、その中から本当にいるものを見極める力は必要です。
自分が死んだときに、たくさんのくだらないものを残して、残った人に片づけという苦行をさせたくはありません。
だから、いらないものを手放していく、本当にいるものだけを選んで身の回りにおく、という生き方はすがすがしいと思います。
そしてその手放されたものを使う人に渡していく。
例えば亡くなった方のものを大切に伝えていく「形見分け」という言葉があります。
少し前までは成長した子供の服は「おさがり」として使ったものでしたが、日本では今はそれも嫌がられるといいます。
ヨーロッパの友人は長く先祖から伝わる食器や家具を大切にしている人もいました。
また、USAでは不用品を手放すために、ガレッジセールや、NPOがやっているスリフトショップが盛んでした。
まだ使えるものを、使える人に譲って、譲られて、その物の命が尽きるまで使ってあげる。
新品だけがもてはやされるのではなく、古いものでも工夫して使っていく。
そんな手段のあるコミュニティの生活がいいなと思います。
以前に日本で近所の人に声をかけて、自宅や庭を使って、ガレッジセールという名の不用品交換会をやった時、思ったよりたくさんの人が集まり、その中の一人に「こういうこと、普通の人がやっていいって知らなかった」と言われました。
新しいもの好きな人が多い日本人の中には、こんな古いものを出したら恥ずかしいとかいう気持ちもあるのかな?
海外では普通にその辺のおばあちゃんとかが、2~3個のものを台に乗せて「ガレッジセール」とダンボールに書いた看板を出して、のんびりその横に座っていました。
考えれば日本人だって、海外に住んでいるときはみんな気軽にガレッジセールや、引っ越しの前の不用品差し上げ会をやっていました。
それなのに未だに日本ではあまりポピュラーじゃないのが不思議です。
ネット・オークションという手段が浸透してきましたが、それは一部のネットに詳しい人に限られてしまいます。
フリーマーケットみたいに場所代を払ってたくさんの人が集まるような大きな催し物に参加しなくても、ネット・オークションに出さなくても、もっと気軽に、自分ちの前のちょっとしたスペースに物を置いて、本を読んでお茶でも飲みながら通りかかる人と喋りつつ、必要な誰かに廉価または無料で不用品を譲る「ガレッジセール」を、もっと気軽に、気兼ねなくみんながしてくれるといいな。
捨てるのは簡単。
でも、どんどん捨てよう!と説く前に、不用品を上手に流通させられるシステムをもっと考えて作っていってほしい。
そんなに難しいことじゃないし。
「ぼくはお金を使わないで生きることにした」は、マーク・ボイルやハイデマリー・シュベルマーのように、お金を使わない生活がすぐにできるわけではないけれど、少なくとも地球環境に対して『破壊的』な行動をとりそうなとき、冬でも汗をかくほど暖房したりして、限りある化石燃料を垂れ流しのように使っていると思われるとき、必要でもないのにお金を使いたくて消費してしまいそうなとき、また、まだ使えるものを「邪魔だから」捨てようかなと思ったときなどに、ふと立ち止まって知恵を絞るきっかけになりそうな『考えるヒント』をたくさん提供してくれる本だったのでした。
さて、マーク・ボイルはこの生活を始めるにあたって、彼女に振られてしまい、新しい彼女が欲しくて・・・と書いていましたが、もし、マーク・ボイルみたいな男性に惚れてしまった女性はどうなるのか。
それがこの本
食べることも愛することも、耕すことから始まる ---脱ニューヨーカーのとんでもなく汚くて、ありえないほど美味しい生活

に書いてありました。
長くなってしまったので、また今度ご紹介しますね。




















それで、いきなり大きなお世話ですが、不用品をバザー品として送れる場所があるので、その場所をお伝えします。大阪にある、『豊能障害者労働センター』で、5つのリサイクルショップを運営して、バザー品はそこで売られています。売り上げ金は、主に障害者福祉に使われています。
私も「ずっと長く使う」と信じて買ったものが、意外と使わなくなった、ということが、よくありました。以前はもったいないと思いながら、不用品を泣きたい気持ちで仕方なく捨てていましたが、今はここの労働センターに送れるので、とても嬉しいです(^^) それで、私と同じように、「使わないものを捨てられない」と悩んでいる人を助けたくて、多くの人に、この労働センターを教えているのです。
バザー品の送り先のHPは http://www.tumiki.jp/bazar.html
です。このページを開いて頂いたほうが、わかりやすいと思います。
また、ここの送り先を気に行って下さったら、知り合いの方にも伝えて頂けると嬉しいです。私は一人でも多くの「もったいなくて捨てられなくて困っている」方々を助けたいので(^^)
コメント&情報、ありがとうございます!
>初めまして。不用品をもったいなくて捨てられないという気持ちにとても共感します(^_^)/
それで、いきなり大きなお世話ですが、不用品をバザー品として送れる場所があるので、その場所をお伝えします。大阪にある、『豊能障害者労働センター』で、5つのリサイクルショップを運営して、バザー品はそこで売られています。売り上げ金は、主に障害者福祉に使われています。
さっそく教えていただいたHPを見てまいりました。
いい感じでした!
こういう、「寄付」で不用品を送れる場所は、いろいろあるようです。
わたしも、避暑地でペンションをやっている方で、避暑の期間が終わると置き去りになる犬猫を保護してる方のやっているバザーによく送っております。
こういったバザーなどで、不用品をまた活用して、しかも自分は身軽にすっきりなっていければ、うれしいですね。
あと、このHPにも書いてありましたが、お中元や結婚式の引き出物のように、「相手がいるかどうかわからないものを勝手に送りつける」
日本の文化も考え直さなくてはいけないですね。
最近はカタログ式とかもありますが、カタログ見ててもいらないものばかり。
どうせなら現金がいい、とかいってしまいそうな自分が恥ずかしいです・・・
こんな私ですが、よろしくお願いいたします。