物語には、出会う時期っていうものがあると思うのです。
ファンタジーはなおさらです。
作品がどんなに良質のものであったとしても、それが子供向けにかかれたものであったなら、大人になってから読んでも、それが生活の1部になってしまうことはないですよね。
日常の生活に追われながら、初めて、魔法とか小人とか妖精とかの世界にどっぷり浸るのは、どんなに心の中に子供がすんでいる人でも、難しいところがあると思います。
だからこそ、幼い人たちには、心の柔らかい、小さな頃に、良質の児童文学にたくさん出会って欲しいな、と思います。
そうして心に入り口を作っておけば、大人になってからでもファンタジーの世界に簡単にいけるから。
それがどんなに、苦しいときの避難場所になってくれることか。
(ま、jesterみたいに避難しっぱなしの現実逃避生活も困りますが・・・・

)

今回、子供の頃にナルニアを読まずに、大人になってから『ナルニア国物語』の映画を突然みた人は、なかなか入りづらいのではないかしら。
どうしても、他の映画とCGを比べたり、戦闘シーンを比べたり、そういう方向から見てしまうかもしれません。(もちろんそれはそれで、一つの見方ですが)
その点jesterは小学校のときにナルニアと出会うことが出来て幸せだったと思います。
まるでふるさとにもどったような気がしました。
自分もいつか魔法を使えるようになるかもしれないと信じていた頃。
だからワードローブの向こうにある雪の中のランプポストも、タムナスさんの居間のお茶も、アスランも、そして泥足にがえもんも、銀の椅子も・・・・・
すべて現実と混同するほどリアルに受け止め、自分の一部になっていたんじゃないかと思います。
というか、あの頃jesterにとっては現実と同等に平行して成り立ってる世界で、
「なにかあっても、あっちに逃げ込める」っていう場所でした。
かくれんぼをしていたら、いつの間にか別の世界にいってしまうかもしれない。
誰も知らないうちに・・・・
押入れの奥に隠れるとき、ちょっと恐ろしく思いながらも、期待してた子供時代。
(そして、オニが捜しにきて足音がすると、決まってトイレに行きたくなるあの緊張感。何度漏らしそうになったことか(殴

それを今、映像として見せてもらった幸せ。
まさに「生きてて良かった」です。
長生きすればつらいことも多いけど、いいこともまたたくさんあるもんじゃのお。
映画を見終わって、「あ~~~ 手塚治虫さんに見せたかった・・・・」
なんて思ってしまいました。
ロード・オブ・ザ・リングスのときも同じことを思ったのです。
手塚さんはバクシアニメをアメリカまで見に行った、というほどの人ですから、きっと喜ばれたことだろうと思って。
それを、手塚さんの漫画をリアルタイムで読んでいたファンの友人にいったら、
「ああ、手塚さん、きっと悔しがっただろうね・・・・
あの人、あんなに忙しくても、自分より若いひとが描く漫画も全部読んでたし、けっこうジェラシーもある人だったから、
『自分がこれをやりたかったのに!』っていったと思うよ。
宮崎監督のアニメなんかも、きっと悔しがったと思うもの」
といわれました。
そうです、そうです、同業者としては、単にファンとしてでなく、『自分ならどう作るか』という視点でもご覧になったでしょうね。
天国にも音響のいい映画館があると良いです。
この記事、
JUNeK-CINEMAにも同掲しました。
























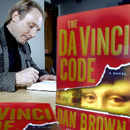





 )
)



 我慢しました・・・・。
我慢しました・・・・。


