今更ながらなのですが、過去に黄銅鉱のタイトルは何度か使い、三角式黄銅鉱に関してもチョットだけ触れておりましたが、三角式黄銅鉱というタイトルは今回が初めてです。
三角式黄銅鉱と言うと、二十数年前に秋田大学鉱業博物館で見た形の変遷していく標本セットが非常に印象的でした。そして、和田維四郎コレクションにも複数の標本があったと記憶しております。



上の写真は、三角式黄銅鉱と思われる分離結晶と母岩付き結晶です。
今、なぜ、三角式黄銅鉱なのかと言うと、昨日知ったことなのですが、どうも三角式黄銅鉱の発見者は若林彌一郎だったらしいのです。
若林彌一郎とは日本三大鉱物コレクションと言われている東京大学・若林鉱物標本の蒐集者で、珍しい石川県出身の鉱物学者(金沢市片町で生まれた。)でした。
その若林鉱物標本が東京大学総合研究博物館で特別展示されるようです。期間は3月23日~9月1日となっており、私も久しぶりに東京に行き見学したいと思っております。
今回の展示内容を見てみると、もちろん荒川鉱山産の三角式黄銅鉱がラインナップされておりました。(三角式黄銅鉱は若林彌一郎が荒川鉱山の鉱山長在任中に発見したそうです。)
「INTRODUCTION TO JAPANESE MINERALS」(工業技術院地質調査所 1970年)という本には、三角式黄銅鉱の産地として、秋田県以外にも飛んで石川県の尾小屋鉱山が記載されております。更に、「所謂三角式黄銅鑛に就いて」(砂川一郎 1949年)と言う論文には、「筆者は尾小屋鉱山に於ける産出を疑問覗している。」と書いてありました。
実際のところ、尾小屋鉱山産の三角式黄銅鉱はあったのでしょうか?
長らくそのような現物は不明でした。ただ、数年前、それらしきもの(細長いタイプのもの)が某所の収納品の中から再発見されております。また、一昨年、能美市の鉱山跡からもそれらしいもの(細長いタイプのもの)が採集されております。
三角式黄銅鉱は日本だけに産出するらしいので、そのような貴重なものが身近な産地に存在していたという事、また、その発見者が石川県出身者だったという事、そういう意味で石川県人にとっては特別な存在であろうと思います。










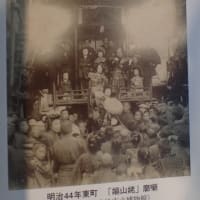

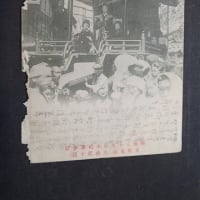













コメント、ありがとうございます。
野呂さんにとっては懐かしいキャンパスですよね。
数年前に同じところで結晶関係の講演が有り、行きました。本郷三丁目から赤門・安田講堂までのルートは面影が残っていたけど、キャンパス内は大きく変わってました。