
▲<第46回「青年ふるさとエイサー祭り」>
9月11日・12日に、那覇市奥武山野球場で、第46回「青年ふるさとエイサー祭り」が開催されました。
昨年までは、「北谷球場」で開催されていたが、今年から会場が那覇市奥武山野球場に移った。主催は、「青年ふるさとエイサー祭り実行委員会」(沖縄県青年団協議会、沖縄青年会館、琉球放送、沖縄タイムズ)。
今年は、台風の影響で「全島エイサー」(会場:沖縄市)が、一週間ずれて同じ日の開催となり、大会主催者&参加者は調整に苦労をしただろう。
12日の15時過ぎに、最寄駅の「赤嶺駅」から2駅目の「奥武山公園駅」で下車し、「奥武山野球場」に入った(入場料500円)。丁度、「若鷹太鼓」の演舞が始まった時だった。

▲<「若鷹太鼓」>
途中から、グランドに下りて、「名護市城青年会」、「金武町金武区青年会」、「恩納村安祖青年会」を観た。

▲<名護市城青年会」>



▲<「金武町金武区青年会」>



▲<「恩納村安富祖青年会」>

▲<スタンドでも、グランドでも観る事が出来る。観客は家族連れが多く、食事をしながら観ている>
17時~18時まで、演舞がなく時間が空いたので家に帰った。
那覇市内の人には、エイサー祭りが奥武山公園で観れるのが嬉しい。
沖縄県青年団協議会の実行委員会の皆さまありがとう!来年もよろしく!

















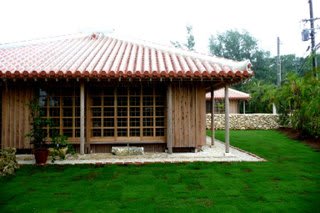


































































 <幼虫>
<幼虫>

 <右側は、羽化した抜け殻>
<右側は、羽化した抜け殻>


 <交尾中>
<交尾中>




 <気にいったシーサーしかし、顔の向きが・・・>
<気にいったシーサーしかし、顔の向きが・・・>







 <4月9日「琉球新報」のインタビューに、答える澤地久枝さん>
<4月9日「琉球新報」のインタビューに、答える澤地久枝さん>