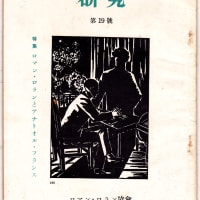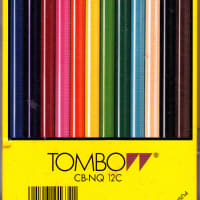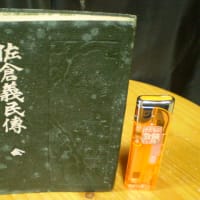今まで書いたことない一揆です。
千葉県の館山市周辺、江戸時代は安房国といって、屋代越中守忠至の領地でした。27か村、石高約1万石ですので、この領地で起きた一揆を万石騒動とよびます。
時代は正徳元年(1711年)、赤穂浪士の事件から10年後、江戸時代ど真ん中、今から300年前くらい前になります。
義民は3人、3人の義民碑(墓)はこの騒動の直後から立てられ、江戸時代を通して(今でも)村人に祭られてきたというから珍しい。ふつう、義民の墓や碑は江戸時代はおおやけには立てられなかったと思うのに。
悪役というか、この一揆で断罪された侍はこの藩の御用人上席家老相談役川井藤左衛門。もと、浪人です。紀州の出身とか、代官所に追われた過去があるとの説がります。
殿様の屋代忠至が大坂城番をしていたころに知遇を得、江戸に戻るときいっしょに江戸屋敷にいって出入りを始める。再度、殿様が大坂勤番になるとまた大坂に従い、その有能ぶりを認められ、家臣に。知行150石。
殿様の命令、というか、どこの殿様の願いも、財産をふやせ、金をつくれ、でしょう。浪人から重臣に抜擢された川井に期待されたのは財政改革家としての辣腕でした。
川井は新田開発に取り組みますが、それだけでは急場の役にはたたない。で、領地の木を大量に切り出して江戸で売って金を作ります。神社仏閣の木まで切り出します。作業も農作業で忙しい百姓を動員する。このころ酒屋さんの税は幕府はなくしたのですが、この土地では依然として酒屋から税をとりあげる。
正徳元年。新しい年貢の布告。今までの慣例をまったく無視したもので、最もできのよい上田から家来に刈り取らせ、量の計算も勝手に割り増し、これを標準として命令。例年よりも、6000俵の増税(2倍)。改革には痛みがつきもの。領民よ、痛みをがまんしてくれといったかどうか。しかし、領民はがまんできない。
9月9日から8日まに村民は北条にある陣屋におしかけ、嘆願。しかし、陣屋は面会せず、願い事があれば書面にて出せ。領民は、「過去10年間の年貢のどの年の年貢でもいいですから、その年貢にしてください。どんなに高くても、過去10年以内の年貢ならいやとはいいません」の書面を出す。陣屋は、「もはや決定済みだから是非もない。この決定に違反すると重罪に処すぞ、とおどかす。
9月22日、陣屋の郡代は二人の名主を呼び出し、江戸の上屋敷へ出頭せよ、と命令する。名主を呼び出して大目玉をくらわそうという魂胆。江戸の上屋敷には川井藤左営門が待っている。つづく。
千葉県の館山市周辺、江戸時代は安房国といって、屋代越中守忠至の領地でした。27か村、石高約1万石ですので、この領地で起きた一揆を万石騒動とよびます。
時代は正徳元年(1711年)、赤穂浪士の事件から10年後、江戸時代ど真ん中、今から300年前くらい前になります。
義民は3人、3人の義民碑(墓)はこの騒動の直後から立てられ、江戸時代を通して(今でも)村人に祭られてきたというから珍しい。ふつう、義民の墓や碑は江戸時代はおおやけには立てられなかったと思うのに。
悪役というか、この一揆で断罪された侍はこの藩の御用人上席家老相談役川井藤左衛門。もと、浪人です。紀州の出身とか、代官所に追われた過去があるとの説がります。
殿様の屋代忠至が大坂城番をしていたころに知遇を得、江戸に戻るときいっしょに江戸屋敷にいって出入りを始める。再度、殿様が大坂勤番になるとまた大坂に従い、その有能ぶりを認められ、家臣に。知行150石。
殿様の命令、というか、どこの殿様の願いも、財産をふやせ、金をつくれ、でしょう。浪人から重臣に抜擢された川井に期待されたのは財政改革家としての辣腕でした。
川井は新田開発に取り組みますが、それだけでは急場の役にはたたない。で、領地の木を大量に切り出して江戸で売って金を作ります。神社仏閣の木まで切り出します。作業も農作業で忙しい百姓を動員する。このころ酒屋さんの税は幕府はなくしたのですが、この土地では依然として酒屋から税をとりあげる。
正徳元年。新しい年貢の布告。今までの慣例をまったく無視したもので、最もできのよい上田から家来に刈り取らせ、量の計算も勝手に割り増し、これを標準として命令。例年よりも、6000俵の増税(2倍)。改革には痛みがつきもの。領民よ、痛みをがまんしてくれといったかどうか。しかし、領民はがまんできない。
9月9日から8日まに村民は北条にある陣屋におしかけ、嘆願。しかし、陣屋は面会せず、願い事があれば書面にて出せ。領民は、「過去10年間の年貢のどの年の年貢でもいいですから、その年貢にしてください。どんなに高くても、過去10年以内の年貢ならいやとはいいません」の書面を出す。陣屋は、「もはや決定済みだから是非もない。この決定に違反すると重罪に処すぞ、とおどかす。
9月22日、陣屋の郡代は二人の名主を呼び出し、江戸の上屋敷へ出頭せよ、と命令する。名主を呼び出して大目玉をくらわそうという魂胆。江戸の上屋敷には川井藤左営門が待っている。つづく。