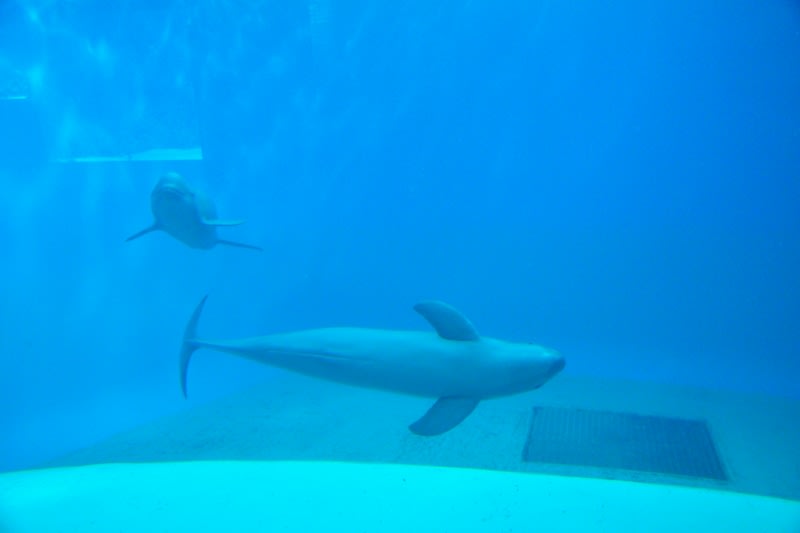下関市で乗ってた観光バスの駐車場の前にあった赤間神宮を参拝の後、隣の春帆楼(下関条約の会場 ただし、当時の建物は1945年に空襲で焼失)で
思わぬ時間を取り、お目当ての水族館(海響館)に行くのが遅くなった。

先頭を行くのがキングペンギン
キングペンギンは、コウテイペンギンに次ぐ大型種である。
19世紀まではこの種が最大のペンギンとして知られ、名もキング(王)が冠されたが、19世紀にさらに大きなペンギンが発見され、名にエンペラー(皇帝)が
当てられたという経緯がある。322mの潜水記録がある
2番手グループが3番目に大きなジェンツーペンギン
ジェンツーペンギンは、その温順な性格から温順ペンギン和名もある。普通、ペンギンが泳ぐ速さは、平均時速10km程度だが、このジェンツーペンギンは、
時速36kmになることもあるそうだ。

海響館1階の「亜南極に生きるペンギンコーナー」にはキングペンギン、ジェンツーペンギン、イワトビペンギン、マカロニペンギンの4種のペンギンがいる。
ちなみに現在世界にいる19種(18種とも)のうち12種は、絶滅の恐れのある種あるらしい。
キングペンギンの隣にいる頭部の白い帯模様が目立つのがジェンツーペンギン。
ここは、水量700トン、水深最大6mを誇る世界最大級のペンギンプールでフォークラング諸島に代表される亜南極圏の環境を再現しているらしい。

ピンぼけだが、こちらを向いているのがイワトビペンギン
イワトビペンギンは、資生堂の整髪料のアニメCMにもなったキャラクターのROCKYとHOPPERがそうである。
このピンぼけには訳がある。実は、手前の野鳥が気になったのである。

カモメ科でアジサシ類のインカアジサシ(体長41cm)
インカアジサシは、フンボルトペンギンやミズナギドリ類の巣穴をしばしば利用するらしい。
ちなみに、海峡館2階に南米チリの「アルガロボ島」を再現した「フンボルトペンギン特別保護区」を設置しており、フンボルトペンギンもいるのだが、時間の関係で
見学しなかった。

これもピンぼけ写真だが、中央のキングペンギンの左にいるのがマカロニペンギン
マカロニペンギンの「マカロニ」とは、18世紀のイギリスの言葉で、当時のイタリアの最先端の流行を取り入れた「伊達男」のことで、本種の飾り羽にちなむ。
上記のイワトビペンギンもマカロニペンギン属である。両者の見分け方は、飾り羽が額の所でくっついているのがマカロニペンギン、左右に分かれているのがイワトビペンギン。

ジェンツーペンギンがホースを噛んでいる