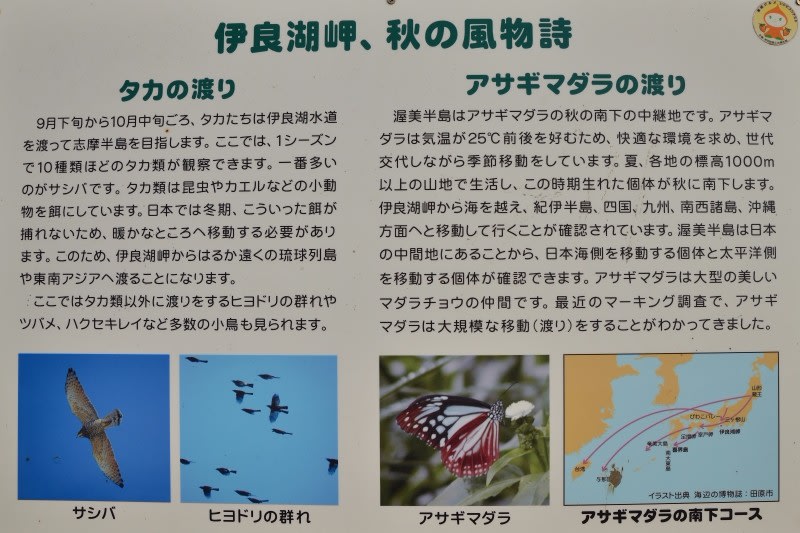岐阜県郡上市にある「ひるがの高原コキアパーク」。去年の夏に来たばかりなのに、風景が変わっているせいで、
園内に入った当初は気がつかなかった。

その原因がこれ。 スキー場のゲレンデに植えられている約3万株のコキア(ホウキ草)
夏は緑だったのに、秋にになるとピンクに変わっている。

これを束ねると箒になるからホウキ草という名がついた。

まさに秋といった感じだが、風が吹いていて少し肌寒かった。でも天気がいいから気持ちが良い。

特徴的な2峰が見えたので拡大してみた。白山の御前崎(2,702m)と剣ヶ峯(2,677m)だ。

雲が良い。

何かと思えば赤そばとのこと

普通のそばに比べると味は大分落ちるらしい。

秋と言えばススキだ。白山連峰の大屏風も見える。

園内に入った当初は気がつかなかった。

その原因がこれ。 スキー場のゲレンデに植えられている約3万株のコキア(ホウキ草)
夏は緑だったのに、秋にになるとピンクに変わっている。

これを束ねると箒になるからホウキ草という名がついた。

まさに秋といった感じだが、風が吹いていて少し肌寒かった。でも天気がいいから気持ちが良い。

特徴的な2峰が見えたので拡大してみた。白山の御前崎(2,702m)と剣ヶ峯(2,677m)だ。

雲が良い。

何かと思えば赤そばとのこと

普通のそばに比べると味は大分落ちるらしい。

秋と言えばススキだ。白山連峰の大屏風も見える。