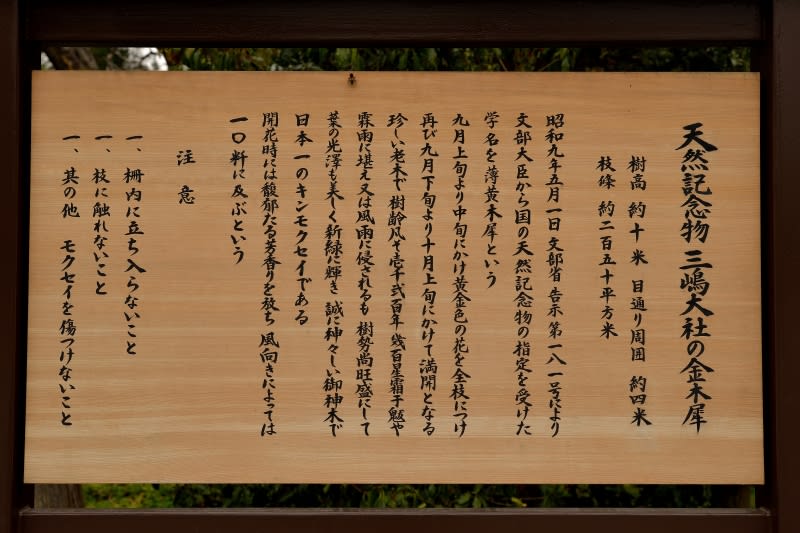ツアーのバスの中では、観光地に到着する前に添乗員さんが名所の由来を説明してくれる。ここ修善寺での説明は、弘法大師がこの地を訪れた807年
に際に病弱の父親の体を洗う少年を見つけ、その孝心に心を打たれた弘法大師が「川の水では冷たかろう」と手にした独鈷杵で川の中の岩を打ち砕き、
そこから霊泉を湧出させた。という伝承話を説明してくれる。
さらに話は続き、大師が父子に温泉療法を教えたところ、摩訶不思議、父親の十数年の固疾はたちまち平癒、その後この地には温泉療法が広まったと伝え
られている。伊豆地方最古の温泉。

桜の背後にあるのが本堂
修禅寺という地名の元になった寺の修善寺は、空海(弘法大師)が同年807年に開基し、その後荒廃・再興を繰り返し、真言宗から臨済宗 、そして曹洞宗
になったそうだ。
鎌倉幕府2代将軍の源頼家が御家人間の権力闘争に巻き込まれた形で修善寺に幽閉され、実母の北条政子に許しを乞うたが聞き入れられず、暗殺されたこと
でも知られている。

かなりの雨が降っている。

この川は、蛍が舞う川として有名な桂川

修善寺温泉街を流れている桂川のほとりにある竹で囲まれた遊歩道「竹林の小径」
「竹林の中に自然石を敷き、建仁寺垣や桂垣を配した風情のある光景は、「伊豆の小京都」と称される修善寺にふさわしい。」と喧伝されている。
しかし、この竹林の小径はもともとこの地域に繁茂していた竹の活用ということで、1995年から1997年に工事をされた事業であり、小径自体は
新しいものだ。