旧聞になりますが、記録の目的で記述します。
2009年6月6日、京都新聞の主催で「ソフィア京都フォーラム2009:日本の匠 心と技」と題して、山本さん、諏訪蘇山氏(女流陶芸家)、河野美砂子氏(ピアニスト・歌人)のパネル討論がありました。
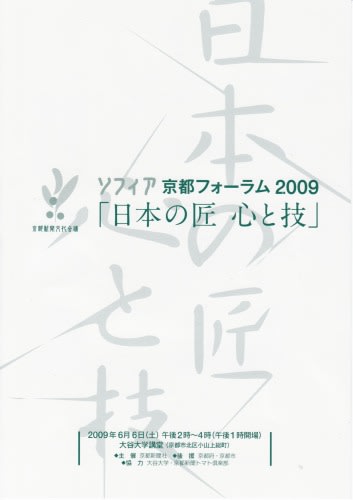
山本さんは、京都市生まれ、同志社大学文学部卒、出版社、フリーライターを経て作家に。2004年「火天の城」で松本清張賞受賞。本年、「利休にたずねよ」で第140回直木賞受賞。「火天の城」は西田敏行主演にて映画化(現在上映中)。

彼の講演で、なるほどと思ったポイントは次のとおりです。
・出版社勤務(たしか業界新聞の取材記者であった。いわゆる大手ではない)の時に、アルバイトで各種の調査記事、単発記事などライターをやっていた。結構いい収入にもなり、依頼件数も安定してあったので「フリー」として独立した。有名人の本や手記の「ゴーストライター」として、収入はサラリーマン時代よりもよかった。ポルシェも買った。
フリーライターが、ビンボウで生活に困るというイメージは、必ずしも正しくない。
父は、文学部の大学教授であったので自宅に沢山の歴史書や文献資料があった。若いときは、反発心もあり興味はなかった。
小説を書いてみようと考えて素材の収集を始めた時、父の収集した歴史全集も読んでみた。
歴史における史実を骨格にして、その行間を埋める「創作」エピソード、人物の性格を想像にてストーリーに都合よく作り上げることなど、時代小説の執筆のやり方がわかった気がした。
そこで、歴史モノというジャンル、そこに独自の取材を織り込んで、ストーリーを創作していくこと。時代背景などしっかりとリサーチし、現代にも存在するもの・職人であれば取材を繰り返した、詳細を書き込む。
さっそく、「火天の城」を文庫本で買って読破しました。
織田信長が、安土に城を築く時、築城を請け負った大工棟梁のお話。
要所要所は、史実でしょうが、大工棟梁の心情や具体的な苦労話が記録として残っているはずもなく、ストーリーと詳細のほとんどは作者の創作。
直木賞の「利休」でも、「朝鮮の美女」は創作と言っていましたし、彼女にもらった絶妙な色彩の茶壷も同様とのこと。
山本さんの、ネタばらしを聞いていて、この種の小説(歴史物ミステリー)は、それなりの設計図を書いて、詳細を想像で詰めいていく作業だな、工学的アプローチと感じました。
(ちょっと、いつか、やってみたい気持ちになりますね。そんなうまくいくはずはないだろうが)
2009年6月6日、京都新聞の主催で「ソフィア京都フォーラム2009:日本の匠 心と技」と題して、山本さん、諏訪蘇山氏(女流陶芸家)、河野美砂子氏(ピアニスト・歌人)のパネル討論がありました。
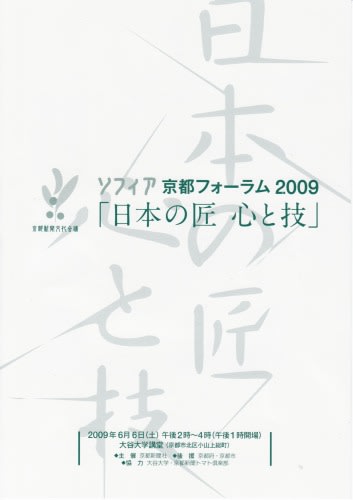
山本さんは、京都市生まれ、同志社大学文学部卒、出版社、フリーライターを経て作家に。2004年「火天の城」で松本清張賞受賞。本年、「利休にたずねよ」で第140回直木賞受賞。「火天の城」は西田敏行主演にて映画化(現在上映中)。

彼の講演で、なるほどと思ったポイントは次のとおりです。
・出版社勤務(たしか業界新聞の取材記者であった。いわゆる大手ではない)の時に、アルバイトで各種の調査記事、単発記事などライターをやっていた。結構いい収入にもなり、依頼件数も安定してあったので「フリー」として独立した。有名人の本や手記の「ゴーストライター」として、収入はサラリーマン時代よりもよかった。ポルシェも買った。
フリーライターが、ビンボウで生活に困るというイメージは、必ずしも正しくない。
父は、文学部の大学教授であったので自宅に沢山の歴史書や文献資料があった。若いときは、反発心もあり興味はなかった。
小説を書いてみようと考えて素材の収集を始めた時、父の収集した歴史全集も読んでみた。
歴史における史実を骨格にして、その行間を埋める「創作」エピソード、人物の性格を想像にてストーリーに都合よく作り上げることなど、時代小説の執筆のやり方がわかった気がした。
そこで、歴史モノというジャンル、そこに独自の取材を織り込んで、ストーリーを創作していくこと。時代背景などしっかりとリサーチし、現代にも存在するもの・職人であれば取材を繰り返した、詳細を書き込む。
さっそく、「火天の城」を文庫本で買って読破しました。
織田信長が、安土に城を築く時、築城を請け負った大工棟梁のお話。
要所要所は、史実でしょうが、大工棟梁の心情や具体的な苦労話が記録として残っているはずもなく、ストーリーと詳細のほとんどは作者の創作。
直木賞の「利休」でも、「朝鮮の美女」は創作と言っていましたし、彼女にもらった絶妙な色彩の茶壷も同様とのこと。
山本さんの、ネタばらしを聞いていて、この種の小説(歴史物ミステリー)は、それなりの設計図を書いて、詳細を想像で詰めいていく作業だな、工学的アプローチと感じました。
(ちょっと、いつか、やってみたい気持ちになりますね。そんなうまくいくはずはないだろうが)














