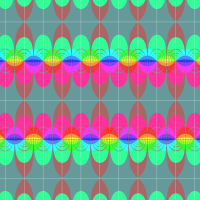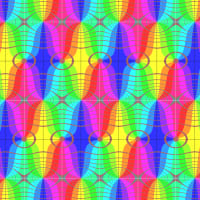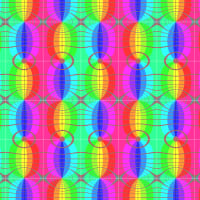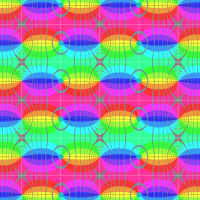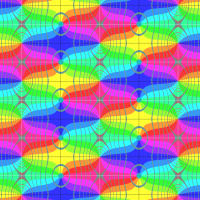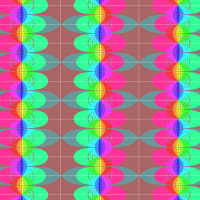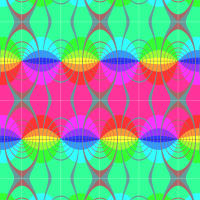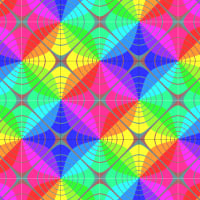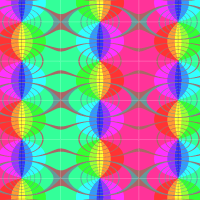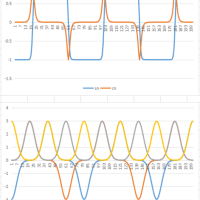雑誌、数理科学2022年5月号の特集の続き。
巻頭言で述べられているように、20世紀半ば以降の数学教育では微積分と線形代数の2本立ては決定版と私も思います。数学自体はもとより、物理・工学、化学や生物学などの需要をある程度満たし、その強力さは現代文明のきらびやかさを見ると一目瞭然と思います。
ただ、問題は中身。その特集では雑誌の記事のためかいろいろ基礎部分が吹っ飛んでいるような気がします。応用だけだったら表面的な理解で十分でしょう。大抵は分かっている人がマニュアル書いたりソフトを組んでいますから。
しかし、何か問題が起こったときに対応できなくなると思います。高校時代の印象ですが、上位の大学に行った人々の大半は過去の入試問題を解くこと無く答えを先に見てパターン認識で回答していたみたいです。もちろん、その方がずっと効率的でしょう。私はそんな面白くもなんともない行為にあきれていましたが、その場合はよほどの天才では無い限り上位の大学は無理で、私も身の丈に合った大学を選んでしまいました(後知恵ですが、この選択は後々ものすごく良かったと思っている)。
前述したように微積分は連続の概念をすっ飛ばすと単なる数式変換になっていて、もちろんその独自の数式変換法が売りの面はあります。ですから理解が間違っているとも言いがたいのですが、その先に進むのは不可能になると思います。
この特集ではわざわざε-δ法に一章を割いていて、じっくり読めば良いのかもしれませんが、冒頭で中間値の定理を頭ごなしに認めていて、下手すると循環論法になっているような気がしてきたので思わずざっと見してしましました。
中間値の定理は公理に匹敵する代物です。つまり連続の概念と同等です。今はなぜかなかなか出てきませんが、アルキメデスの原理(性質、公理とも)が初期の重要概念みたいです。それとガロア理論が全く出てこないのも手落ちのような気がします。
とはいえ、前述したように応用分野から見ると実数とは何か、連続とは何かは些細な問題です。目の前の測定値は普通は離散量(ガイガーカウンタなど)か連続値(普通に物差しとかアナログの電流計とか)ですから。
それよりも問題と思えるのは線形代数が意外にちゃんと理解されていないように思えることです。
ややくどくなってきたので、いったん中止します。続きを書いてみて内容が面白く感じたら掲載すると思います。
巻頭言で述べられているように、20世紀半ば以降の数学教育では微積分と線形代数の2本立ては決定版と私も思います。数学自体はもとより、物理・工学、化学や生物学などの需要をある程度満たし、その強力さは現代文明のきらびやかさを見ると一目瞭然と思います。
ただ、問題は中身。その特集では雑誌の記事のためかいろいろ基礎部分が吹っ飛んでいるような気がします。応用だけだったら表面的な理解で十分でしょう。大抵は分かっている人がマニュアル書いたりソフトを組んでいますから。
しかし、何か問題が起こったときに対応できなくなると思います。高校時代の印象ですが、上位の大学に行った人々の大半は過去の入試問題を解くこと無く答えを先に見てパターン認識で回答していたみたいです。もちろん、その方がずっと効率的でしょう。私はそんな面白くもなんともない行為にあきれていましたが、その場合はよほどの天才では無い限り上位の大学は無理で、私も身の丈に合った大学を選んでしまいました(後知恵ですが、この選択は後々ものすごく良かったと思っている)。
前述したように微積分は連続の概念をすっ飛ばすと単なる数式変換になっていて、もちろんその独自の数式変換法が売りの面はあります。ですから理解が間違っているとも言いがたいのですが、その先に進むのは不可能になると思います。
この特集ではわざわざε-δ法に一章を割いていて、じっくり読めば良いのかもしれませんが、冒頭で中間値の定理を頭ごなしに認めていて、下手すると循環論法になっているような気がしてきたので思わずざっと見してしましました。
中間値の定理は公理に匹敵する代物です。つまり連続の概念と同等です。今はなぜかなかなか出てきませんが、アルキメデスの原理(性質、公理とも)が初期の重要概念みたいです。それとガロア理論が全く出てこないのも手落ちのような気がします。
とはいえ、前述したように応用分野から見ると実数とは何か、連続とは何かは些細な問題です。目の前の測定値は普通は離散量(ガイガーカウンタなど)か連続値(普通に物差しとかアナログの電流計とか)ですから。
それよりも問題と思えるのは線形代数が意外にちゃんと理解されていないように思えることです。
ややくどくなってきたので、いったん中止します。続きを書いてみて内容が面白く感じたら掲載すると思います。