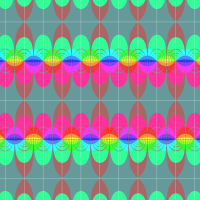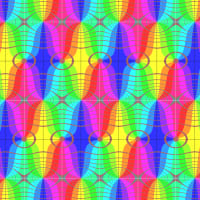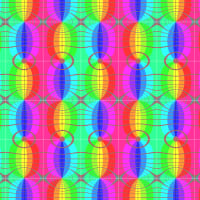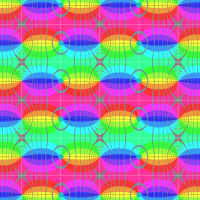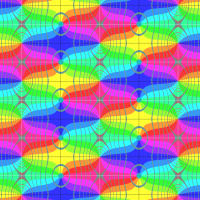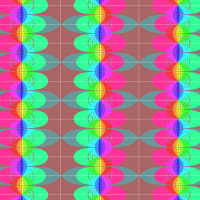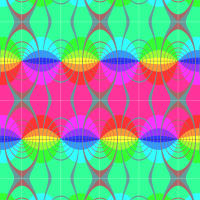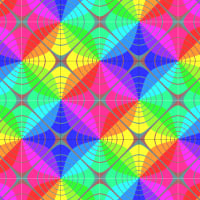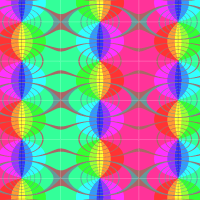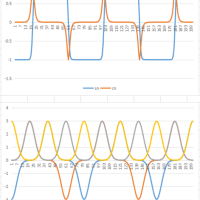最初に読んだpython 3の入門書は分厚くて実行例が多くて助かります。しかし、教科書というよりは解説書で、文法を網羅しているかどうかはやや不明。なので途中から速読してしまいました。もう一つの決定版と裏表紙に書いてある入門書に移りたいと思います。
こちらはパラパラと眺めた分には教科書風の感じがします。ただし、python 2の後期に書かれたもので、一応、python 3対応となっていて、それらしいキーワードはありますし、現在売られている、ということは差し支えないみたいですが、micro pythonはpython 3対応のはずなので、どうなるか。
でまだ、肝心のfx-CG100のmico pythonは動かしていません。
そうそう、classwizシリーズへの批判の矢面に立ってしまったformatキーの動作は改善されています。関数電卓としてはややごつくて重い感じですが、TIの教育用グラフィック電卓もこんな感じです。ポケコンと考えれば大きさも重さもお値段も普通のような気がします。
この電卓のmicro pythonの操作性が良ければ、こちらをメインにしても良いと思います。それを探っている訳。
本来のpythonならあるはずのdequeと正規表現(パターンマッチング)とbtreeがあれば私的にはほぼ完璧ですが、多分、ありません。
基本のpythonが用意しているデータは数値と文字列の基本型と、複合型としてタプル、リスト、辞書、があります。タプルは構造とか構造体とか複合項と呼ばれるもので、集合論の一要素に相当します。とりあえず、空間座標の(x, y, z)の感じだ、と思えば良いようです。統計学の標本の一個と言えば分かる方には分かると思います。
リストはLISPのリストと同様の線形リストのようです。が、基本関数(?)が末尾を操作する .append()と .pop()みたいなので、私が連想するリストとは逆順です。中身が知りたいところで、今度の本に書いてあるかな。
辞書の存在は一瞬喜んだのですが、順序の無いハッシュ表みたいです。これがあるだけでも大変な威力ではあるものの、ちょっと惜しい感じがします。
オブジェクト指向の計算機言語ということで、その系統の計算機言語(C++など)を知らないと理解困難な箇所があります。従来型のC言語などを深く知っている人ほど困惑すると思います。
いわゆるルーチン内のサブルーチンは局所関数として書くみたいです。この動作がLISPのfunctionの感じらしく、ややユニークと思います。実機で動作を試してみたいと思います。