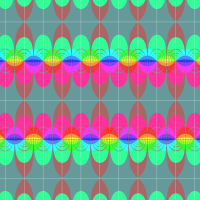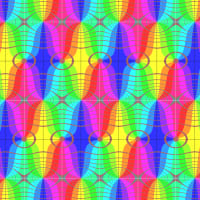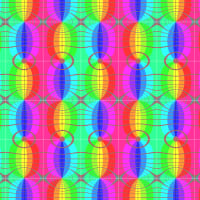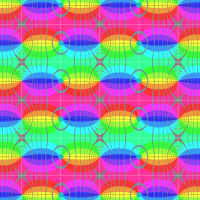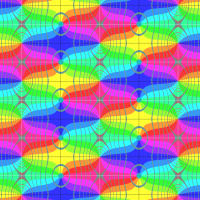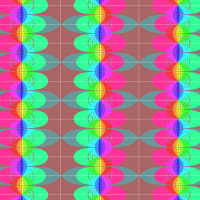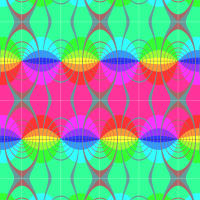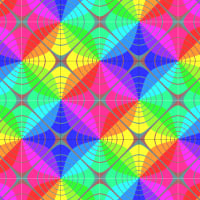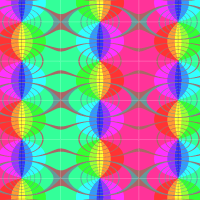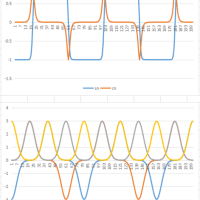話が逸れたのでビデオゲームについては一旦保留します。今のところPS3の時代が続いている感じで、ハイビジョン規格がいかに優れていたかを証明している感じになっています(内容はずっとモダンになっている)。あと、かつては3Dアクセラレータと呼ばれたGPU、つまりポリゴン立体(OpenGLなど)と。
ポケコンは関数電卓+tinyBASICと考えれば良い装置です。アルゴリズム部分を簡易BASICで記述し、データ構造としては浮動小数点実数(十進10桁程度)とその配列が使えました。計算機言語での普通の整数の概念は無く(配列の要素の指定にはその実数を使う)、文字列は原始的なものだけだったと思います。
逆に、元来のtinyBASICは整数(符号付き二進16bit)しか扱えず、複合データは(整数の)配列だけです。文字列は画面出力用の固定文字列のみ。
ポケコンのRAMはCMOSで電池バックアップの不揮発性でした。ここは今の並みのPCよりも優れています。メモリの容量は初期には2KBほどで、後期には32KB程度が普通だったと思います。BASICシステムはそれとは別のROMに入っていて、こちらがRAM領域を圧迫することはありません。CPUは8bit系が多かったはずです。クロック数はせいぜい10MHz程度と思います。
当時はいわゆるパソコンはセット(本体+CRTモニタ+フロッピーディスク(FD)+プリンタ。JIS系キーボードは本体付属。マウスは不要)で50万円ほどの装置と思えば良く、それよりはずっと経済的なコンピュータでした。
元々は私のような技術屋がちょっとした科学技術計算に使う、つまり関数電卓の発展系(高級プログラム電卓)として開発されたと思います。しかし、安いので今で言うオタク、趣味の方々が殺到しました。実用方面ではそのころ流行していたQC(品質管理)の道具として計算尺みたいな感覚で使われていたと思います。こちらは程なく表計算ソフトに移行し、さらに専用ソフトに移行していったはずです。
ですからゲームは格好のターゲットで、当時のマイコン雑誌に掲載されていたはずです(うろ覚え)。表示はASCII(+カタカナなど)の24桁1行とか4行とかです。128×32ドット白黒などのビットマップもあったような気がしますが、使い勝手はパソコンBASIC比で良くなかったです。
外部との入出力は大問題で、おそらく多分後述します(気が向いたら)。話題のメインは行番号BASICの歴史的位置づけです。
ポケコンは関数電卓+tinyBASICと考えれば良い装置です。アルゴリズム部分を簡易BASICで記述し、データ構造としては浮動小数点実数(十進10桁程度)とその配列が使えました。計算機言語での普通の整数の概念は無く(配列の要素の指定にはその実数を使う)、文字列は原始的なものだけだったと思います。
逆に、元来のtinyBASICは整数(符号付き二進16bit)しか扱えず、複合データは(整数の)配列だけです。文字列は画面出力用の固定文字列のみ。
ポケコンのRAMはCMOSで電池バックアップの不揮発性でした。ここは今の並みのPCよりも優れています。メモリの容量は初期には2KBほどで、後期には32KB程度が普通だったと思います。BASICシステムはそれとは別のROMに入っていて、こちらがRAM領域を圧迫することはありません。CPUは8bit系が多かったはずです。クロック数はせいぜい10MHz程度と思います。
当時はいわゆるパソコンはセット(本体+CRTモニタ+フロッピーディスク(FD)+プリンタ。JIS系キーボードは本体付属。マウスは不要)で50万円ほどの装置と思えば良く、それよりはずっと経済的なコンピュータでした。
元々は私のような技術屋がちょっとした科学技術計算に使う、つまり関数電卓の発展系(高級プログラム電卓)として開発されたと思います。しかし、安いので今で言うオタク、趣味の方々が殺到しました。実用方面ではそのころ流行していたQC(品質管理)の道具として計算尺みたいな感覚で使われていたと思います。こちらは程なく表計算ソフトに移行し、さらに専用ソフトに移行していったはずです。
ですからゲームは格好のターゲットで、当時のマイコン雑誌に掲載されていたはずです(うろ覚え)。表示はASCII(+カタカナなど)の24桁1行とか4行とかです。128×32ドット白黒などのビットマップもあったような気がしますが、使い勝手はパソコンBASIC比で良くなかったです。
外部との入出力は大問題で、おそらく多分後述します(気が向いたら)。話題のメインは行番号BASICの歴史的位置づけです。