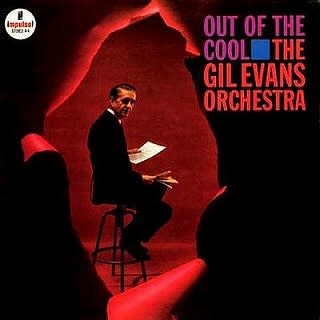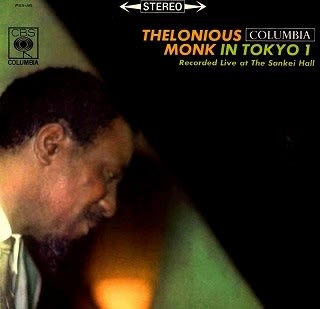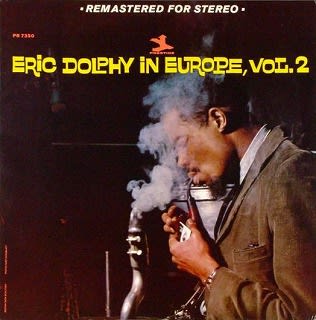■I Talk With The Spirits / Roland Kirk (Limelight)
複数管同時吹き、息継ぎ無し(?)吹奏、その為に独自考案したという珍しい管楽器や日常的な鳴り物等々を堂々と駆使しながら、実は誰よりもモダンジャズの王道を歩もうとしていたのが、ローランド・カークだったと思います。
しかし、失礼ながら本人には盲目というハンデがあった事もあり、そうした姿勢が結局はキワモノ扱いされていた現実は否定出来ません。
実際、ゴッツイ黒人がグラサン姿で不思議な楽器や鳴り物をぶら下げ、臨機応変にそれらを操っている写真を最初に見たサイケおやじは、完全に???!?
そして超人的な演奏が記録されたレコードを聴いて、吃驚仰天!?!
正直、最初はどうやって吹いているのか、想像もつかない部分さえありましたし、映像ではありますが、初めて動くローランド・カークに接した時は大袈裟ではなく、感動しましたですねぇ。
このあたりは現在、DVDも出回っていますので、一度はご覧いただきとうございますが、さらにもうひとつ、凄いなぁ~と思ったのは、ローランド・カークが実に正統的な楽器の鳴らし方を身につけている事で、例えばテナーサックス奏者としての存在感は決して軽く無いでしょう。
で、同じように凄いというか、味わい深いのがフルートやピッコロでの実力で、本日ご紹介の1枚は、まさにそれに徹して全篇を作り上げた裏名盤だと思います。
録音は1964年9月16&17日、メンバーはローランド・カーク(fl,vo,etc)、ホレス・パーラン(p)、マイケル・フレミング(b)、ウォルター・パーキンス(ds,per) が中心となり、適宜ゲストが参加しています。
A-1 Serenade To A Cuckoo
ローランド・カークのオリジナルとされていますが、聴けば誰もが、どっかで……?
そう思うほどに親しみ易い曲メロが素敵です。
しかもタイトルどおり、カッコーの鳴き声を模したというか、イントロから鳩時計と思しき効果音やフルート&ピッコロによる音楽的表現が冴えわたり、加えてモダンジャズ王道のクールでグルーヴィな4ビートが的確に融合しているのですから、たまりません♪♪~♪
さらにローランド・カークならではの巧みな息遣いを利用したアドリブのジャズ的な実用度の高さも快適至極ですし、クリスタル・ジョイ・アルバートという女性歌手のスキャットボーカルが絶妙に使われるあたりは、1960年代映画の劇伴サントラの趣まであるんですから、ねぇ~~♪
ホレス・パーランの短いアドリブも、独得のピアノタッチがニクイです。
A-2 Medley
We'll Be Together Again
People
これは有名なスタンダード曲という事で、お馴染みのメロデイを意外なほどすんなりと聞かせてくれるローランド・カークのフルートからは、その実力が充分認知されるはずです。
もちろん呻き声(?)や語り調で歌詞を呟く手法は、分かっちゃいるけど、ニヤリとさせられる瞬間でしょうねぇ~♪
その、あまりにも素直な歌心には、驚かれるかもしれません。
A-3 A Quote From Clifford Brown
アップテンポの正統派4ビートで演じられるハードバップのブルースは、タイトルどおり、どうやらクリフォード・ブラウンのアドリブフレーズが利用されているのかもしれませんが、それに拘る以前にローランド・カークのジャズ魂は真っ向勝負に輝いています。
リズム隊の実直なノリを背景に、なにやら様々な事をやらかすローランド・カークのオチャメなところは???ではありますが……。
A-4 Tree
これまた、どっかで聞いたことがあるようなメロディが心地良い、ローランド・カークならではのオリジナル曲です。
もちろんバックはモダンジャズ王道路線の4ビートで、なかなかグルーヴィな雰囲気を盛り上げていますが、それにしてもアグレッシヴなフルートを熱演するリーダーのアクの強さは唯一無二! なんとなくリズム隊が翻弄される瞬間さえあるような感じでしょうか。
しかしホレス・パーランの本気度は高く、変則ワルツビートっぽいノリやアドリブの面白さは特筆物だと思います。
A-5 Fugue'n And Alludin'
これは短い、つまりはLP片面終了の場面転換を意図した演奏なのかもしれません。
それはバロックのメロディと手法を借用したもので、神妙に演じた後にオチャラケるローランド・カークが憎めませんねぇ~♪
ちなみにヴァイブラフォンはボブ・モーゼスが担当したという事です。
B-1 The Business Ain't Nothin' But The Blues
これまたローランド・カークが十八番というか、黒人ブルースやR&Bの「お約束」をたっぷりと転用させた粘っこいモダンジャズで、その黒っぽい雰囲気の醸し出し方は流石!
しかも素直に分かり易いんですよねぇ~♪
まあ、このあたりの率直な表現方法が、ヒネクレタ感性を至上主義とする我国の玄人ジャズファンには嫌悪される部分なのかもしれませんが、虚心坦懐どころかストレートに受け入れてしまうだけの快楽性は、何もこの演奏だけではなく、ローランド・カークが提供する全てに共通するものだと思います。
ホレス・パーランにしても、この手のグルーヴは得意技ですし、絶対にキワモノとは決めつけられない、これぞっ、立派なモダンジャズ!
B-2 I Talk With The Spirits
アルバムタイトル曲も、これまたローランド・カークの狙いがミエミエという仕掛がイヤミ寸前ではありますが、ちょいとエスニックな導入部から幽玄のメロディ展開、そして原始のムードが強く滲む静謐なソロパフォーマンスには、不思議と惹き込まれてしまいます。
B-3 Ruined Casties
これはズバリ!
「荒城の月」なんですねぇ~、滝廉太郎のっ!
それを堂々と自らのオリジナルとクレジットしたローランド・カークの胸中は如何に???
短い原曲メロディだけの演奏ですから、日本人なら怒るよりは、ニンマリして聴きましょうね。
B-4 Django
お馴染み、MJQの人気ヒット曲がノリノリの4ビートで演じられる、唯それだけでモダンジャズを聴く喜びに満たされるんですから、如何にローランド・カークが正統派のプレイヤーなのか、納得するしかないと思います。
決して妙なケレンはやっていないところが逆に物足りない?
そんな我儘さえ言いたくなるのが不思議なのは、この天才を認められない証拠かもしれませんが。
B-5 My Ship
これも有名スタンダード曲ですから、その魅惑のメロディをジンワリと吹きつつ、次第に感情が高ぶっていくが如きアドリブ表現へと踏み込むローランド・カークの見事な目論見!
いゃ~~、これがジャズかもしれませんねぇ~♪
ということで、なかなか痛快にして味わい深いアルバムです。
一般にローランド・カークはアトランティック期の作品が人気高かもしれませんが、極言すれば駄作を残さなかった稀な演奏家だと思います。
ただし、そこに十人十色の好き嫌いがあるのは否定出来ません。
その意味で、本日ご紹介の1枚は、なかなか人気の共通度も高いアルバムでしょう。
ちなみにジャズ喫茶では「荒城の月」ゆえにB面が定番かもしれませんが、CDならば、ぶっ通し鑑賞がOKかもしれません。
それほど素敵な演奏集なのでした。