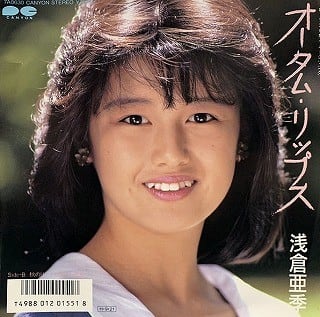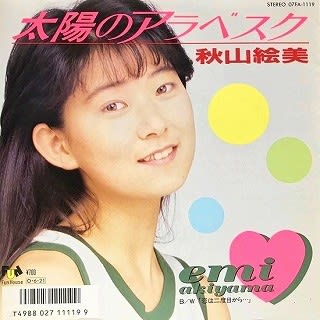■あまぐも / ちあきなおみ (日本コロムビア)

現在は実質引退状況にあればこそ、ちあきなおみの芸歴は俯瞰出来るとするならば、その過程において幾つか在った転機の中でも、殊更昭和52(1977)年頃から、ニューミュージック系の楽曲を専心して歌い始めた活動は特筆すべき事かと思います。
説明不要ではありますが、公式レコードデビュー以降の彼女はポップス歌謡から演歌を含む正統派歌謡曲の世界で大輪の花を咲かせていたのですから、なにも……、あらためて……云々という批評は確かにあったとはいえ、とにかくも昭和52(1977)年4月に突如(?)中島みゆきがから提供のシングル曲「ルージュ」を出して以降、超問題作となった「夜へ急ぐ人」で爆発的な話題を呼び、ついに翌年発売となった本日掲載のシングル盤A面曲「あまぐも」では、決定的なAORサウンドに彩られた歌謡世界を披露したのですから、たまりません (^^♪
サイケおやじがチマチマと書いていた当時のメモを読み返してみれば、これを初めて聴いたのは昭和53(1978)年3月、夜の街で流れていた有線放送からだったみたいで、その時の強い印象が後々まで残ったものですから、掲載盤もリアルタイムでゲットした1枚です。
そしてレコードに針を落しつつ、何度も鑑賞し、やるせなくも甘美な歌と演奏にシビレまくったわけですが、製作クレジットを確認すれば、作詞作曲:河島英五&編曲:ミッキー吉野という、これは納得出来そうで、それなりに違和感を覚えたのも正直な気持ちです。
なにしろ楽曲を提供した河島英五と云えば、野性的な風貌と例えば昭和51(1976)年に自身のソロ名義で発売以来、ロングセラー化していた「酒と泪と男と女」に代表される所謂「フォーク系男唄」のイメージが強かったですから、この「あまぐも」で書かれたアンニュイな女心の歌謡世界は凡そ似つかわしくないはずが、この……、ジャストミート感はっ!?!
それはイントロから絶妙の雰囲気を醸し出すエレピ、どっしりと腰の据わったドラムス、ソフト&メロウなギターにシンプルな歌心を滲ませるベースという、極めてシンプルな伴奏があればこそ、ちあきなおみの卓越した歌唱力が、じっくりとそこにある「歌」を表現する時、ミディアムテンポのドラマチック歌謡が完全無欠にリスナーの耳に届けられるという素晴らしさは唯一無二 (^^♪
もちろん、ここでの演奏パートはミッキー吉野のアレンジということは、当然ながらミッキー吉野(key) 以下、浅野孝已(g)、スティーヴ・フォックス(b)、トミー・スナイダー(ds,fl) という、リアルタイムのゴダイゴのメンバーによるものですから、自然体の纏まりの良さは最高であり、絶妙にスティーリー・ダン風の隙間の多いカラオケが作られたのも、それを埋めるが如き、ちあきなおみの絶対的な歌唱力を想定してのプロデュースだった様に思います。
逆に言えば、このカラオケで、この「あまぐも」を歌えるのは、ちあきなおみ以外、存在しないと思うほどなんですよ、サイケおやじにはっ!
特にサビを歌い出す瞬間と呼応して煌めくエレピのフレーズとサウンドの存在感には、何度聴いても、ゾクゾクさせられるんですねぇ~~♪
ですから、こ~して素晴らし過ぎるトラックに接した後は必然として、同時期に発表されていたLP「あまぐも」をゲットし、聴きまくったわけですが、その傑作についても追々書き記す所存です <(_ _)>
そして、この「あまぐも」を含む彼女のLP「あまぐも」こそは、我が国AOR歌謡の決定的な名作と断じて、後悔しないサイケおやじではありますが、ここで「AOR」という言葉を安易に用いた点については本来、それは「Album-Oriented Rock」、つまりはシングルヒットよりは、アルバムをメインに楽しめるロックという欧米の音楽用語が、我が国では「Adult-Oriented Rock」として解釈される和製英語化した業界用語となって広く通用されているもんですから、サイケおやじにとっても後者の方が馴染んでいるというか…… (^^;
まあ……、何れにせよ、大人の琴線に触れる素敵な音楽にちがいないわけですよねっ!
ちあきなおみには、それこそが相応しいんじゃ~ないでしょうか (^^)
このシングル曲「あまぐも」には、それが集約されている気がしております <(_ _)>