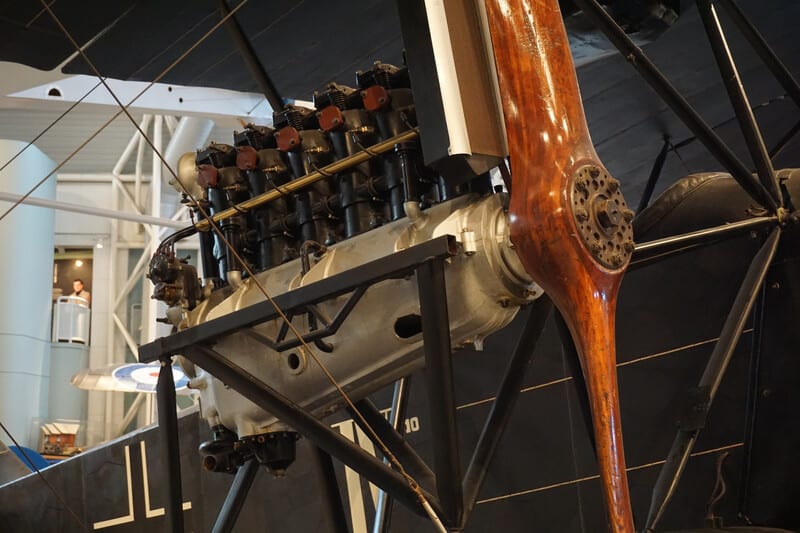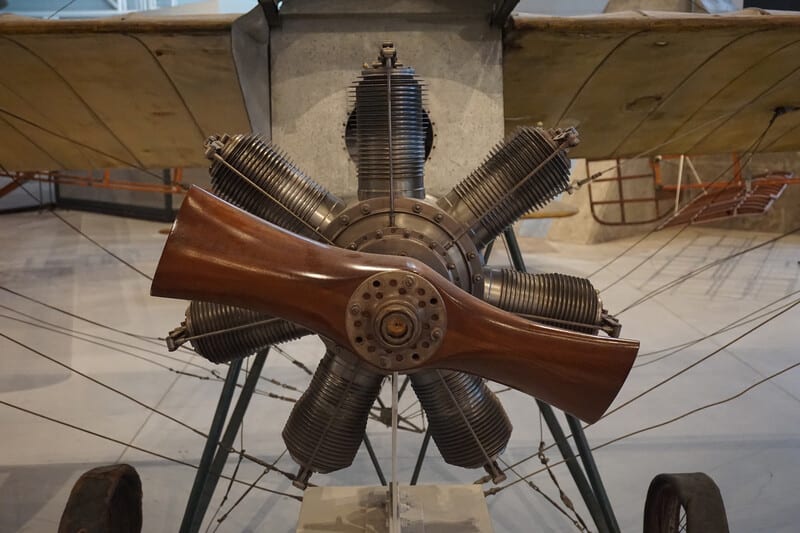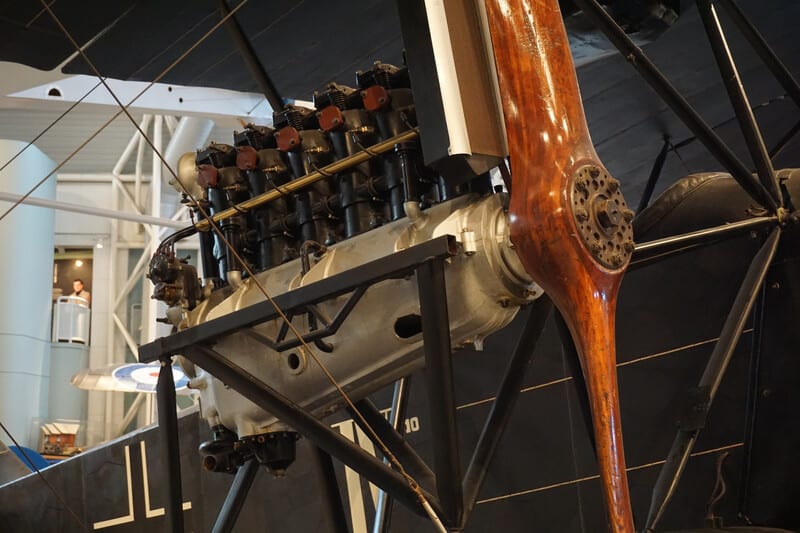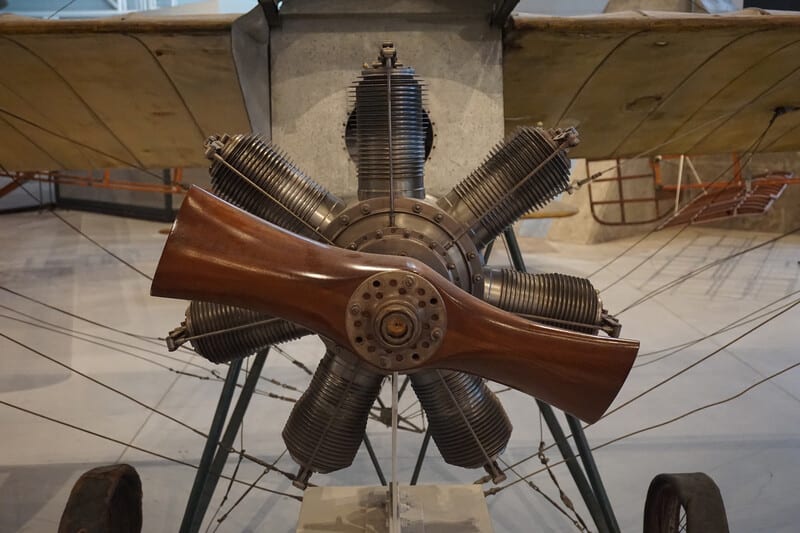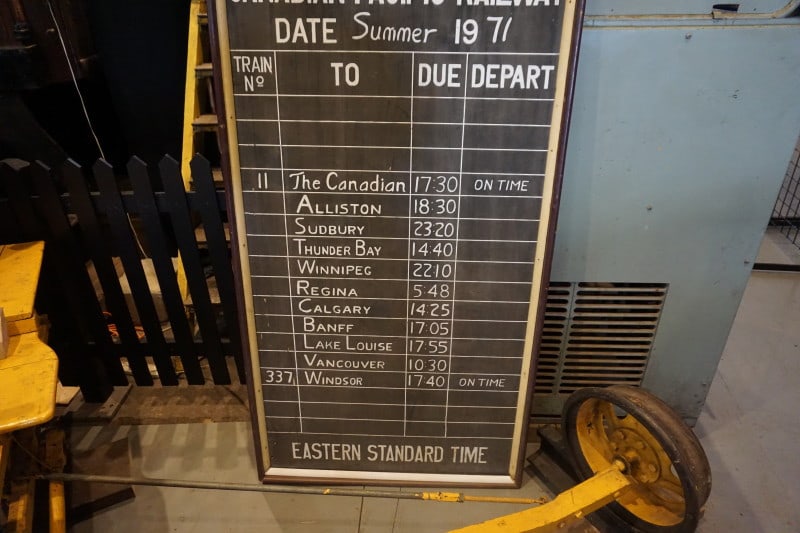トロント鉄道博物館の続きです。前回に続き屋外展示車両を見て回ります。
これは前回記事で紹介したCPのアルコS-2形7020号機の第2エンド側。
これはカナディアンパシフィック鉄道 (CP) の188625号ファウラー有蓋車。
一口に有蓋車といっても色々奥が深いわけですが、これはファウラー有蓋車 (Fowler boxcar) という種類に当たります。これはいわば、軽量と低価格を実現するために開発された有蓋車で、カナダ国内で大量に製造、運用された貨車です。
1900年代の有蓋車の荷室部分、つまり箱の構造は、骨格の周りに木製外板を骨格の外側と内側の両面に貼り付けて構成されていました。骨格は19世紀までは木製でしたが、20世紀に入ると衝突安全性の観点から鋼製の物が登場してきました。
CPの技師W・E・ファウラーは、車両メーカーのドミニオン・カー&ファウンドリー社と協同して、1908年に3種類の36ft長、積載量40tの穀物輸送用有蓋車のプロトタイプを開発しました。その中から、車体側面のN字形の鋼製骨格に外側の外板を省略した物が選定されました。これが「ファウラー有蓋車」です。外板を内側のみとすることで製造費用の削減と軽量化を実現しました。また、修理も容易だったと言われています。
1908年の初回発注では500両が製造されましたが翌年には1,000両が追加発注されました。CP向けの貨車でしたがカナディアンナショナル鉄道 (CN) にも製造され、さらに第一次世界大戦による需要増でカナダ向けに70,000両以上が大量製造されました。そのうちCP向けだけでも30,000両以上製造されました。36ft長に加えて40ft長の貨車もラインナップに加わり、経済性の高さもあってかアメリカでも普及していったそうな。
その後1950年代には全金製有蓋車が登場し、穀物輸送は荷役の手間の減るホッパー車に取って代わられるようになりましたが、ファウラー有蓋車はしぶとく走り続け最後の車は1980年代まで現役だったそうです。
さてこの188625号は、第一次世界大戦真っ最中の1917年に製造された個体です。廃車時期は分かりませんでした。
どこの馬の骨とも知れない貨車移動機、もといこの博物館所蔵の1号機です。
カナディアン・ロコモティブ社が1950年にライセンス生産した50トン級入換機です。ライセンス元はアメリカのウィットコム・ロコモティブ社 (Whitcomb Locomotive Co.) で、ご存知ボールドウィン社の子会社でした。
これは石灰石採石場用に製造されたものでした。他にも骨材や建設資材運搬等で活躍して1997年廃車。2007年にトロント鉄道博物館が購入しました。
典型的なセンターキャブの貨車移動機で、ロッド式の動輪が古めかしくて素敵です。
博物館がこれを取得後、エンジンの復元を行って見事再稼働状態へ。この博物館の1号機関車として収蔵車両の入換作業に従事しているのです。ちなみに塗装は、トロント・ハミルトン&バッファロー鉄道をモチーフにしているとかで。
これも電気式ディーゼルなので、ロッド式の動輪に目が行きがちですが電車っぽい台車なのです。
カナディアンナショナル鉄道 (CN) の蒸気機関車U-2-g形6213号機です。当館の目玉車両であります。
車輪配置は4-8-4ノーザン(呼び方は会社により異なるがCNではこれ)です。8輪の大直径動輪(U-2-g形の動輪直径は1,854mm)を活かした牽引性能と高速性能を兼ね備えた配置なのです。
6213号機は1942年CNのモントリオール工場で製造され、カナダ東部ハリファックスからサスカチュワン州までを主な運用範囲としていました。1959年に退役し、部品取り車となります。蒸気機関車時代の終焉が近づいていた当時、トロントの鉄道愛好会が6213号機の価値を見出しトロント市に寄贈する動きを見せます。1960年、現存する中でトロント地域で運用されていた最後の蒸気機関車として6213号機が選ばれます。剥ぎ取られた部品は復元されて、同年トロント市に寄贈されて今に至ります。
当館で唯一の蒸気機関車で、転車台の反対側からでも伝わってくる大きさと存在感があります。しかし近づくことができなかったのでちょっと残念でした。
どこの馬の骨とも知れない貨車移動機。現地にもホームページにも特に説明がないのでよく分からない機関車です。
銘板を見てみたら1948年ボールドウィン製で、CPのDS-10g形とありました。あとはググってみると7069号機で、ボールドウィンの社内型式はDS-4-4-1000-SC形なんだそうな。DS-10gは、CP内の型式だと思います。
DS-4-4-1000-SCは、4軸動輪、1,000馬力エンジン搭載車のスイッチャーです。前期型の8気筒NAエンジンの608NA型と後期型の6気筒ターボ付きエンジンの606SC型がありにけり。7069号機は後者だと思われ。
CPの機関車は、このマルーンと灰色の2トーン塗装がやっぱり好きなんですよ。気品があるじゃないですか。
CNのGMD製GP7形のGR-15a形4803号機です。
GP7形はEMDが開発したロードスイッチャーです。ロードスイッチャーの元祖はアルコのRS-1形で、エンジンフードとセミセンターキャブの形態です。GP7形は当時のロードスイッチャーの決定版として普及していき、使い勝手の良さから従来のキャブ型ディーゼル機関車に代わって北米のディーゼル機関車の標準型の形態となっていくのです。製造機数は7,000機!
エンジンは16気筒、9000cc、1500馬力で、発電した電気で4台の電動機を回します。発電ブレーキも備えています。最大で8機を総括制御できます。
この4803号機は、EMDのカナダ法人であるGMDで1953年に製造されました。CN線内のあらゆる場所を走っていたそうですが、台車が軽量化されていたので西部の低規格路線でも走れたらしく、秋の穀物収穫期には優先的にそこで運用されていたそうな。1984年廃車で、その直後にトロント市150周年事業として同市に寄贈されて今に至ります。
ロードスイッチャーなので前後どちらにも走行できるんですが、フードの短いほうが前方とされています。
GP7形は、前後のエンジンフードの高さが揃っています。特に前方側のフードが高いのです。高さが揃っているので見た目は美しいですが、前方視界は悪いですよね。このようなフードをハイノーズと呼びます。
ハイノーズになったのは、労働者対策とも言われています。GP7形は蒸気機関車の置き換えにも使われたのですが、2名乗務だった蒸気機関車から1名乗務のディーゼル機関車に代わると片方の乗務員は職にあぶれてしまいます。そこで、わざと前方視界を悪くして2人目の乗務員にも前方監視の仕事を与えたのだ・・・ということらしいです。
そんな非効率的なことも長くは続かないので1名乗務に移行していくんですが、そうなるとやっぱり前方視界が悪いのでノーズ高さを切り詰めたローノーズに改造される事例が増えました。ハイノーズはこれに対する言葉なのですね。
大半のGP7形がローノーズに改造されたらしく、4803号機のようにハイノーズで現存する個体は貴重なのだそうです。それ以外にも、4803号機は比較的原型をよく留めていると言われています。ただし電動機は撤去されています。
緑と黄色を基調としたCNの1960年代以前の塗装です。これも好きなんですよね。4803号機は塗装もピカピカで素晴らしいです。
台車は2軸ボギーです。B-B配置、日本で言うところのD級機です。EMDのGP系機関車は以降も一貫して4軸機として製造されています。ちなみにGPというのは「汎用」を意味します。現地のギークは「ジープ」と呼んどるそうな(Jeepとは発音が違うんでしょうけども)。
当時はなんとなく撮影していた台車ですけど、一般的なGP7形とは違う台車を履いています、これ。
一般的にはブロンバーグ台車 (Blomberg truck) という物を履いてるんですが、これはフレキシコイル台車 (Flexicoil truck) という種類だそうな。肝心のコイルばねが見えないのであまりはっきりしたことは言えんですが、枕ばねにコイルばねを使った台車のことなんじゃないスカね。ブロンバーグ台車は板バネだし。
フレキシコイル台車は1952年に登場したGP7形の6軸版(C-C配置)であるSD7形用に開発された3軸台車が最初です。SD7自体はほとんど売れませんでしたが・・・(製造数150機未満)。
その後2軸台車版も開発されて、GP7形にもオプションで付けられるようになっています。前述の通り、どういうからくりか知りませんがブロンバーグ台車と比べて軽量化されていたので、軸重を低くしたい目的で履かせていた可能性はありますな。
キャットウォークは歩くことができました。そこからキャブを覗き見。運転機器を斜めに配置するのはこの頃からなのね。日本のDE10も斜めに置けば首の疲労も低減されたのでは。
CNの木製カブース79144号です。カブースというのは日本で言うところの車掌車です。
1920年製の有蓋車424669号を1957年に改造して造った物。貨車改造のカブースって初めて聞きましたけど、そういう事例ってもしかして結構あるんですかね。
1970年代に廃車になって、個人が引き取って事務所兼住まいとして置いていたそうです。カブースは保存車両としては実用性ありますし。2014年に当館に寄贈されて2015年までに復元されて今に至ります。なのでまだ復元されたてといっていいでしょう。
手ブレーキ。
台枠や足回りは改造されていないそうなので、当時物の板バネ台車を履いたままです。
CNのロゴマークです。
反対側から。
もう一台のカブース、トロント・ハミルトン&バッファロー鉄道(TH&B)70号です。
TH&Bが1921年に製造したカブースで、その時の車体は木造でした。1950年代に外板を鋼製にして半鋼製車となっています。
TH&Bは、1892年設立の鉄道で、名前通りハミルトン地域のローカル鉄道です。1895年にはCPとニューヨークセントラル鉄道により買収されて両社の傘下になります。1987年にCPに吸収されて会社としては消えてしまいました。今も路線はCPが保有してるほか、ハミルトン駅はGOトランジットの旅客駅として使用されています。
というところで今日はここまで。
その36へ→