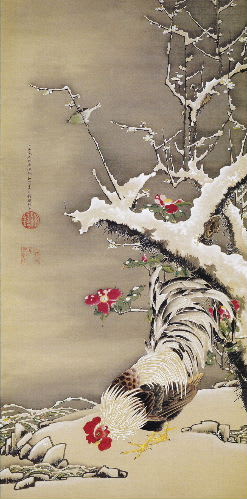伊賀寺社巡りのメインの一つである新大仏寺に到着。
ここは何といっても盧遮那仏でしょう。
お会い出来るのが楽しみです。

山門前に大型無料駐車場がありました。
いざ参拝開始。
所在地:三重県伊賀市富永1238番地
宗派:真言宗智山派
御本尊:盧遮那仏
創建:建仁2年(1202)
開基:源頼朝
開山:重源上人
【縁起】
源頼朝が後鳥羽法皇の勅願寺として開創、
重源を開山として創建されたと伝えられる。
重源は鎌倉時代に東大寺大仏と大仏殿の復興事業を指揮した僧として知られ、
当寺は東大寺の伊賀別所となった。
新大仏寺と称する所は重源上人が東大寺に敬意をはらって、
寺の名前に新の字を加えた。
その後、長らく衰退し戦国時代末期にはかなり酷い状態であった。
新大仏寺を訪れた松尾芭蕉はその様子を笈の小文や伊賀新大仏之記で記している。
再建されたのは江戸時代中期の寛延年間(1748-1751)のことである。
【大門】

とても立派な山門です。

扁額に東大寺伊賀別所と書かれています。
【仁王像】


【明王殿】

これはどう見ても交通安全祈祷殿ですね。

やはりお不動さんがいらっしゃいました。
【白寿観音像】

足元に爺さん婆さんがいました。
このパターンはどっかのお寺で見た記憶があるな。
【慈母観音】

子供がモロ人間でちょっと違和感がある。(^^;
【本坊】

御朱印や拝観受付はここでは無く、
明王殿前にある売店である寺務所となります。
【石塔】

【石仏】

これは善光寺式如来ですかね。
【鐘楼堂】


【十三重搭】

【鎮守社】

【大師堂】

元文3年(1738年)に護摩堂として建立されたもので、
ペリーが浦賀に来た時は国難消除の祈祷を修したそうです。
【大仏殿】

享保12年(1727)から延享5年(1748)にかけて建立されたもの。



元々の御本尊である大仏如来を祀っていたので、
大仏殿となっていますが、現在は釈迦如来が祀られていました。

地蔵菩薩と役行者が祀られていて、
なかなか立派な地蔵菩薩でした。

堂内外陣は砂でした。
こういうお堂はたまにありますね。
【岩屋不動明王】


大仏殿の裏手に回ると滝場があり、
そこには6メートルもの不動明王が祀られています。

ここからだとお顔が見えない。(泣)
滝場は水行をしないと入れないとのこと。
【石仏】

【護摩祈祷堂】

不動明王が見れなくて残念だなぁと思いながら反対側に回って見ると、
中に入れることが判明。
寺務所の方に確認してみると入っても良いとのこと。

何とも厳かな雰囲気。

ガラス越しに御対面。


江戸時代より多くの修行者の願いを受け止めてこられました。

最初見た時、ちょっとびびった。(^^;
【鎮守社】

【本堂】

これが本堂なのね。
てっきり横の大仏殿が本堂かと思ってたよ。
寛永9年(1632年)上野城主藤堂大学助髙次公が、
雨乞い祈願成就の御礼として寄進されたもの。

元俊乗房重源像をまつった由縁から上人堂と称するが、
現在は阿弥陀如来が祀られていました。
【鎮守社】


【新大仏殿】

ここだけ拝観料300円が必要です。
まずは二階に上がり盧遮那仏とご対面です。
この新大仏殿は外よりもヒンヤリとしていて寒い。
【盧遮那仏】

撮影禁止でしたので伊賀上野観光協会より拝借。
素晴らしい。
息を飲む程の見事な大仏様です。
快慶作ということでしたが、そんなに快慶の雰囲気を感じません。
それもそのはず、元々は宋の仏画をモデルにしているので、
快慶という雰囲気が感じられないのも仕方ありません。
当初は立像の阿弥陀如来であったが、
江戸時代の享保年間に仏師祐慶により修復され、
現在の坐像盧遮那仏になりました。
他に俊乗房重源像が祀られていました。
こちらもリアルな彫刻で見事でした。
【石造基壇】

一階に戻ると次は基壇です。
こちらのブログの画像を拝借しました。
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad/7460/mie-sindaibutuji.htm
元は阿弥陀三尊の台座だったそうで、
よくも鎌倉時代に造ったもんだと感心した。
石を切るのは出来たとしても、二段目をよく乗せたなぁ。
どうやって石を乗せたんだろうか。
【御朱印】

書置きのみとのことです。
拝観料300円の価値は充分ありますので、
ここを訪れたなら新大仏殿は拝観しましょう。
ここは何といっても盧遮那仏でしょう。
お会い出来るのが楽しみです。

山門前に大型無料駐車場がありました。
いざ参拝開始。
所在地:三重県伊賀市富永1238番地
宗派:真言宗智山派
御本尊:盧遮那仏
創建:建仁2年(1202)
開基:源頼朝
開山:重源上人
【縁起】
源頼朝が後鳥羽法皇の勅願寺として開創、
重源を開山として創建されたと伝えられる。
重源は鎌倉時代に東大寺大仏と大仏殿の復興事業を指揮した僧として知られ、
当寺は東大寺の伊賀別所となった。
新大仏寺と称する所は重源上人が東大寺に敬意をはらって、
寺の名前に新の字を加えた。
その後、長らく衰退し戦国時代末期にはかなり酷い状態であった。
新大仏寺を訪れた松尾芭蕉はその様子を笈の小文や伊賀新大仏之記で記している。
再建されたのは江戸時代中期の寛延年間(1748-1751)のことである。
【大門】

とても立派な山門です。

扁額に東大寺伊賀別所と書かれています。
【仁王像】


【明王殿】

これはどう見ても交通安全祈祷殿ですね。

やはりお不動さんがいらっしゃいました。
【白寿観音像】

足元に爺さん婆さんがいました。
このパターンはどっかのお寺で見た記憶があるな。
【慈母観音】

子供がモロ人間でちょっと違和感がある。(^^;
【本坊】

御朱印や拝観受付はここでは無く、
明王殿前にある売店である寺務所となります。
【石塔】

【石仏】

これは善光寺式如来ですかね。
【鐘楼堂】


【十三重搭】

【鎮守社】

【大師堂】

元文3年(1738年)に護摩堂として建立されたもので、
ペリーが浦賀に来た時は国難消除の祈祷を修したそうです。
【大仏殿】

享保12年(1727)から延享5年(1748)にかけて建立されたもの。



元々の御本尊である大仏如来を祀っていたので、
大仏殿となっていますが、現在は釈迦如来が祀られていました。

地蔵菩薩と役行者が祀られていて、
なかなか立派な地蔵菩薩でした。

堂内外陣は砂でした。
こういうお堂はたまにありますね。
【岩屋不動明王】


大仏殿の裏手に回ると滝場があり、
そこには6メートルもの不動明王が祀られています。

ここからだとお顔が見えない。(泣)
滝場は水行をしないと入れないとのこと。
【石仏】

【護摩祈祷堂】

不動明王が見れなくて残念だなぁと思いながら反対側に回って見ると、
中に入れることが判明。
寺務所の方に確認してみると入っても良いとのこと。

何とも厳かな雰囲気。

ガラス越しに御対面。


江戸時代より多くの修行者の願いを受け止めてこられました。

最初見た時、ちょっとびびった。(^^;
【鎮守社】

【本堂】

これが本堂なのね。
てっきり横の大仏殿が本堂かと思ってたよ。
寛永9年(1632年)上野城主藤堂大学助髙次公が、
雨乞い祈願成就の御礼として寄進されたもの。

元俊乗房重源像をまつった由縁から上人堂と称するが、
現在は阿弥陀如来が祀られていました。
【鎮守社】


【新大仏殿】

ここだけ拝観料300円が必要です。
まずは二階に上がり盧遮那仏とご対面です。
この新大仏殿は外よりもヒンヤリとしていて寒い。
【盧遮那仏】

撮影禁止でしたので伊賀上野観光協会より拝借。
素晴らしい。
息を飲む程の見事な大仏様です。
快慶作ということでしたが、そんなに快慶の雰囲気を感じません。
それもそのはず、元々は宋の仏画をモデルにしているので、
快慶という雰囲気が感じられないのも仕方ありません。
当初は立像の阿弥陀如来であったが、
江戸時代の享保年間に仏師祐慶により修復され、
現在の坐像盧遮那仏になりました。
他に俊乗房重源像が祀られていました。
こちらもリアルな彫刻で見事でした。
【石造基壇】

一階に戻ると次は基壇です。
こちらのブログの画像を拝借しました。
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad/7460/mie-sindaibutuji.htm
元は阿弥陀三尊の台座だったそうで、
よくも鎌倉時代に造ったもんだと感心した。
石を切るのは出来たとしても、二段目をよく乗せたなぁ。
どうやって石を乗せたんだろうか。
【御朱印】

書置きのみとのことです。
拝観料300円の価値は充分ありますので、
ここを訪れたなら新大仏殿は拝観しましょう。