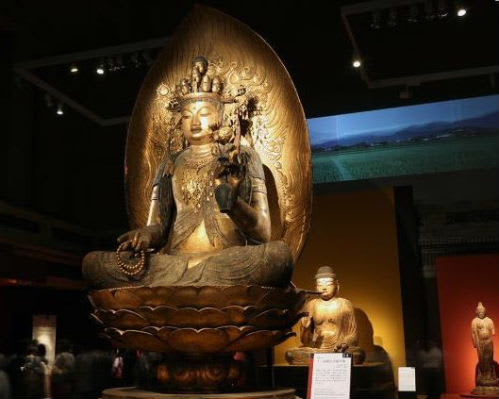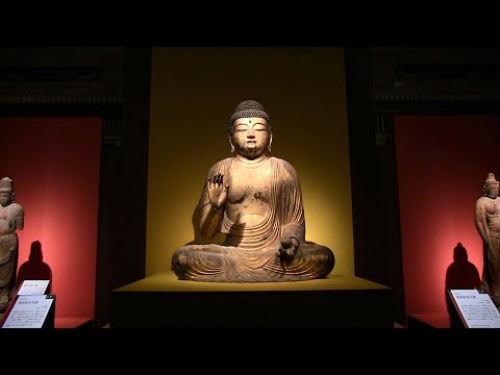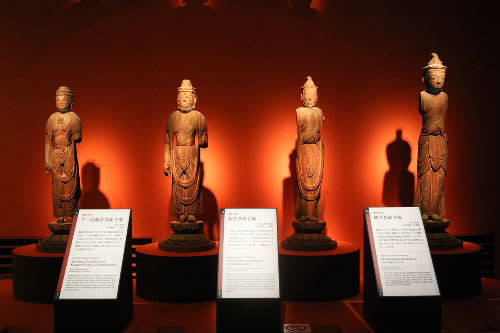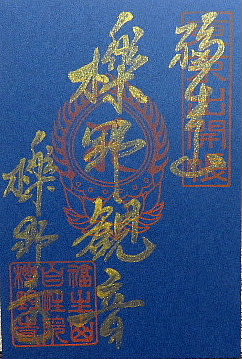今日は朝9時にアポを取って當麻寺の宗胤院を訪れました。
何でも来年のカレンダーの上部に好きな文字や絵を、
書いていただけるということを知って、
飛んで行った次第。(^^
三か月振りの参拝となります。
<2016年7月16日参拝>
http://blog.goo.ne.jp/05100625777/e/3d8fa857ed1a8b78814b90f52c0d4113
所在地:奈良県葛城市當麻1263
宗派:浄土宗
御本尊:阿弥陀如来
創建:不明
開山:宗胤上人
【山門】

御住職の奥様に無料で停めれる場所を教えてもらっていましたが、
今日は祭りがあるので遠慮しておきました。
【神輿】


【境内】

仕事でもプライベートでも遅刻しないのがゴマラー。(^^
約束の時間である9時に宗胤院へ。
御住職が出てこられ早速カレンダーに絵を描いていただく。
私は絵をお願いしましたが、
文字だと好きな漢字一文字を、
芸術的に書いていただくことが出来ます。
描きながら私の仕事の話や御住職のこと等、
いろいろ面白い話をして話が弾む。
ちょっと前に東京に行って増上寺を参拝したことを言うと、
御住職は僧侶になる為に増上寺で修行したとか。
増上寺で修行するのは知らなかったな。
その後は奈良の長谷寺でも修行したそうです。
そんなこんなで一時間半程で完成。
ササっと書いていただいて良かったのに、
凄く丁寧に書いていただきました。(^^
【カレンダー】


出来上がった作品です。
凄く綺麗で感動です。(^^
上には私が好きな「諸行無常」と書いていただきました。
御住職は四文字の漢字を書くのがデフォルトで、
いろいろな四文字熟語や仏語の見本がありました。
描いている時に新たにカレンダーをいただく方が宗胤院に来られた。
この方も交えて一緒にいろいろお話をさせていただき、
三人でとても盛り上がりました。(^^
お話をさせていただいていると、
この方は絶大な影響力がある有名ブロガーさんだと分かりましたね。
明るくとても良い方でした。(^^
いつもブログを拝見して知らない情報を配信していただき、
かなり助かっていますよ。
この方のカレンダーに絵を描いている時も同席させてもらい、
御住職の絵を見させていただきました。
墨画がとても素晴らしかった。(^^
【名刺入れ】

ひょんなことから檜の話になったら、
御住職から檜の名刺入れをプレゼントしていただけました。
嬉しい。
本当に有難うございます。(^^
【イラスト】

こちらは御朱印帳に画いていただいたものです。
花はコスモスです。
これもとても良いですよね。(^^
書いていただいた文字は欣求浄土にしてもらいました。
御住職が修行された増上寺といえば徳川家康、
徳川家康といえば欣求浄土なんで。(^^
ピンクのコスモスの花言葉は「純潔」。
穢れた世界から純潔である極楽浄土を求める欣求浄土。
コスモスに欣求浄土は我ながらナイスなチョイスだと思います。(^^
【御朱印】

ちなみに通常の御朱印は300円。
イラストは片面だと500円。
両面の場合は通常の御朱印と一緒で千円になります。
これは別の某有名ブロガーさんが御住職と相談して、
決められたそうです。
それでも値段は安いよね。(^^
私達がもっと高くても良いですよと言っても、
御住職はそんな高い料金は取れないと固辞されていました。
2千円や5千円とかぼったくる京都のお絵描き寺の御住職は、
宗胤院の御住職を見習って欲しいよ。(苦笑)
お寺の経営がしんどいのは同じなんですけどね~。
【襖絵】


カレンダー、イラスト、御朱印全て終了し、
御住職にお願いして御本尊様をお参りさせていただきました。
本堂にあるのがこの襖絵です。
これが超絶素晴らしい。


この襖絵欲しいわ~。
何百万もすると思うので買えませんけど。(^^;


この筆使いのタッチがたまらない。
本当に好きな墨画です。
今度、小さいサイズながら御住職にお願いして、
墨画を描いていただくことになった。
出来上がりが楽しみです。
結局、三時間も居座ってしまいました。(^^
お相手していただいた御住職には厚く御礼申し上げます。