5/13(日)九州国際3DM3日目。昨日までの2日間はいい天気でのウォーキングでしたが、今日は朝から曇り空。いつ雨が降ってもおかしくないくらいです。
一応、ポンチョを着て傘をさしてのウォーキングです。今日は、本当は、20kmを歩く予定でしたが、家内が昼から松橋(まつばせ)の友達に会う約束をしていますので
10kmコースに変更。7:30 30kmコースと一緒にスタート。出発の「激」は、ロシア女性の方。







3,7km地点が30k、20k、10kの分岐点。


これから本町アーケード街を歩きます。朝が早いためか、まだ商店は開いていません。
八代亜紀さんは、1日目14時から会場でミニコンサートを行われましたが、昨日は、八代でコンサートをされました。



塩屋八幡宮は、八代妙見祭の原型をつくり上げたといわれる八代城主細川三斎公が、大分の宇佐八幡宮の御分霊を迎え祀られたお宮です。
明暦元年(1655年)旧暦10月25日に、時の八代城主松井興長(まついおきなが)公時代に現在地に社殿が築かれて以来、親しみ祀られてきた社です。
その御鎮座の記念日である11月25日の例祭は、今も「しおやのまつり」の愛称で、市民に愛され受け継がれています。
妙見祭では神幸行列の御旅所(おたびしょ)となっており、11月22日に神様が「お下り(おくだり)」され、翌23日の早朝に塩屋八幡宮から「お上り(おのぼり)」行列が妙見宮に向け出発します。



歩いていると右側にモダンな建物が見えてきます。これは、八代市立博物館です。周りには、皐月が咲き出していました。


松浜軒は、元禄元年(1688)、八代城主松井直之公が母崇芳院尼のために建てたお茶屋です。当時この辺りには松が茂り、八代海を見渡せる浜辺であったことから松浜軒と名づけられました。
別名「浜の茶屋」とも呼ばれていました。(国指定名勝) 四季折々の花々が咲き、特に6月上旬には約5,000本の肥後花ショウブが大輪の花を咲かせ、多くの人々の目を楽しませます。
また松井家に伝わる家宝を展示する松井文庫の資料館があり、宮本武蔵ゆかりの「戦気」の軸や手彫りの木刀も展示されています。(八代観光HPより)


コースは、八代城址に入ります。
元和5年(1619)の大地震でそれまでの麦島城が崩壊したため、加藤正方が麦島城北方に新たに築いたのが八代城で、同8年(1622)に竣工しました。
石垣に石灰岩を使用し別名白鷺城ともよばれます。加藤家改易の後、寛永9年(1632)細川三斎(忠興)が入城、正保3年(1646)には松井興長が入城し以後松井氏九代の居城となりました。
一国一城令の例外として熊本城以外に認められた城で、八代の地が幕府から重要視されていたことがわかります。(八代観光HPより)



八代城址には、「八代宮」があります。明治維新以降、南朝の功労者を祀る神社の創建運動が各地で起こり、懐良親王の墓所のある八代の住民からも、懐良親王と良成親王を祀る神社を創建し、
鎌倉宮・井伊谷宮と並ぶ官幣中社にしてほしいという請願が何度かなされました。住民である徳富忠七や八代宮創立発起担当人の村上忠三らは、墓所から遠くない松江城(八代城)の址に神社を建て
ことを求めました。これを請けて1880年(明治13年)に太政官が熊本県に創立を命じ、懐良親王を祭神とし、良成親王を配祀する神社が八代宮の名で願い通りに造られることとなりました。





八代宮の参道から本町アーケード街に入ります。このあたりは、八代の歓楽街でしょうか、クラブやキャバレー、スナックなどが建ち並んでいます。
キャバレー「白馬」は、歌手八代亜紀さんがアマ時代、ここで歌っていました。



8,3km地点の八代ハーモニーホールがチェックポイントですが、私たちが来るのが早かったせいか、まだ準備がされていませんでした。



約30分ぐらい待ち、チェック印をもらい再びウォーキング開始します。
萩原橋では、正規の時間にスタートした10kmコースの人とすれ違いました。
10:10 ゴールしました。


3日間の参加者は下記です。いっそでウォークは、八代の幼稚園、保育園、小中学校、高校の生徒さんが参加されました。
余談になりますが、「八代」という地名の由来が気になりましたので調べました。肥後国誌には、八代の地名の由来は、社(やしろ)で天照皇大神の山陵が、上古にこの地にあったので
「やしろ」と言われるようになったと記されています。


今日は、そんなにひどい雨には、遭いませんでしたが、ポンチョを着ていたため蒸し暑く、汗を流すため、八代市東陽町の温泉施設に行ってきました。
東陽町は、石工の町として知られています。




来週は、福井県若狭町の「三方五湖ツーデーマーチ」に参加します。







































































































































 信濃の国は、十州に 境連ぬる国にして・・・・・
信濃の国は、十州に 境連ぬる国にして・・・・・


















































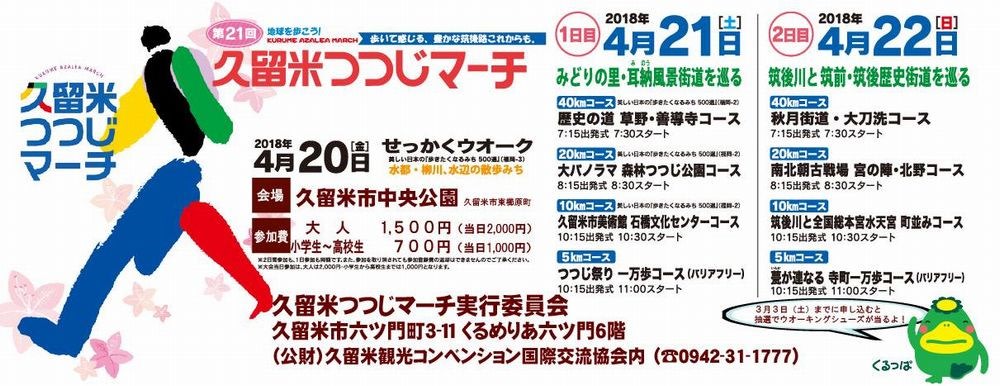

























































































































































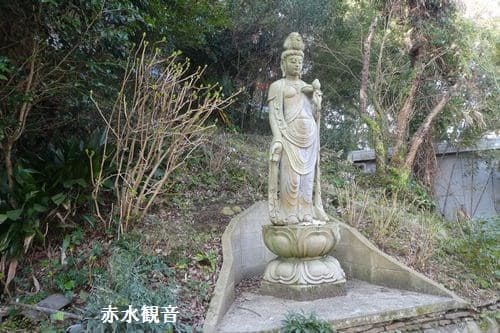


























































 ]
]







