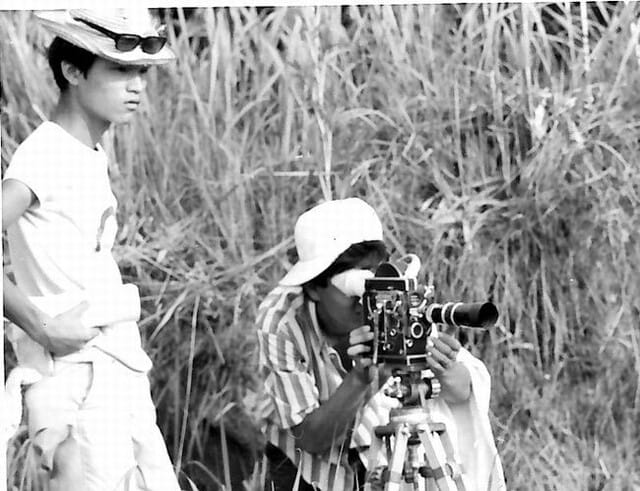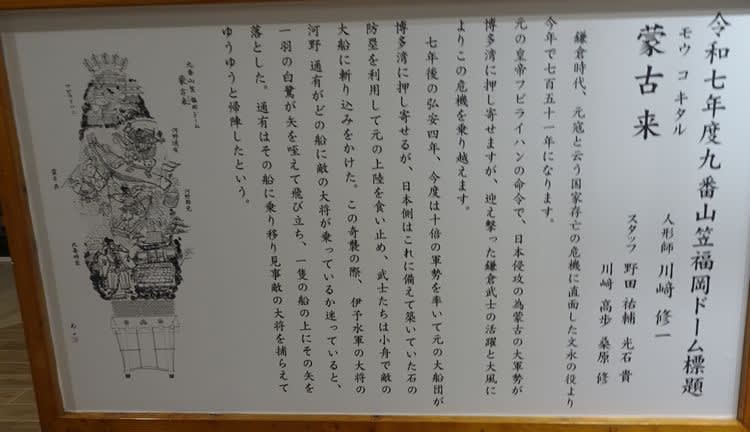ふくおかウォーキング協会は、7月中旬から猛暑のため、夏休みに入り8月23日(土)の例会から再開しました。
この夏休みは、昨年から行っていますが、今年も猛暑猛暑の連続で今考えると夏休みを設けてよかったと感じています。
8月も20日を過ぎましたが、まだ暑く、今日(8/23)の例会は「日陰を歩いて涼感!地下鉄の駅出口風景」として木陰を歩き、地下街を歩くというもの。
距離も10kmから7kmに短縮し、また、緊急時は、最寄りの地下鉄の駅で解散するようにしています。
集合場所は、JR吉塚駅、参加者は、53名。
今日のマップ

9:30吉塚駅をスタート


先ず福岡県庁に向かいます。
ここの木陰を歩きます。少し風もあり涼しいです。

この先では、当協会副会長が、西鉄市内電車貫通線の電車が走っていたと説明されていました。西鉄東車庫もありましたね・・・・
このあたりは、「千代の松原」といって昔は松林でした。昭和27年ごろヒット(ヒットと言っても博多だけかな?)した「博多ワルツ」の歌詞にも登場します。 Bing 動画
Bing 動画  (博多ワルツ)
(博多ワルツ)
この歌は、私が駆け出しの営業マンのころその頃はカラオケもなく、よく宴会などで歌っていました。(大昔の話です)
この千代の松原に「松原水」という井戸水があります。明治・大正時代の博多の人達の暮らしを支えていた井戸です。
説明文を見ると、
明治初期、まだ井戸水を利用していたころ、博多部の井戸は水質に恵まれず、そのため飲料水は当時の那珂郡千代村一帯(現在の博多区千代付近)に続く松林(千代松原)の砂地から汲む
井戸水を運んでまかなわれていた。これも次第に建て込む人家の家庭汚水で利用できなくなってきた。
そこで明治29(1896)年 福岡市は、飲料水確保のため千代村堅粕(現在の博多区東公園)の東公園内の国有地約1アールを年間1円8銭で借り受け、工費50円で市設の井戸を掘った。
これが「松原水」の起こりである。
明治34(1901)年には、福岡市による「市設井戸取締規程」が定められている。井戸には看守を置く事、汲む者は給水許可証を携帯すること、料金は1石(180リットル)に10銭宛などと細かく規定して本格的に管理された。
このようにして、業者も水桶12個積んだ大八車をガラガラ引いて、戸別に配達したため、上水道通水(大正12年)まで、松原水売りは博多の風物詩であった。
なお、明治33(1900)年 皇太子嘉仁親王(のちの大正天皇)が来福の際、飲料水として使われ、記念の石碑が傍に建っている。


東公園の所には、福岡武道館が建設中でした。
福岡武道館は、現在大濠公園の所にありますが、武道館の所に新県立美術館が建設されることになり、東公園に移転することになりました。2025年11月完成予定です。

新武道館の所に「阿部源蔵元市長」の銅像が建っています。阿部元市長は、昭和35年(1960)から昭和47年(1972)まで市長を務められ、昭和47年には、福岡市を
政令都市に昇格されました。当時の市の人口は100万人でしたが、50年以上たった今では、市の人口も約169万人になりました。

千代町から大博通りに向かいます。


博多座の所から地下に潜ります。


アンパンマンミュージアムの所から再び地上へ。


那珂川の西大橋を渡り天神へ。


天神中央公園では、ビールのイベントが行われています。ウォーキング後のビールはおいしいでしょうね!!!


アクロス福岡で休憩


休憩後、アクロス地下から天神地下街へ


冷房が効いて地上とは別世界みたいです。


天神南駅の先から地上へ。


地上に出るとまた直射日光が迎えてくれます。地上と地下ではどのくらいの気温差があるのでしょうか?
春吉橋を通り櫛田神社へ


櫛田神社は、インバウンドの方が多くそれぞれ貸し切りバスで来られています。

櫛田神社から地下鉄祇園駅へ
意外と知られていませんが、地下鉄祇園駅から博多駅にはこの地下道を通っていくことができます。
地下鉄が中洲川端駅から博多駅に延伸工事した際にここに仮駅が設けられました。



12:00 博多駅地下街にゴールしました。

暑い中のウォーキングでしたが、木陰を通ったり地下街を通ったりで少しでも暑さが凌げたコースでした。
このコースを作成したスタッフに拍手です。