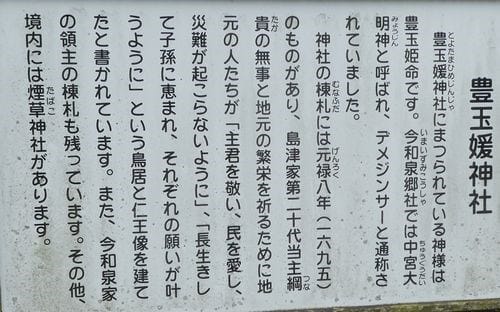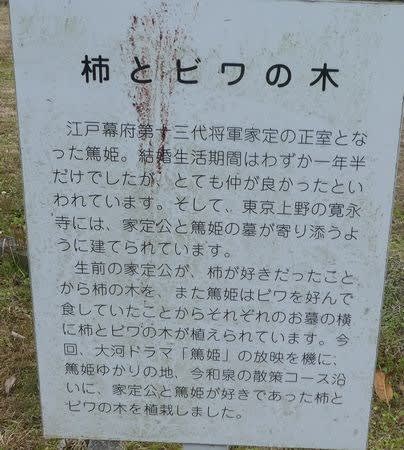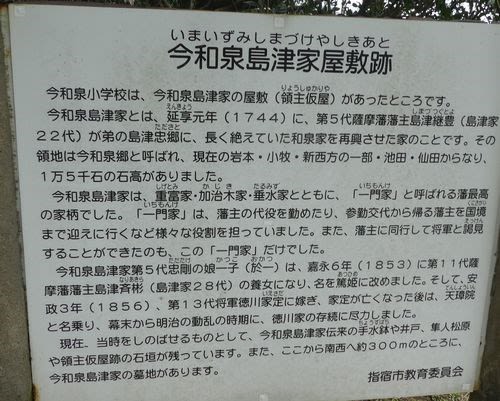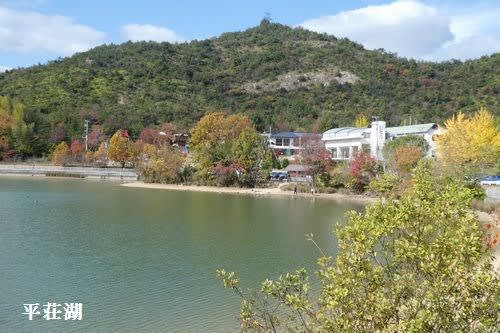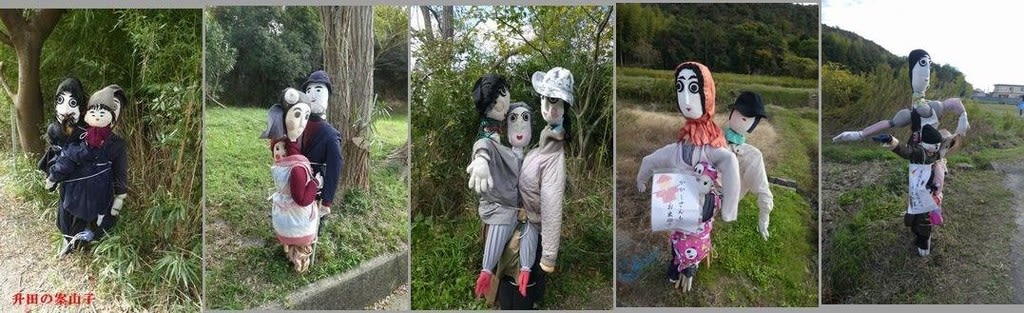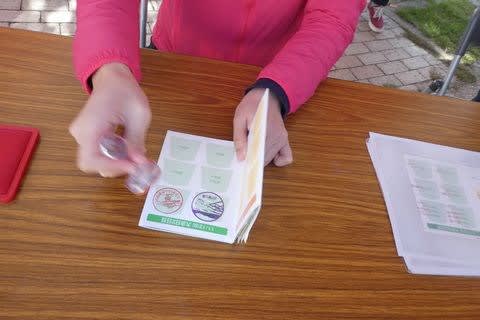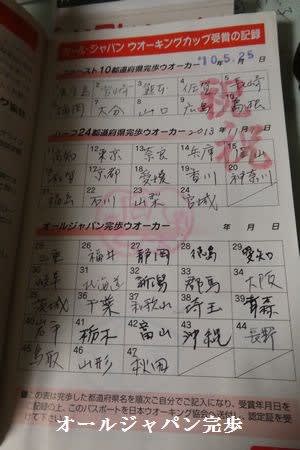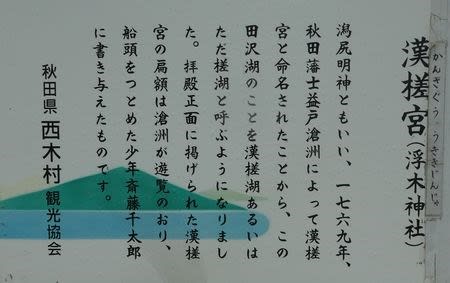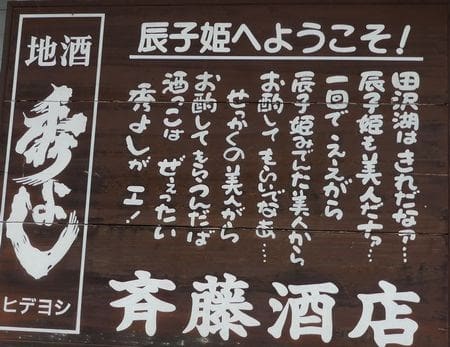2/25(日)宮崎ツーデーマーチ「こばやし霧島連山絶景ウォーク2日目」。
前日は、絶好のウォーキング日和でしたが、今日は朝からシトシトと小雨が降っています。午前中でももってくれればいいのですが・・・・・・
昨日は、ゴールした後、道の駅ゆーぱるのじりを覗きましたら、野菜が安い!福岡の産直店より2割~3割ほど安いです。

さて、本題に戻ります。今日は30kmコースに行きたかったのですが、雨の為、20kmに変更しました。勿論いつものフライングスタートです。
8:00 30kmと一緒にスタートします。


市役所前を通り、駅伝の名門「小林高校」前を通ります。
小林市役所は、現在新築中で、外観は、木を使ったデザインです。今年6月に完成予定だそうです。
小林高校の駅伝部は、全国大会出場52回(うち、全国優勝7回)を誇る強豪校です。



小林高校から、最初の上り坂、緑ヶ丘公園に向かいます。緑ヶ丘公園の梅林は、もう7分~8分ぐらい花が咲いています。紅と白のコントラストがいいですね。


今年の冬季オリンピックでは、カーリング女子LS北見の「もぐもぐタイム」が有名になりましたが、このコース最初の「もぐもぐタイム」が緑ヶ丘公園です。
公園内には、SLも展示されています。この公園、何年か前の大会で通りました。


運動公園入口が20k、30kの分岐点。20kは、運動公園を通り出の山に向かいます。
このあたりから雨が降ってきました。傘を差し、合羽を着てのウォーキングです。


このあたりアップダウンが続きます。昨日痛めた膝が泣き始めました。一緒に歩いていた歩友さんと離れ膝をいたわりながらゆっくりゆっくり歩きます。
地鶏の里が2回目のもぐもぐタイム。バナナ、ゆで卵が振る舞われました。ゆで卵は、しょうゆをかけたら味が変わると教えられ、実行すると一段とおいしくなります。



ホタル館に到着。ここでは、豚汁、アユのから揚げです。
ここでは、30kmの速い方から抜かれていきました。



出の山淡水魚水族館が1回目のチェックポイント。
小林市は、市内に約75ヶ所もの湧水地があり、出の山公園の湧水が名水百選にも選ばれるなど「名水のまち」と呼ばれています。その豊富な名水を活用し、
昭和58年より「宮崎県水産試験場小林分場」がチョウザメ研究に取り組んできました。同試験場は、平成16年に日本で初めてシロチョウザメの完全養殖に成功するなど国内において
トップクラスのチョウザメ技術を有しています。小林市の水は、チョウザメの養殖に適した水温であり、稚魚期には、地下水を利用することで、
悪性の菌を池に入れることなく安全に育てる最高の条件のもと成育することができます。現在、小林市内では5業者で養殖を行っています。
すべての養魚場で飼料の統一、霧島裂罅水で養殖されており品質統一に努めています。(小林市HPより)
チョウザメというと世界三大珍味「キャビア」が有名ですが、チョウザメの魚肉を使ったお寿司などもおいしいそうです。


まきば演芸場です。天気がいい日は、ここからの霧島連山のビューポイントですが、残念ながら雨の為煙っています。


昨年歩いた時は、ここの河津桜は、ほぼ満開でしたが、今年は開花が遅れているのかまだ蕾でした。


消防訓練広場では、ミニトマト「あいこ」の御振舞。


2回目のチェックポイントは、「霧島岑(みね)神社」です。
明治6年(1873年)霧島六社権現の一つであった夷守神社を合祀した後、夷守神社跡地に遷座し現在に至る。









ゴールでは、白玉ぜんざいがサービスです。雨で濡れたので温まります。
今年の参加者は、2日間(2日目は雨でしたが)で2000人を超えました。昨年は1900人でしたので若干増えましたね。これもスタッフさんたちの地道な努力の賜物でしょう。
来年も参加者が増えるといいですね。勿論私たちも来年も参加する予定です。
ただ、会場のステージとスタート地点が前と後ですので、参加者の方は後方でスタートを急ぐためか、スタートの方ばかり集まり、ステージ側には、あまり集まりません。
折角の来賓の御挨拶や、太鼓の演舞は、見ていない状態です。会場の配置をもう少し考慮されればと思っています。


会場をあとに、神の郷温泉で汗を流してきました。歩いた後の温泉はいいですね。