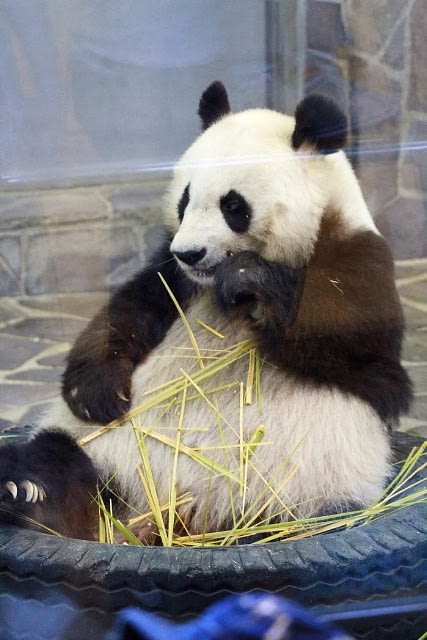今回は『ナマケモノ & ボブキャット』の紹介です。

夜行性で、1日の約15-20時間眠っています。
1日の半分以上眠り、ゆっくりした動きから「怠け者」と名づけられたそうです。

ナマケモノは、大きく別けてフタユビナマケモノとミユビナマケモノが知られていますが、いずれも中央アメリカから南アメリカにかけての湿度の高い熱帯雨林に分布しています。フタユビナマケモノには指(実際は指骨)が2本、ミユビナマケモノには指が3本あります。
コロンビアとベネズエラの北部のほか、スリナムやブラジル北部、ペルーの北部などの密林地帯に生息し、完全な樹上生活をしています。

夜になると低カロリーの木の葉や植物の芽、木の実、果実などを食べます。
1日に数枚の葉を食べるだけで生きていけるので、水分補給はほとんど果汁で補っています。
余計なエネルギーをあまり使わないように、必要最低限の食べ物、動きで効率よく生活をしています。

頭部は短くて丸く、耳は外からは見えにくく、前足は後足よりも長く樹上生活に適しています。

体は黄灰色や灰褐色の長い毛で覆われていて、ナマケモノは他の樹上性の動物と違って、体を木の枝にぶら下げて生活しています。
そのため体毛はほかの哺乳類とは違い、全く逆に生えているほか、野生の成獣ではしばしば苔も生えているそうです。

ナマケモノは他の哺乳類と違って、外気温によって体温が左右され、24~35度の間で体温が変化します。
この為、気温が一定する熱帯の一部地域でしか生活できず、樹上でも体温調整の為に天蓋や日陰などに移動したりします。

ボブキャットは同じネコ科に属するオオヤマネコとは同属です。
北アメリカのカナダ南部からメキシコ南部辺りにかけて広く分布しています。

茶色か赤茶色の毛皮で覆われていて、腹部は白く、しっぽは短くて先端が黒く、頬には耳から続く長いふさ毛があり、耳の裏はトラなどのように黒くて白い斑点が見られる。
ワイルドキャットとも呼ばれ、体はイエネコの2倍ほどです。
足が長く、手のひらは大きく、耳にはふさふさの毛が生えています。

獰猛な捕食動物で、自分よりはるかに大きな獲物を仕留めることもできます。
普通はウサギや鳥、ネズミ、リスなどの小動物をエサとしています。

ボブキャットは単独行動をする動物ですが、さまざまな環境に適応していて、人の住む近くにも姿を現します。
北アメリカ全土での生息数はかなり多いと考えられ、アメリカだけでもおよそ100万頭いると推定されます。
次回は『保津川下り』の紹介です。

夜行性で、1日の約15-20時間眠っています。
1日の半分以上眠り、ゆっくりした動きから「怠け者」と名づけられたそうです。

ナマケモノは、大きく別けてフタユビナマケモノとミユビナマケモノが知られていますが、いずれも中央アメリカから南アメリカにかけての湿度の高い熱帯雨林に分布しています。フタユビナマケモノには指(実際は指骨)が2本、ミユビナマケモノには指が3本あります。
コロンビアとベネズエラの北部のほか、スリナムやブラジル北部、ペルーの北部などの密林地帯に生息し、完全な樹上生活をしています。

夜になると低カロリーの木の葉や植物の芽、木の実、果実などを食べます。
1日に数枚の葉を食べるだけで生きていけるので、水分補給はほとんど果汁で補っています。
余計なエネルギーをあまり使わないように、必要最低限の食べ物、動きで効率よく生活をしています。

頭部は短くて丸く、耳は外からは見えにくく、前足は後足よりも長く樹上生活に適しています。

体は黄灰色や灰褐色の長い毛で覆われていて、ナマケモノは他の樹上性の動物と違って、体を木の枝にぶら下げて生活しています。
そのため体毛はほかの哺乳類とは違い、全く逆に生えているほか、野生の成獣ではしばしば苔も生えているそうです。

ナマケモノは他の哺乳類と違って、外気温によって体温が左右され、24~35度の間で体温が変化します。
この為、気温が一定する熱帯の一部地域でしか生活できず、樹上でも体温調整の為に天蓋や日陰などに移動したりします。

ボブキャットは同じネコ科に属するオオヤマネコとは同属です。
北アメリカのカナダ南部からメキシコ南部辺りにかけて広く分布しています。

茶色か赤茶色の毛皮で覆われていて、腹部は白く、しっぽは短くて先端が黒く、頬には耳から続く長いふさ毛があり、耳の裏はトラなどのように黒くて白い斑点が見られる。
ワイルドキャットとも呼ばれ、体はイエネコの2倍ほどです。
足が長く、手のひらは大きく、耳にはふさふさの毛が生えています。

獰猛な捕食動物で、自分よりはるかに大きな獲物を仕留めることもできます。
普通はウサギや鳥、ネズミ、リスなどの小動物をエサとしています。

ボブキャットは単独行動をする動物ですが、さまざまな環境に適応していて、人の住む近くにも姿を現します。
北アメリカ全土での生息数はかなり多いと考えられ、アメリカだけでもおよそ100万頭いると推定されます。
次回は『保津川下り』の紹介です。