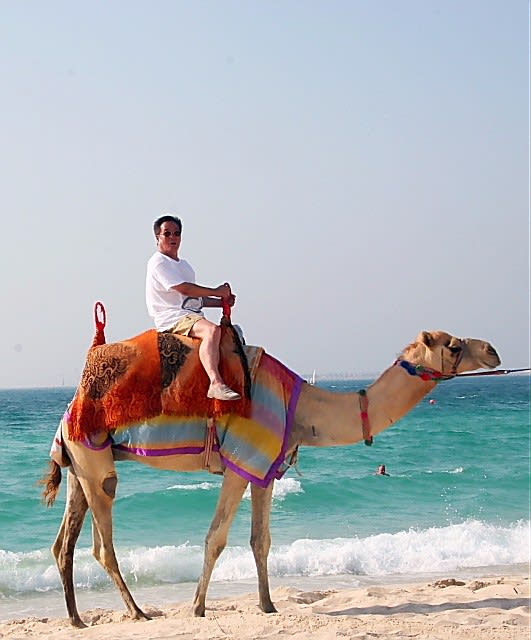今回は『ピグミーゴート』の紹介です。

ピグミーゴートは、西アフリカのカメルーンが原産といわれる超小型のヤギです。

アフリカの家畜ヤギとして育てられています。

家畜として利用されるほか、ミニヤギなどとよばれ、ペットとして飼われる場合もあるそうです。

性格はおとなしい動物のようで、ズーラシアでは子供たちとの触れ合い所を設けているそうです。

股が短く、体が小さいことで愛くるしい感じがペットとして人気があるそうです。

体高40-50cm、体長60-70cm、体重20-35Kgぐらいdesu.

乾燥に強く、粗食によく耐えるので、西アジアの乾燥地帯では重要な家畜です。

1950年代にアメリカに持ち込まれ、そのおとなしい性格からペットとして大人気になったそうです。

体色も黒・白・茶とバリエーション豊富なのも人気なのでしょう。

毛の長短はオスメスの違いかと思ったのですが、未確認なので、毛を刈られているかいないかかもしれません。

次回は猛暑の中でBBQの報告です。

ピグミーゴートは、西アフリカのカメルーンが原産といわれる超小型のヤギです。

アフリカの家畜ヤギとして育てられています。

家畜として利用されるほか、ミニヤギなどとよばれ、ペットとして飼われる場合もあるそうです。

性格はおとなしい動物のようで、ズーラシアでは子供たちとの触れ合い所を設けているそうです。

股が短く、体が小さいことで愛くるしい感じがペットとして人気があるそうです。

体高40-50cm、体長60-70cm、体重20-35Kgぐらいdesu.

乾燥に強く、粗食によく耐えるので、西アジアの乾燥地帯では重要な家畜です。

1950年代にアメリカに持ち込まれ、そのおとなしい性格からペットとして大人気になったそうです。

体色も黒・白・茶とバリエーション豊富なのも人気なのでしょう。

毛の長短はオスメスの違いかと思ったのですが、未確認なので、毛を刈られているかいないかかもしれません。

次回は猛暑の中でBBQの報告です。