
先週のこと。同人「季節風」の3つのお祝いがあった
1つ いとうみくさんの「糸子の体重計」が初出版したこと。
2つ 高橋秀雄さんの「地をはう風のように」が青少年読書感想文全国コンクール課題図書になったこと。
3つ 堀米薫さんの「チョコレートと青い空」が児童文芸新人賞を受賞、さらに高橋さんと同じ課題図書に選ばれたこと。
1,2についてはこのブログで感想を書いたので省くが、堀米さんとは初顔合わせ。この日著作を購入できたので後日読んで感想を述べてみたいと思う。
いとうさんにいたっては、初出版記念なのに、もう2作目「おねえちゃんって、もうたいへん!」が会場で並んでいた。これも購入。二次会後、サインをもらい損ねたと思って開いたら「いとうみく」と直筆があった。
ラッキー

左から高橋秀雄さん、堀米薫さん、いとうみくさん。
ひと仕事やり終え、達成したあとの晴々としたお顔がまぶしい。
晴れやかな先達たちのお姿の後ろに見え隠れするのは苦しんだであろう研鑽の日々。
物書きという同じ土俵に立ち、こりゃ怠けられねえな、とおずおずと衿を正すのである。


越水さんの挨拶から延々とつづく祝辞に、季節風を取り囲む絆の深さを思う。
高橋さん、長年の苦心が報われましたな。おめでとうございます。
堀米さんには初めてご挨拶させていただいた。処女作が本になる類稀な才能の持ち主。震災を乗り越えた強さで力作を書き続けてくださいまし。おめでとうございます。

そして、いとうさん。季節風に入会した時から先を走っていた先輩。同人のなかの名うての実力者も、これだけ年数を経て、熟成させてのデビューなんだ。まっこと勉強になりやす。

いとうさん。ホント、書いてきたものが本になってよかったね。
夢が努力で目標になり、ついに作家として踏み出した日に立ち会えた。
発起人、実行委員の皆様、どうもお疲れさんでした。
同人の皆さんと絵描きさん、編集者たくさんの業界の方々にエネルギーを注入された。
こりゃ、負けてられねえ。
同人仲地さんにアドバイスされたことを実践してみようと思う。
やるしかない、やるしか
「入梅や 祝う笑顔の 目出度咲き」
海光

2012年3月31日付の拙ブログにて紹介した、熊澤南水さんから小包が届いた。
樋口一葉の朗読音源がつまったCDを頂いたお礼に、いくつか商売道具の本を送った。そのお礼にしては嵩があると思いきや、懐かしいアナログテープが入っていた。
嬉しいことにあっしの拙い創作を吹き込んでくれたのだ。
ところが、肝心のハードがない。CDラジカセも使わないと捨ててしまって久しい。
しばらく友人、先輩に聞いてみたがやはり時代の変遷激しく、なかなかに聴けない。
そこで、アナログテープからデジタル音源に変換する機器を購入したのだ。
メタルとか懐かしいですな。
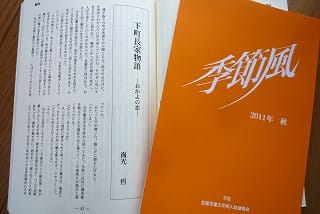
◇拙作『下町長屋物語 -おかよの恋-』 by 熊澤南水朗読
http://www.myspace.com/1005079018
音質は雑音が交じっているが、それが時代を感じさせてまたよいように思う。
拙い文章も、プロの朗読にかかると魔法のように変じるから不思議だ。
ひとりベッドに横になり、目を閉じる。
文化文政の江戸新吉原の清掻の音、色街の嬌声が部屋を満たしていく。
空気が湿り気を帯び、心が広がり豊かになった。
南水さんとのありがたい出会い、粋な計らい。津軽女の江戸住まいの極み。
人は所詮孤独なもの。でも、一人で生きているのではないのだ。
ありがてえな。
ご愛読の皆さんもよろしければ聞いてやっておくんなさいまし。
『江戸住まい 長き苦労も 芸の肥え』
海光

熊澤南水作品CD『十三夜と大つごもり』

3月の朗読会

「吉原御免状」
著:隆慶一郎
平成元年9月25日 新潮文庫初刊
「清掻や うつつか夢か 恋の町」
海光
いや~まいった。
溜息しか出てこない。
隆慶一郎が61歳を過ぎてから小説を書いたこと。名うての時代小説家であったことを知っていくつかの作品は読んでいた。
それまで読んだどの書き様にも接触しない文章に新鮮を覚えたのはたしかだ。
順番が逆になったが、その原点となったこの「吉原御免状」を読んだら絶句してしまった。
スゴイ!、この一言。
日本堤という小見出しがある。
「松永誠一郎が、浅草日本堤の上に立ったのは………」と始まる。
あっしは吉原で生まれ育ったのだから当たりまえだが、日本堤は目と鼻の先である。
余談だが、東京大空襲の時はここ馬道の土手通りだけ焼け残ったのだ。その古い木造建ては、今でも老舗の桜鍋や天麩羅の店として軒を連ねている。
老舗の味を求めて今でも行列が絶えない。浅草の灯が復活して久しいが、人力車で巡る観光客も通る。東京スカイツリー開業によってさらに拍車がかかるだろう。
明暦3年(1657年)のこの地を舞台に話はすすむ。
隆氏が微細に入り調べ上げたであろう史実。それを元に極めて大胆に着想した時代創作を練り上げ、読み手を知らず江戸初期の混沌に誘ってくれる。
宮本武蔵、神君御免状、柳生、家康の影武者、くぐつ一族、そして色里吉原。いくつものキーワードが大波小波のように押し寄せては返す。
清掻(すががき)の音色が仲の町の見世という見世に輪唱し、主人公誠一郎の涙を誘うのだ。
氏は東京帝国大学、学徒出陣、そして東京大学に再入学し、仏文を学んだ秀才。小林茂雄を慕って東京創元社で編集を経て、立教、中央大学でフランス語をおしえた。
その後は池田一朗という本名で、映画、テレビのシナリオライターとして長く活躍。「にあんちゃん」でシナリオ作家協会賞を受賞する。
企業勤めでいうところの定年の歳を過ぎてからの作家転向。直木賞候補にあがった作品。
恐ろしいほどの才能。
もちろん毛色は違うが、江戸を目指すものとして全身を貫いた痺れが止まらない。
本を読んでそう感じたのは、人生で三度目だ。
ご一読をオススメする

「糸子の体重計」
著:いとうみく 画:佐藤真紀子
2012年4月 童心社刊
『夢中になった。』
あさのあつこ氏の腰帯文句が目に飛び込む。
同人の中にあって、あっしが入会した折はすでに筆達者の著名人だったいとうみく氏の初出である。
「糸子の体重計」という意味深なタイトル、ユーモラスなイラストからして子どもたちには馴染みやすいのではないか。第一印象でそう感じた。
ひと段落したら読もうとテーブルに置いていた。
すると二男が話しかけてきた。
「糸子の話?」
「そうだよ」
「あの糸子?」
「…………」
なんだか噛み合わない。と思ったら、NHK朝ドラのカーネーションの主人公糸子の本だと勘違いしたようだ。
「ドラマの主人公とはちゃうよ!」
「なあ~んだ……」
こっちこそ、なんだ、だ。読まないのか。
静かになった。
本を探すと、その二男が物語の世界に入りこんでいる。
大好きな給食の話ということもあったのだろう。
あとで尋ねると、章ごとに一人称の登場人物が入れ変わるのも興味深かったようだ。
身近な題材、文章力、構成力、そして人の内面を描く力。
現役の子どもを夢中にさせる魔力を目の前で見せ付けられる。圧倒された。
やっぱりリアリズムの書き手として非凡なんだな。
あっしの拙い感想は控えたい。
季節風から期待の人がついにデビューしたのだ。
いとうみくの船出である。
きっと大海原の先には希望の大陸と眩しい光が満ち満ちている。
いとうさん、デビューおめでとう
やったね
『体重計 汗をかけども 変化なし』
海光


「燦」2 (光の刃)
著:あさのあつこ 画:丹地陽子
文春文庫 2011年 12月10日
ご存じの方も多かろう。わが季節風の代表、あさのあつこ氏の新しい時代物第二弾だ。
「燦」シリーズ1巻は、同人誌で僭越ながら書評を書かせていただいた。その折も触れたが、連作の序だけに、登場人物の一通りの紹介にページが費やされていたのは致し方あるまい。
そこで、2巻目を愉しみにしていたのだ。
藤沢周平氏の創った海坂藩のように、あさの氏も田鶴藩、神波の一族と魅力的な架空の国と種族を作り上げている。おそらく後世に残る響きとなるのであろう。
主人公は、吉倉伊月と燦の兄弟である。血統は同じくして、育った環境がまったくの異。その対比を愉しむ氏の筆運びが見物。
あっしは伊月の仕える圭寿が好きだ。気ままに生きたいという願いは二男であれば望みがあった。ところが意に沿わず、藩主の急変から世継となってしまう。その圭寿が、1巻では将軍へ拝謁するため江戸へ上るところまで書かれていた。
そこで、2巻である。
舞台はお江戸。氏は離れた土地でお暮らしなのに、江戸の雰囲気が見事に表現されていて唸る。
圭寿にとっては窮屈で退屈な江戸の中屋敷住まい。そこから抜け出すように戯作に没頭する圭寿。
まるで作家を目指していた若き日の氏そのものではないか、と心を躍せながら読んだ。
1巻同様、2巻も次作へ誘う仕掛けが縦横に張り巡らされている。
版元須賀屋の一間。伊月と主のやり取り。弥勒の月シリーズの木暮新次郎と遠野屋を連想させる。派手さはないが、選び抜いた言葉の遊びは充分に愉しめた。
物語がついに動きだしたのだ。
「燦」の世界に浸ってしまった。
これから読まれる方のため、詳細は避ける。
あとがきがないのは、なんとも残念であるが……。
一読者として、ひとを描くお手本としても、とにかくこの先が気になって仕方ない、とだけ記しておく。
「何時の世も 変わらぬ情熱 青嵐」
海光

「おはなしの森」
神戸新聞総合出版センター刊
2012年4月17日第1刷
「山笑う 蒲団のなかの 母の声」
海光
春の研究会の後、同人の森くま堂さんから1冊のご本をいただいた
その名も「おはなしの森」。愉しい童話が20も集められている。
帯にある通り、20人の作家の心がつまった、20の物語。
かたつむり、節分の鬼、クマ、恐竜、おばけ、ネズミ、カレイ、リュックサックやどろだんごまでたくさんも主人公、たくさんのモチーフ、子どもたちが活き活きとする世界が広がっている。
そして、森くま堂さんの『クマ町』である。
筆名も、タイトルもクマなのだ。よほどお好きなのにちがいない。
クマオくんのおとうさんが風邪を引いてしまう。町一番の働きものも、風邪を引いたら一人ぽつんと寝ていることが淋しいのだ。
そんなおとうさんを思うクマオくんとおかあさん。大草原の家のような、あったかい家庭がそこにあった。
それもそのはず、このおとうさんのモデルはご主人だとか。。愛に溢れているはずやね。
作者の優しさとユーモアが、あま~いハチミツに溶けてたっぷりつまってる
おいらもクマ町にいって、ハチミツ豆が食ってみたくなった。シングルモルトのスコッチに合うんじゃないかってのは、不謹慎かしら…。
神戸新聞子育て欄に連載された100話から選りすぐった20のお話。
こんな素敵なお話を紡ぐ作家さんが身近にいるなんて、兵庫の子どもたちは幸せだね。本という形になることで、もっとたくさんの子どもたちに届くといいな。
森くま堂さん、愉快でかわいいご本に、温かいご家族のお話をありがとう。
おいらはおいらでブログなど書いてないで、肝心の作品を書かねえとなあ
第58回青少年読書感想文全国コンクール課題図書

「地をはう風のように」
著:高橋秀雄 画:森英二郎
福音館書店 2011/4/25初刊
わが同人のひでじぃこと、高橋大兄の『地をはう風のように』(画・森英二郎/福音館書店)が本年度の課題図書に選ばれたとのこと
いやあ、めでたい。
氏にしか書けない筆跡は、昭和の田園暮らしを描く骨太の作品である。
四季のそって章立てされた形は読みやすく、この時代の男の子の本質をついている。
蒼天に召す後藤竜二氏に語りかけたように、間違いなく氏の最高傑作のひとつであろう。
とても、清々しい読後感を味わえる傑作だ。
「どん底にこそ本物の幸せがある」と帯に銘打ってあるように、昭和30年代の栃木県今市の地に足をつけ、どっしりと踏ん張り生きてきた氏ならではの真骨頂だ。
2011年8月5日の拙ブログに感想を載せている。ご興味ある方は
http://blog.goo.ne.jp/admin/editentry?eid=d96ac1e21eafa6e111cc06a290ad3b2f
高橋さん、おめでとうございます。
もがき、苦しくとも書き続けることの気高さと尊さをその行動で示唆しれくれる。
後ろをよちよちついていく身として、尻を叩かれている気がする。氏の後輩でいられること、その出会いに改めて感謝するしかない。
永遠の少年、ひでじぃの快進撃は、これからが本番だ
「四季巡り 永久の少年 祝い酒」
海光

「恋する新撰組」1&2巻
著:越水利江子
画:1巻 朝未 2巻 青治
「青い空 さくら一面 恋に咲く」
海光
先ずタイトルから惹かれるではないか
なんといっても、新撰組に恋だ。
数多の書き手が綴ってきた幕末の男たち。戦国物と並んで、もっとも歴史愛好家や一般読者に愛される時代であろう。
その屈強のサムライたちにおよそ似つかわしくないタイトルだけに、妙に気になる題名である。
季節風という、日本最大にして、これもまた屈強の書き手集団に入会した折、編集委員の先輩方の本を片っ端から読んだ。
それ以来である。久しぶりにページを捲る。
一人称の書き出しにハッとしている間に、すぐに三人称に移り、幕末の日常が立ち現れる。
読み進めるうちに、さきが気になってくるこの高揚感。これぞ、エンターテイメント時代小説の醍醐味である。完全に往時の壬生村や古都の町のにトリップする。
拙くも時代物を書く身に、これぞ、ザ・お手本という表現力で魅了されるまま、世界に沈殿していく。
それも極上の時代小説にして、児童文学なのだから恐れ入る。
時代の要請で殺生集団となった壬生浪士たちの刹那を、主人公の宮川空のひた向きな一途を描くことで、誤解を怖れずに云えば、暗さを陽に、厭世感を爽やかに見せてくれている。
う~~、と唸るしかない。さ、す、が、姐御。
あの時代も、この時代も生を全うするのは同じ人間だ。
尊皇攘夷も、倒幕も、脱原発も世の中を善くしたい、変えたいと願う心は同じ根底にあるのではないのか。
近藤も、土方も、龍馬も、以蔵も、海舟もみんなそれぞれの大義や正義を信じて戦ったのだ。
その一つの象徴が「誠」に染め抜かれた幟であり、その後の錦の旗なのであろう。
赤襦袢の叫びは彼だけの叫びなのだろうか、無名の民の叫びでもあるのではないか。

「恋する新撰組」3巻
作中、食いしん坊の原田が、江戸の棒手振りの物まねをするシーンがあった。
名編集のT氏に借りた、大江戸万華鏡を聴いているような描写だ。
いみじくも合評会で越水氏から直接指摘された、町の売り子の声。
深川で獲れた、浅蜊、しじみ売りにはじまり、納豆売り、豆腐売り、苗売り、鰯売り、鰹売り、金魚売り、心太売り、凧売り、風鈴売り……。
まさに、お手本である。
前回は気付かなかった。まさか自分が時代物を書くなんて思ってもみなかったのだから。
でも、ふと気付けば、どの時代にも、季節の風物詩をちょいと差し入れることで、情緒が深まることは明らかでないか。
果たしてそんな輩が物書きなんて、目指していいものか。
鴨川の本流のような一気呵成、極上のエンターテイメントには、欲と無欲に生きる不条理と摂理、その深い生のドラマに、主人公の恋が不思議と溶け込んでゆく。
いや、所詮、男も女も突き動かされるものは普遍であるはずなのだ。
そして、お馴染みの事件も時代考証をしっかりと尽くした自信溢れる筆致で書かれている。
大人が読んでも充分に足る、時代児童文学がここにある。
近藤勇、土方歳三、沖田総司、井上、藤堂、原田、山南、永倉等、隊士の息遣いを感じたい歴史好き、幕末マニアにも一読する価値大のシリーズだ。
続けて、「月下花伝」も読んでみようと思う。
沖田総司の終焉の地ともされる縁結びの、今戸神社の桜も咲いた
どうやら無間地獄は続くが、1粒2粒、酒精でない水滴が体の内部に溜りつつある

舞台朗読家 熊澤南水さん
冬の陽だまりのある週末のこと
地元浅草天麩羅で有名な大黒屋が営むブレーメンハウスにでかけた。
この日、舞台朗読家の熊澤南水さんのひとり芝居が開かれたのである。
ここで、簡単に南水さんのプロフを書いてみる。

東京新聞と朝日新聞の掲載記事
〈熊澤南水プロフィール〉
津軽出身。幼い頃から心に秘めたという「ことば」にこだわり、舞台朗読の道に進む。樋口一葉作品をはじめ、原作に忠実に心に沁みる言葉を伝えたいと、およそ30年に渡って全国各地で公演を行う。1991年国際芸術文化賞を受賞、2011年には吉永小百合さんとともに、下町人間庶民文化賞を受賞。浅草の有名洋食店「ヨシカミ」の女将という顔も持つ。2012年秋には能楽堂での公演が予定されている。

「津軽から 下町語り 春を呼ぶ」
海光
当日の演目は平岩弓枝作「ちっちゃなかみさん」。
幼いとき両親と別れた加代、治助の姉弟と豆腐屋を営む叔父新吉の物語。
江戸の下町、浅草と向島を舞台に繰り広げられる人情話。南水さんの声を頼りに耳を澄ませると、市井の民の息遣いが聴こえてくるようだ。
語りのあと、一葉はじめ明治の文豪を研究するT氏と一緒に、南水さんと話す機会をもらった。単身津軽から都会に嫁ぎ、方言や対人、様々なご苦労も、この30年の朗読芝居に活きていると話す言葉に、決してぶれることのない信念と確信がみえる。

南水ひとり語りCD
後日、一葉「十三夜」と「大つごもり」のCDを送ってくださった。深夜、目を閉じて聴くと、ラジオドラマとはまた違った独特の語りが往時へ誘う。
返礼に「季節風」108号を送ると、数日してまた郵便が届いた。
手紙と一緒にカセットテープが入っている。開けて驚くではないか。
あっしの掲載作「下町長屋物語-おかよの恋-」が吹き込まれたテープが同封されている。
いやあ、うれしい。ホントにうれしいねえ。生きているといいことがあるもんだ。
南水さん、ありがとう。
生憎、ダブルカセットデッキを処分して久しい。酔徹兄いに連絡したら、使ってないダブルカセットを気前よくくださるという。
いただいたら、ゆっくりと聴こう。
人に恵まれ、ご縁に恵まれ。。
あとは、物書きとして自立するのみですな
 公演の記事
公演の記事
それがたとえ無間地獄であっても、描き切った愉悦があるのなら。
いつまでつづくことやら……。
一生もんだよ、なんて野暮は先輩方ご勘弁くだせえまし

「男子弁当部」(オレらの青空おむすび大作戦!)
著:イノウエミホコ 画:東野さとる
2012年2月初版 ポプラ社刊
「男子弁当部」の最新刊が発売になった
オトメン小学生テラソラの活躍するこのシリーズもひとまずの最終巻。
愛読者にはお馴染みの、ユウタ、高野、北原の弁当部は最後まで元気いっぱい。
元気すぎて、兄ミライの突然の誘いに、なんと米どころ新潟まで遠征してしまうのだ。
う、うらやましい…。
渋谷のカリスマギャルが田植えをして話題になったのも記憶に新しいが、子供たちにこういう原体験をさせることも大切な教育なのだと思う。
普段、口に入る食料がどういう苦労と喜びを経て、届けられているのかを知れば、食事を残すようなことも減るんじゃないかな。
食材を採る、狩る、植える、それを経験すれば、3食を口にするありがたみが判るはず。
そして、料理をすることでその気持ちはさらに深化していくのだと思う。

「おむすびや 愛と塩まぜ 春うらら」
海光
作者は連載を続けていくうちに、弁当もシンプルイズベストに行き着いたと云う。
表紙に種明かししてしまっているのは至極残念である。
今回はどんな弁当になるのかな?、というせっかくのドキドキワクワク感が持てないからだ。
でも、児童書だとある意味仕方ない部分でもあるのかな。
裸の大将の究極に、ぐふふとほくそ笑んだあっし。
もうすぐお花見がはじまる
イノウエさんの愛がたっぷり詰まった弁当を開いたら、桜の木の下のおにぎりがグッと美味しくなること請け合い。
もっとたくさんの弁当が見たい。
テラソラがパリやローマにシェフ修行なんてのも興味あるなあ。
いつか成長したテラソラたちのその後を読んでみたいと思う今日この頃である

「恋する和パティシェール」
著:工藤純子 画:うっけ 2012年3月 ポプラ社刊
工藤純子氏の最新刊、和菓子の本が発売になった
2010年の秋、季節風の泊まり込み合宿で初めて草案を読んでから、実に2年。待ちに待った期待の新作はいい意味で期待を裏切る表紙になって再登場した。
今どきの女の子たちがカワイイって、手にとりそうなカラフルなイラストからワクワク感が溢れる。
主人公の如月杏があんこをこさえるように、練りに練った和菓子の一冊である。

浅草ROXLIBRO児童書コーナーの棚から
和心堂、おばあちゃんも健在で、なんとなくうれしい。
詳細は内容がわかってしまうので避けるが、表紙からも想像できるように「さくら餅」が登場人物たちの心と心をつなぐ強力なお菓子なのだ。
草案なでしこスイーツでは長命寺と道明寺のコラボだったが、こういう手できたかという縁結びのさくら餅の創作
さすがですな、工藤さん。
創作というのは、こんなに時間をかけて寝かせて、こねて、練って、完成度が増すものなんだな、と若輩は勉強になった。
あっと驚くラストの仕掛けは、綿密な取材に、餡子を練る粘り、卵白を手で泡立てる苦しみを超越した熱意と繊細にあるのだな。
工藤氏の料理物の描き方は、リトルシェフ姫野亜美の活躍でお馴染みの「ミラクルキッチン」で証明済み。
和菓子という新たなシリーズに、待ち望んだ子どもたちにお楽しみの一冊であろう。
すでに、次作の予告も載っている。
作者と版元のこぶしを握る覚悟と満々たる心地良い自信が未来を照らしてくれるのだ。
この作品を読んで、いつしかあさのあつこ氏の「ほたる館物語」を思い出していた。
和心堂の杏のおばあちゃんも、ほたる館の一子のおばあちゃんも、ばあちゃんっ子だったあっしには懐かしい匂いを運んでくれる。
昭和のセピアが残る時代には、大家族がそこかしこに存在した。団地に始まり、都会に住む日本人が、天を目指して暮らすようになり、核家族がセットになって増殖した。
元気なばあちゃん、じいちゃん。その経験という知恵と一緒に暮らす安心感は、もう過去のものとなりつつある。
せめて物語を読んでいる一時でも、ほっこりとしたい。
そんな思いで、本を広げ、原稿用紙の升目に向き合うのである。
「桜葉や 香りは花見の 予告かな」
海光

工藤さんの作ってくれた桜餅。
早くお店に買いにいかないと、あんこも桜の葉も堅くなっちまうぞ
 上野の森美術館前
上野の森美術館前
3月最初の日曜日
底冷えが戻った風のなか、上野公園に向かう。上野の森美術館で「小林豊展」が開催されている。この日は、小林画伯の講演も予定されていると過日の同人の薦めのまま入場した。
 小林画伯の講演
小林画伯の講演
北緯36℃線にこだわる画伯の思いが、静かな情熱で語られる。発酵食品、醸造酒と蒸留酒の作られる土地の差異、いずれ酵母や菌の生きられる世界の分布に例えての話は興味深く、酒飲みにはわかりやすかった。子供たちにはどう響いただろうか。
子供たちの質問に、落ち着いたバリトンで答える眼差しは親密そのもの。その慈愛はきっと、長い時をかけて世界と日本の辺境と核心を旅した画伯ならではだろう。

画伯が云う。北緯36℃を境に吹く風は、日本ではさらに複雑で気まぐれのようだ。
寅さんのように旅する絵描きは、太古から吹きつける街道の風を捉える術を心得ている。
まるで、風のハンターだ。
現代を描いたという絵本の原画からは、懐かしい原風景がこころをくゆらす。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
印象的だった2枚について。
1枚は「イスタリフの春」という海外の風景画。
青い陶器で有名なイスタリフの町であろうか。簡素で乾燥した集落に、春山の草木が笑う印象的な絵だ。
画伯が卒業後、中東、アジアを旅した風景という1枚に、過ぎ去りし青い日々を重ねた。
カイロからテロを避けて入国したイスラエル。死海からエルサレムに向かい、小さな白い車を運転した記憶が脳裏にフラッシュバックする。
写真をみるより、記憶が喚起されるとはどういうことだ。
これが絵のもつ力の一つなのであろうか。
もう一枚は「ジブラルタル海峡」。
海は空を映す鏡だという。黄金に近い同系色のグラデーションで描かれた海と太陽と空の絵に魅せられた。
筆をとった絵描きが見たそのままが、目にうつるようだ。
あっしは絵の素人だから、むずかしいことは何ひとつわからない。
ただ、この高度な描写まで到達するのに、気の遠くなるような努力と数えきれぬ苦悩の皺が必要なことだけはわかる、気がする。
画伯の名の通り、豊かな春の光に包まれて、上野の森を後にした
「土壁の 町を眺むる 春の山」
海光
(死海の帰路にて)
明日6日最終日は15時まで。。

◆上野の森美術館「小林豊展」◆
2月28日(火)-3月6日(火)
http://www.ueno-mori.org/exhibition/schedule.html#20120228-1g

2月4日のこと。竜泉の一葉記念館にいく。朗読サロンで語り芝居が行なわれた
題目は「にごりえ」。
云わずと知れた、酌婦お力と車夫に没落した源太の無理心中の話である。

ラジオドラマ、朗読と同じく、この芝居も耳で聴く文学の勉強である。
平田京子氏は、男はつらいよシリーズ、大河ドラマ、浅草ふくまる旅館でご活躍中のあぶらののった女優さん。
廓菊の井の酌婦、お力を演じ、物語の全篇を語られていた。

演じながら長い語りをこなすのは、大変な修練だろう。明治初期きっての文章が流れてくる。句読点のない、流麗な言葉の城壁がたちどころにサロンを埋め尽くしていくようだ。
記念館では平成22年1月に続いての第2回目。
3月には「千代田区内幸町ホール」で公演が予定されているという。
TVドラマJIN-仁-や水戸黄門、語り芝居等で活躍されている斉藤和彦氏が、お力への溺愛のため、蒲団屋から車夫に身を落とすろくでなしの源七を、ひとり息子太吉を抱える健気な女房お初を、教育TVやラジオ、CMナレーションを舞台にしている橋本あゆみさんがそれぞれ演じていた。演出された高城淳一氏は、11年8月に逝去された。この舞台を観られた幸運に感謝し、ご冥福を祈る。

映画「にごりえ」は来週記念館で上映される。幕末太陽傳しかり、このところ、旧い銀幕の世界からこころに映る往時に魂が奪われてしまう。

記念館では一葉周辺の人々にまつわる展示がされている。
まだ見ぬ奈津に会えるやもしれない
「春の雲 うつつに見ゆる 夢芝居」
海光
 松尾芭蕉像
松尾芭蕉像
芭蕉記念館のことに触れよう
あっしのランニングコースに、深川の土手沿いがある。護岸された川っぺりだが、塗装された道には芭蕉公の句の碑が並ぶ。たしか芭蕉記念館のそばに、翁が座っているはず。どこにいるのだろうと不思議だった。この日はこの答えを見るつもりで記念館を訪れた。



ここは芭蕉が庵を結んだ縁の地なのだ。大川に沿った万年橋通りにあるその建物はすぐに見つかった。木造の萱であしらえた門を潜ると、小さいが趣のある庭がある。これも小さな滝が流れ、しばし山水の気分に浸った。


「陽だまりに 春を追いつつ 今日も鍋」
海光



芭蕉公が鎮座する祠
記念館に入る。こじんまりとした中、翁の足跡を辿ることができるのだ。
よくぞまあ、あの時代の感覚でははるかに広かった日本を西から東まで歩いたもんだ。
 新大橋と万年橋(嘉永3年)
新大橋と万年橋(嘉永3年)
 芭蕉庵類焼(寛政5年)
芭蕉庵類焼(寛政5年)
 井原西鶴
井原西鶴
住吉大社の神前で、なんと23500句を詠んだという記録があるらしい。ほんまですかい、西鶴殿!?
 芭蕉病床の図(寛政5年)
芭蕉病床の図(寛政5年)
 採茶庵(文政5年)
採茶庵(文政5年)
 落柿舎(京都)
落柿舎(京都)
 芭蕉生家(三重県伊賀)
芭蕉生家(三重県伊賀)
これだけの健脚、そして各国で大名に歓待された翁は、果たして忍者だったのか。嘘か誠か、生家は伊賀にあると云われる。
 陶像(天保6年)
陶像(天保6年)
 芭蕉遺愛の石
芭蕉遺愛の石
たかが五七五、されど五七五。。
この深遠なる俳句の世界は、一度嵌まったら抜け出せない魅惑の扉である。
最後は本歌取りで、一句。

「初雪や 膝小僧に 傷こさえ」
海光
初雪に2度も転けたあっしでやんす

「源氏物語」
作:紫式部 文:越水利江子 画:Izumi
2011年11月15日初版 発行:角川書店
わが同人の大姐越水氏の意欲作である
あの古典「源氏物語」を子どもが読めるように、一度揉み砕き、さらに己の手法で掻き集め築く気の遠くなる作業なのだ。
数々の歴史物を扱った児童書を世に送り出している名手であるから、どんな形で源氏を書かれるのだろうと、興味は深かった。
子どもたちが手に取りやすく、読みやすいように紡ぐ魔法の杖のような筆力を持つ大姐。
だが相手はあの大古典。千年もの間読みつがれ、また幾多の作家がその訳に手を染めているほどの魅力ある物語。それだけに、児童書として書くのはさらに難しいと察せられる。
正直、この物語には長い間心が動かないで生きてきた。この度、越水氏が文を起こしてくれたことで、まさに、初めてこの古典に触れることができたのだ。
原作にはない、青砥こと水鬼が文字通り水先案内人になって、古典に不慣れな読者を優しく導いてくれる。素晴らしい発想力だ。
若かりし樋口一葉が転写し続けたという、この古典の調べの一端にようやく触れることができた。
日本人が千年語りつないできた物語。まさにいちばん最初に出会う「源氏物語」であった。
何度も挫折してきた大人の読者にもオススメの一冊である
「千年の 夢語らいで 息白し」
海光









