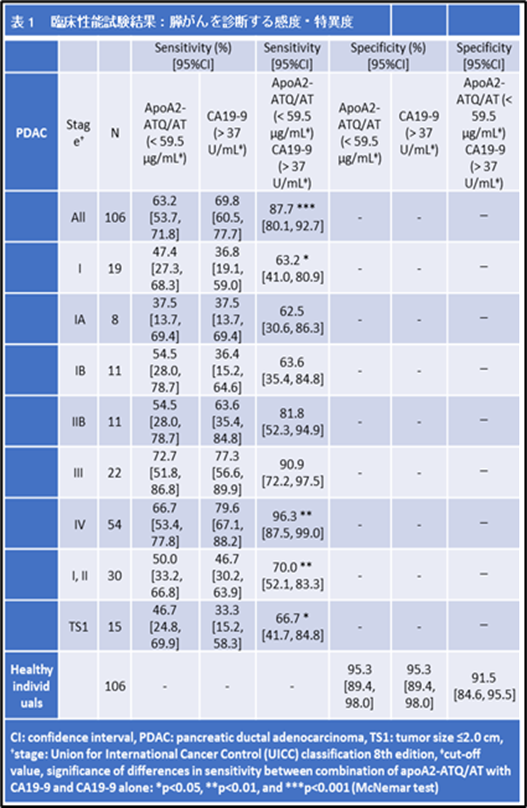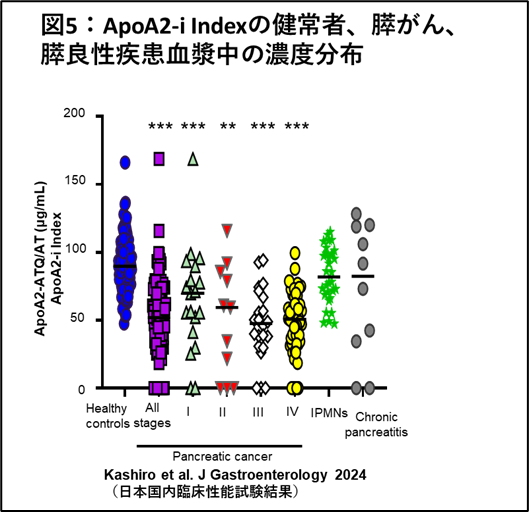先週の9月3日にクリニックからアルコール性肝硬変の60歳半ばの男性が紹介されてきた。食欲不振・倦怠感があり、体動困難ということで、入院治療の依頼だった。
2年前に腹水貯留・下肢浮腫で受診して、地域の基幹病院消化器内科に紹介していた。肝性腹水として、入院ではなく外来治療されていた。
肝臓専門医が退職したために、今年の始めに紹介元に戻されていた。7月には別の病院に紹介して入院になったが、「コロナの患者さんが入院して、免疫力の弱い患者さんは退院した方がいい」、という理由で退院になっていた。
今回も入院先を探したが、受ける病院がなくて、仕方なく(?)当院に頼んできたのだった。飲酒を継続していると困ることになる(離脱症状)と思ったが、数日は飲酒していないそうだ。
受診してみると、下肢浮腫はあるが、腹水・胸水はなかった。痩せている割に内臓脂肪が目立つ。


一人暮らしで、両親・同胞は亡くなっている。甥がいるが、北海道在住だった。知人の妻という方が、夫にいわれて連れてきました、という。
血液検査では、白血球5700・Hb13.4と問題ないが、血小板は7.6万と低下していた。肝機能は、AST 141・ALT 92・γ-GTP 167・総ビリルビン2.4とアルコール性として矛盾しない値だった。血清アンモニアは正常域。
その後問い合わせて、基幹病院からの診療情報提供書を送ってもらった。診断はアルコール性肝硬変・肝性腹水となっていた。途中で通院の中断もあったが、腹水・浮腫の悪化で再度受診したという経過が記載されていた。
利尿薬としてフロセミド20mg・スピロノラクトン25mgが処方されていたが、増量するほどでもないので、そのまま継続とした。総蛋白6.3・血清アルビミン2.9と低蛋白血症がある。
入院すると、食事摂取は良好だった。起立して歩行はできるが、ゆっくりでふらつきがある。それでもしだいに浮腫は軽減して、歩行も良くなって来た。
本人の希望は、帰っても一人なので、できるだけ長くおいてほしい、ということだった。今のところは「おとなしくしている」という雰囲気。こういう入院(絶対入院というほどではないが、諸事情で入院)は当院ならではだろう。
初期研修は港町の病院だったためか、アルコール性肝硬変・アルコール性慢性膵炎の患者さんをかなり診ていた。昔に比べると、アルコール性肝硬変は大分少なくなっているような印象がある。希少な症例になっていくのかもしれない。