2013.03.30(土)、奈良市にある大安寺に”巖封じ”のお礼参りに来たついでに、奈良県の北西部の日頃音是れル事の少ない地域にある古寺を北から順に回っている。
最初が「長弓寺」そして、「宝山寺」「霊山寺」「東明寺」と見て回り、6番目の寺にやってきた。
「松尾寺」 (まつおでら)
真言宗 補陀洛山(ほだらくさん)
大和郡山市山田町683
参拝境内自由、 駐車料無料
日本最古の”厄除け寺” また、バラの名所としても知られる。

矢田丘陵の南端近くにある松尾山の中腹に位置する山寺である。慶長11年(1606年)成立の『厄攘(やくよけ)観音来由記』、延宝4年(1676年)成立の『松尾寺縁起』等によると、当寺は天武天皇の皇子・舎人親王が養老2年(718年)に42歳の厄除けと「日本書紀」編纂の完成を祈願して建立したと伝わる。なお、松尾寺の北方の矢田丘陵に位置する東明寺(大和郡山市矢田町)も舎人親王の開基を伝える。
『続日本紀』延暦元年(782年)7月21日条には、「松尾山寺」の尊鏡という当時101歳の僧についての言及がある。また、松尾山の山頂近くに位置する鎮守社の松尾山神社境内からは奈良時代にさかのぼる古瓦や建物跡が検出されており、当寺が奈良時代の創建であることは間違いないと思われる。
「本堂」 重要文化財

日本三大黒のひとつ、重文の「木造大黒天立像」が祀られているが、時間も過ぎており、見る事は叶わなかった。
「梵鐘」


「三重塔」 明治21年の再建。一部は古材を使用しているとか。




ここを出た時にはすでに、17時を過ぎていたが、気候もよいせいか、珍しく同行の妻がまだ行くと言う。ならばと「法隆寺」の中にある「中宮寺」に来て見たが、ここらは時間厳守が厳しく、すでに門は固く閉ざされていたので、次の「吉田寺」にカーナビをセットした。













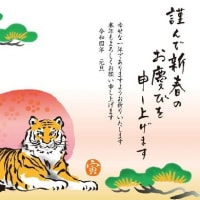






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます