2013.05.26(日)友と二人、東海道桑名宿の旧跡を尋ねる”後期野次喜多道中記”の続編である。今日紹介するのは、七里に渡で船を降りて、旧東海道を約1.7km歩いた所、伝馬町の辺りである。
前にも紹介したように、今回の東海道の旅は企画から実行まで全てを友にやってもらってるのであるが、足も体力も劣る私の能力に合わせて歩く距離を少なくし、且つ駐車料などの最少を求めての方程式を解くと言うのかパズルをやる感覚で計画された道を歩いた。
それは、あたかも映画の撮影の如く、バラバラに撮っておいたものを、道順に従って並べ替えてブログを編集するという誠に合理的な方法になっているのである。であるから、何も見るべきものが無い部分は車を使い、無料駐車場に止めて歩くと言う方法である。
「長円寺(ちょうえんじ)」
浄土真宗本願寺派
桑名市伝馬町98
古くは江場村にあったが、慶長町割の際に現在地へ移りました。市指定文化財として、桑府名勝志、久波奈名所図会、桑名の千羽鶴があります。これは当寺11代住職魯縞庵義道(ろこうあんぎどう)(1834没)の作品です。桑名の千羽鶴は1枚の紙で連続した鶴を多く折る珍しい方法です。境内の墓地には、大坂相撲力士千田川善太郎(1804没)の墓があります

「桑名の千羽鶴」 (ネット上で借用)

「天武天皇社」
桑名市東鍋屋町89番
桑名市東鍋屋町に鎮座の当社は、天武天皇を主神として御祀りしている全国で唯一の神社であります。
天武天皇、壬申の乱に皇后と共に吉野より潜奉、桑名郡家に御宿泊あり、桑名を根拠地として近江軍に対せられ、高市皇子の進言により天皇は美濃へ向かわれたが皇后はそのまま当地に御逗留あり、天皇凱旋の後再び当地に還宿され皇后と共に大和に帰られました。
天武天皇の御宿りは僅かでしたが、皇后は約二ヶ月も御逗留され、当地が二帝との関係浅からぬものがあり、後に至り天恩を追慕し讃仰の念より一社を創めて御祀りされました。



「石取祭車庫」

「一目連神社(いちもくれんじんじゃ)」
桑名市東鍋屋町89番
多度大社の別宮として鎮まりまして、昔も今も絶大な崇敬を集める一目連神社。「一目連神 出でたまふとき多度山鳴動し御光を放ちて頭上を飛び越え 困りし人々を助けたまう・・・」一目連神社の神力によって災難から逃れられた人々は数知れず、お礼参り・願掛けの参拝者は後を絶ちません。
御祭神の「天目一箇命」は、御本宮・天津彦根命の御子神であり、伊勢の天照大御神の御孫神にあたります。古書(古語拾遺)では、天照大御神が天の岩屋戸にお隠れになった際、刀や斧などを作って活躍された神として伝えられており、このことから、鉄工・鋳物等をはじめとする日本金属工業の祖神・守護神として崇められています。毎年11月8日には、「ふいご祭り」というお祭りが斎行され、桑名近辺の会社はもとより全国の関連業者の方々が参拝に訪れます。
また、多度大社周辺は揖斐・長良・木曽の三大河川が集中しており、昔は一度大雨が降るとたちまち増水し、川から水が溢れ、大洪水となって岸辺の集落を呑み込んでしまうような事が度々起こりました。その為、地域の人々は、自分たちの生活を左右し、場合のよっては生命までも脅かされる恐れから、天候を司どると信じられてきた一目連神社に真剣な祈りを捧げて来たのです。これとは逆に、雨が降らず、日照りが続くと米の収穫ができず、食糧難に陥ることから、雨乞い祈祷も盛んに行なわれてきました。
また、海上で仕事をされる人々にとっても天候に対する思いは同じで、天気予報の無かった時代はなおさらでした。漁に出ていたところ、急に海が荒れだして、大時化(おおしけ)の中、一目連神のお導きによって、命からがら岸辺にたどりついた逸話は数多く残されています。
また、一目連神社の御社殿は正面の御扉が無いという、大変珍しい構造をしている事は見逃せない一例です。このことは古文書にも見られるように、非常時に神様が御神意を発する際、龍に姿を変えて天高く駆け上り、いち早く出向かれるためであると云われています。



「明圓寺(みょうえんじ)」
真宗大谷派 瑞瑋山
桑名市西鍋屋町16


「教覚寺(きょうかくじ)」
浄土真宗本願寺派 松下山
桑名市東矢田町
益田庄地頭職二階堂氏の一族が文明3年(1471)に桑名郡町屋に道場を開き、のち東方村にうつり、さらに現在地に移る。


「善西寺(ぜんさいじ)」
浄土真宗本願寺派 走井山
桑名市西矢田町27-2



桑名の名物の「焼きはまぐり」については前に紹介したが、ここでは「時雨蛤」である。
名物の「時雨蛤」はボイルした蛤のむき身を醤油を沸騰させた大鍋に入れて「浮かし煮」と言う独特な方法で煮るのである。味付けに生姜を刻んで入れる。
元は「煮蛤」と呼んでいたが、松尾芭蕉の高弟が、10月の時雨が降り始める頃から作られるために、「時雨蛤」と名付けたとある。
その発祥の地は、先に紹介の昼ごはんを食べた「赤須賀漁港」周辺で、元禄時代から作られ初めたとある。「時雨蛤」にすることで、風味と保存性が高まった事は言うまでも無い。
暖かいご飯に載せて食べると、他に”おかず”なしで、いくらでも食べられる、私の大好物であるが、「桑名の殿さん、時雨で茶々漬け」と歌われるように、お茶漬けにするのも美味しい食べ方である。
<< 続く >>













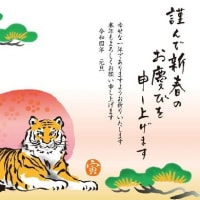






お寺さんには、残念ながら、あまり興味は持てま
せんが、食べ物には興味が湧きます。私も「しぐれ
はまぐり」は大好きです。時々スーパーなどで大売
出しがあります。そういうときには、買ってきて、お
茶漬けにして食べます。美味しいですよね。
「しぐれはまぐり」は、熱いご飯に添えてよし、お茶漬けによし、おにぎりにしても大変美味しいし、保存も効きますから貴重な食べ物です。長い間掛かったのかも知れませんが、昔の人はうまい事を考えたものだと感心します。
ただ、国産品は高いのが難点です。