山野草展があると友に教えられたので、町の広報を見て日にちを確認し、2017.05.21(日)訪れた。概要は前回の当ブログで紹介したので、今回は私の「花写真鑑」にまだ無い花(以下“新種”という)のみを載せたいと思う。
場所:西菰野公会所 主催:きらら会
“けったいな”(?)花である。 これでも我が国に古くからお住まいとは驚いた。 内部へ蠅などが入ると、毛で出られないようになっており、食虫植物のようだ。

どこにでもある雑草であるが、このよういに斑入りになると、山野草として、鑑賞の対象になるようだ!。

山野草らしい花だ。

「チャボシライトソウ(矮鶏白糸草)」 “新種”登録 第1513号


「ヒメウラシマソウ(姫浦島草)」 “新種”登録 第1515号

「ホテイコアニチドリ(布袋小阿仁千鳥)」 “新種”登録 第1516号

南アフリカ出身の多肉草のようだ。

花の名前とご生誕地は中国らしいことは判明したが、その他のことは一切不明、最近になって入ってきた物のようで、まだ世間には殆ど知られていないようである。


「ユキワリコザクラ(雪割小桜)」 “新種”登録 第1520号
花の直径が10mmもない小さな「サクラソウ」である。

第四回目の山野草展の概要は以上であるが、 “新種”が11種類あり、その合計は1520種となった。 ここでは40種類ほどの植物を撮ったので、11/40=0.275とかなり低率であった。 今までの山野草展とは大きな違いを見せたが、これも当然の帰結と考える。
私も含めて、花を植える者は多くの場合、人が植えない花、珍しい花に飛びつく習性があるようであるが、山野草愛好家も似たところがあるようで、珍しい花が多かった。 これらの花はまだ一般には出回っていないようで、名前や状態などを調べようにも手がかりさえない花が結構ある。
また、外見から“新種“であることは、 略間違いないと思っているが、その名前すら確認できないものが、4種類ほどあった。 展示会場に書かれた名前があっても、一般には通用しない名前のため、大変勿体ないが”新種“登録を見送ったのであった。
前回、「ヒメフウロ」と「ヒメフウロソウ」とは別の種であることが分かったと書いたが、 今回は会場の標識は「ユキワリサクラ」とあったが、この名前では花は見当たらず、よくよく調べたら「ユキワリコザクラ」が正しい名前であることが判明したのであった。
以上













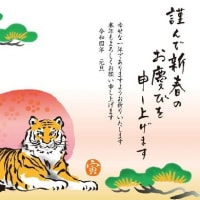






”若く明るい 歌声に雪崩は消える 花も咲く 青い山脈 雪割桜”
ヤフー知恵袋では正式名称はツバキカンザクラと言ってますがいい加減な話ですね。
そうでした「青い山脈」でうたってましたねー!。♪・・・ユキワリザクラ・・・♪・・・とね!。
花の名前は、同じ花でも地域によって異なったり、時代によって変わったりとかして、いくつも名前がある花が多いです。 しかし、よく見ると少しずつ異なることもあり、地域によっては環境や土の質が変わるので、その影響で元は同じでも長い間には変わってくることもありましょう。 これらをひとつひとつ名前がついていたりすると、名前の数は無限に増えてくる事になります。
最近は新しく作った花を、より珍しくして、売り上げを伸ばすために、少し変えただけで、異なる名前でうられています。 こんなのをいちいち数えることは、全く無意味なことと思います。