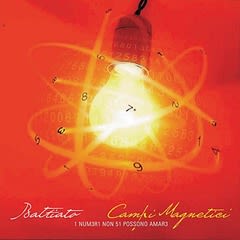”Shangaan Electro - New Wave Dance Music From South Africa ”
ああ、ついにアフリカから来た来た来たっ!
いやぁ、このところずっとアフリカ発の生きの良いサウンドに出会えず、すっきりしない気分が続いていたんだ。で、ネット某所にキンシャサとかで撮られた現地の若い衆によるラップなんかの愚劣な映像がいくつも紹介されているのなんか見つけて、「そうか、アフリカも、世界中を同じ退屈の鉛色に染め替える、あのラップの泥沼にうずもれて腐り果てて行くのか」なんて、すっかり落ち込んでいたんだが。
いやあ、やはりアフリカは負けない、こんな面白い音楽が芽生えていたんだねえ。
音楽の名はシャンガーン・エレクトロというらしい。このCDの副題には”南アフリカ発のニュー・ウェーブ・ダンスミュージック”とある。一言で表現すればそういうことになるんだろう。レコーディングは2004年から2009年と言うことで、どうやら現在進行形で南アフリカ・ローカルで燃え盛りつつある最新サウンドの実況報告としてのコンピレーション・アルバムのようだ。
ジャケにグロテスクなホラー風味の扮装をしたバンドのメンバー(あるいはダンサー)の姿があしらってあるのが象徴的だが、いかにもクールな諧謔趣味が各バンドの演奏を貫いている。(バンドと言っても、ここに収められた演奏がそれぞれ、どの程度独立性を持っているのか、よく分からない。同じ演奏家の手になると思われる音があちこちに出てくるし、実はメンバーがかなり重複する、あるいは、かなりの実力者らしいプロデューサーが全体のサウンドを弄繰り回しているのか。なんか後者のような気がするが)
音は、乱打されるマリンバの音とチープなキーボードの電子音が絡み合い、民族色あったり無機的だったりのソロやコーラスの歌声と一緒に、やたらとぶっ早い打ち込みのリズムに乗って疾走して行く。ブラックジョークっぽい語りや叫びが随所に挟み込まれ、音楽に含まれる猥雑度をいやがうえにも高める。
近代テクノロジーと民族性の融合なんて話が始まると、なんか素晴らしい新時代のサウンド誕生、なんて方向に話が行くのがワールドものの定番だが、この場には変な上昇志向なんかかけらもうかがえず、ひたすらお調子者の浮かれた疾走が続く。こいつは韓国のポンチャクなんかの魂の兄弟というべき音楽なのだろう。
「アフリカに先祖がえりしたアフロ・キューバン音楽の」なんて定番の解説も、「おっさん、意味ない話はやめろよ」と道化師のおどけた哄笑に吹き飛ばされるがオチだろう。南アフリカの伝統音楽の影は濃厚に差しているのだが、休み無く打ち込まれるテクノな乗りの電子音からの突っ込みに絶えず晒され続け、漫才の相方の地位を強いられたままだ。頻出するマリンバの響きも、民俗音楽的というよりは、テクノだったりミニマル・ミュージック的だったりの方向にすっ飛んでいる感じだ。
なんか意味不明の文章で訳分からないと思うけど、いやあ、音楽自体が訳分からないんだから。それも、素晴らしく素敵にクールにムチャクチャなんだからしょうがないよ。
さて、この音楽の明日はどっちだ?なんて余計な事は考えずに、思いっきりのアホのポーズで見守らせてもらおう。行け行け、シャンガーン・エレクトロ!
ああ、ついにアフリカから来た来た来たっ!
いやぁ、このところずっとアフリカ発の生きの良いサウンドに出会えず、すっきりしない気分が続いていたんだ。で、ネット某所にキンシャサとかで撮られた現地の若い衆によるラップなんかの愚劣な映像がいくつも紹介されているのなんか見つけて、「そうか、アフリカも、世界中を同じ退屈の鉛色に染め替える、あのラップの泥沼にうずもれて腐り果てて行くのか」なんて、すっかり落ち込んでいたんだが。
いやあ、やはりアフリカは負けない、こんな面白い音楽が芽生えていたんだねえ。
音楽の名はシャンガーン・エレクトロというらしい。このCDの副題には”南アフリカ発のニュー・ウェーブ・ダンスミュージック”とある。一言で表現すればそういうことになるんだろう。レコーディングは2004年から2009年と言うことで、どうやら現在進行形で南アフリカ・ローカルで燃え盛りつつある最新サウンドの実況報告としてのコンピレーション・アルバムのようだ。
ジャケにグロテスクなホラー風味の扮装をしたバンドのメンバー(あるいはダンサー)の姿があしらってあるのが象徴的だが、いかにもクールな諧謔趣味が各バンドの演奏を貫いている。(バンドと言っても、ここに収められた演奏がそれぞれ、どの程度独立性を持っているのか、よく分からない。同じ演奏家の手になると思われる音があちこちに出てくるし、実はメンバーがかなり重複する、あるいは、かなりの実力者らしいプロデューサーが全体のサウンドを弄繰り回しているのか。なんか後者のような気がするが)
音は、乱打されるマリンバの音とチープなキーボードの電子音が絡み合い、民族色あったり無機的だったりのソロやコーラスの歌声と一緒に、やたらとぶっ早い打ち込みのリズムに乗って疾走して行く。ブラックジョークっぽい語りや叫びが随所に挟み込まれ、音楽に含まれる猥雑度をいやがうえにも高める。
近代テクノロジーと民族性の融合なんて話が始まると、なんか素晴らしい新時代のサウンド誕生、なんて方向に話が行くのがワールドものの定番だが、この場には変な上昇志向なんかかけらもうかがえず、ひたすらお調子者の浮かれた疾走が続く。こいつは韓国のポンチャクなんかの魂の兄弟というべき音楽なのだろう。
「アフリカに先祖がえりしたアフロ・キューバン音楽の」なんて定番の解説も、「おっさん、意味ない話はやめろよ」と道化師のおどけた哄笑に吹き飛ばされるがオチだろう。南アフリカの伝統音楽の影は濃厚に差しているのだが、休み無く打ち込まれるテクノな乗りの電子音からの突っ込みに絶えず晒され続け、漫才の相方の地位を強いられたままだ。頻出するマリンバの響きも、民俗音楽的というよりは、テクノだったりミニマル・ミュージック的だったりの方向にすっ飛んでいる感じだ。
なんか意味不明の文章で訳分からないと思うけど、いやあ、音楽自体が訳分からないんだから。それも、素晴らしく素敵にクールにムチャクチャなんだからしょうがないよ。
さて、この音楽の明日はどっちだ?なんて余計な事は考えずに、思いっきりのアホのポーズで見守らせてもらおう。行け行け、シャンガーン・エレクトロ!