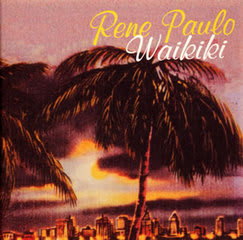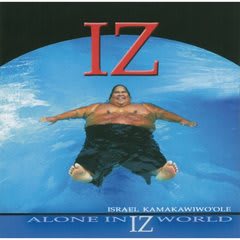”Hawaiian Memories”by NA LEO PILIMEHANA
ハワイの人気者女性3人組のコーラスグループ、”ナレオ”の2005年度作品。(グループ名は”"the voices blending together”を意味する、とのこと)
このアルバム、そのほとんどが古くからハワイに伝わる伝承歌なのだそうで、実際、なだらかな起伏を描く流れるようなメロディののどかな曲が続き、大いなるハワイの自然と人々の心に包まれるようで、実に癒されるものがある。
そもそもこのグループ、ただ音楽好きの女子高校生が集まり、自ら楽器を弾きながら遊びで歌っていたものが、コンテストで優勝したのをきっかけにプロの歌い手となってしまったなんて次第らしいが、いかにもそんな気安さが音楽の中に流れていて気持ちがいい。この種の楽園音楽で気張られたって扱いに困るからねえ。
いかにもハワイと言っていいのか、それぞれにいくつもの民族の血が混交している感じのメンバーの顔立ちだが、その歌唱法は特に民族色を伝えるものではなく、ジャズ的というか平均的アメリカンポップスらしいもの。いかにもアメリカの平均的健全な家庭に育ったお嬢さんたち、みたいな空気がくっきり伝わってくる歌声だ。
もともと、”本土”であるアメリカから伝わってくるポップスに心ときめかしていた彼女らなのであって、ナレオの3人は普段はそれらのものに大いに影響を受けた”ハワイ風のアメリカン・ポップス”を主に英語で歌っている。どちらかと言えば、それが彼女らの本来の顔なのである。
そんな彼女らが20年に及ぶと言うキャリアの中でただ一枚世に問うた、ハワイ民族の血にかかわるアルバム、それがこの”ハワイアン・メモリー”だった。
ナレオの三人の、澄んだコーラスによって歌い上げられる古い、はじめて聴くのに懐かしいような旋律は、その癒し効果によってこちらの心を包み込む。
が、やがて私たちは知るのである。それら旋律の底に沈んでいるのは、失われたハワイ王国の哀しみの記憶である事を。 そいつはまるで”気配”と言ってしまえるような儚さだが、歌の中心に深い陰影を刻んでいるような気がする。