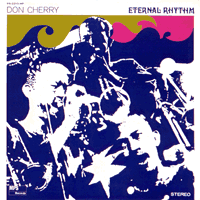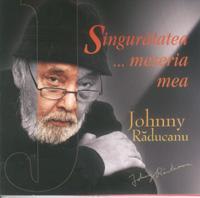と言うわけで。前回、前々回と、すっかりジャズ・ミュージシャンにがっかりさせられちゃったなあ、なんて流れになってきたんで、ジャズ・ミュージシャンがワールドミュージックの視点で見て凄く素敵な仕事をしている盤でも挙げておく。といっても、その仕事をしたのはジャズ・ミュージシャンと一言で言いきれるとも思えない人だけど。
そんな訳で、ドン・チェリーの「永遠のリズム」など。なんか、上のテーマで語る盤としては、あまりにど真ん中過ぎて恥ずかしくなって来る、我ながら。もう少しひねりってものはないのか、おい。と私は言いたい、自分に。
この音楽を語るにあたって、ガムラン音楽を取り入れたフリージャズのサウンド、という概要をまず言っておかねばならないが、ここでドン・チェリーはそれほど真面目にガムランに取り組んでいる訳ではない。なんとなく雰囲気的には、ってレベルのものである。
で、この場合はそれで良いのだろう。フリー・ジャズの演奏者としてチェリーがいつも目指して来たのは・・・これもベタなフレーズで書くのも恥ずかしいが、こだわりを捨てた身軽な感性で奏でられる音楽によって、魂の自由へ到達するって事だから。たとえばここでは「ガムランなる、異国インドネシア独特の音楽を、あえて演奏する者」なるフィクションに自らのミュージシャンとしての立場を仮託することによって得られる自由が、チェリーの欲したものだ。チェリーはここで、”ガムランごっこ”によって架空の楽園の扉を開こうと試みる。
このアルバムにリアルタイムで出会った学生時代は、ずいぶん難解なサウンドと感じられた。まだまだ「音楽とはこんなもの」との固定観念の塊だったからね。民族楽器によって繰り返し提示される不思議な音階と、唐突に暴れまわるソニー・シャーロックの凶悪ギター・ソロ。チェリーが吹く、なんとも捉えようのない二連笛のメロディ。どれも初めて耳にするものばかりで、理解しようとすればするほど、音楽は遠くに行ってしまった。
でも今、それなりの年齢に達して虚心坦懐に耳を傾ける「永遠のリズム」は、何も難しい音楽なんかじゃない。ドン・チェリーは”ガムラン音楽のようなもの”なるオモチャを手に、嬉々として、この地上と天上界を行ったり来たりして遊んでいる。それだけの音楽に難しいも何もあるものか。変に理解したり分析したりしようとするから音楽が遠くに行ってしまうだけの話でね。
そして聴衆たる我々は、ドン・チェリーの手にした幸せに、どこまで”感染”できるかが勝負だろう。鍵は、こちらがつまらないこだわりや定めごとから、どれだけ自由になれるかである。
だから、心の持ちようによっては音楽への開かれた門戸は広くもあり狭くもある。自分のやっている事を”アート”として認知されたいとか、くだらないスケベ根性を懐に呑んでいる奴にはとびきり狭い門戸だろう、少なくとも。うん。ああ、いい気味だ。
この音楽の所属カテゴリー、ドン・チェリーの出自がアメリカ合衆国であるのだから”北アメリカ”にすべきだろうか、いや、ガムランを取上げているから、いっそアジアにしてしまえ、などと迷ったのだが、やはり”その他の地域”が妥当でしょうね。国籍不明とするのが、もっと良いんだろうけれども。