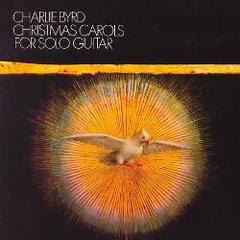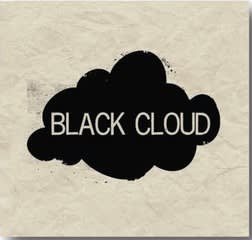”Christmas Carols for Solo Guitar”by Charlie Byrd
土曜日の夕食時、母が私に尋ねたのだった。「おまえ、去年の年の暮れは一人で何してたの?」と。何って、昼間はあなたを病院に見舞い、夜はコンビニ弁当を食べながらテレビを見てたのさ。まあ、今やってることと大差はないやね。
それにしても我が母、今頃になって、つまり一年も経ってから、去年末の自分の入院騒ぎの際、私がどんな暮らしをしていたのか気になりだしたのか。まあ、いいけどねえ。
特に面白いこともない年の瀬。それでも、母が倒れて入院し、今後、寝たきりかも、とか認知症発症の可能性とか言われて真っ暗になっていた昨年の年の瀬を思えば、何もないのは何よりのこと、とも思えて来る。天国にさえ。いや、まったく。
ちょっと不思議なポジションを取り続けたジャズギタリスト、チャーリー・バード。彼の出したクリスマスキャロル集である。大向うに受けそうなクリスマスソングの有名どころなど一曲も含まず、地味なキャロルばかりが並んでいる。
チャーリーもジャズギタリストとしての個性はここでは封印し、クラシックギターの教則本的テクニックによる、シンプルなメロディ提示に終始している。真摯な演奏とでも言うべきか。聴いていると、シンと澄んだ心になって行く気がする。
ガットギターがバランと和音を奏でると、それが教会の鐘の音を思わせる響きで、空気の中に広がって行くようだ。ベツレヘムの町の名が付された二つの曲が妙に心に残った。