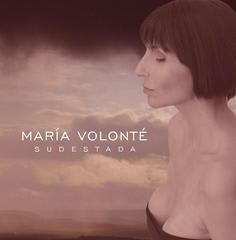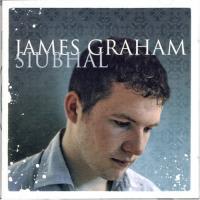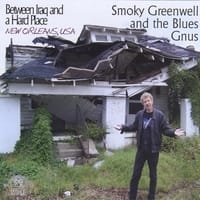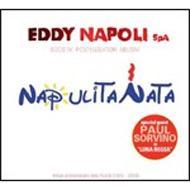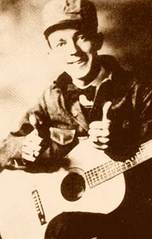”SUDESTADA ”by MARIA VOLONTE
日常の雑記のようなものを日記に書きたい気持ちがないので(なんだそれは)ここには書かなかったが、このところずっと、心がささくれ立つような日々が続いている。その原因と言ってもまあ誰にでもあるであろう生活上のゴタゴタなので、いちいち挙げない。そんなものは、書くほうも読むほうもつまらない。
ただ心象風景として、砂埃を上げて吹き過ぎて行く空っ風のようなものがここのところずっと心中にある。
さっきまでさっぱり実りのない会話を交わしていた、たとえば仕事上の交渉相手に対する呪詛の思いがわだかまっていたりする。あのバカが、と。ほんの30分前には彼は、初対面の人物であったのだが。
どこかで運命のボタンの掛け違いのようなものがあり、私を含めた人間たちは皆、壊れた機械人形のようにピントはずれの動きを繰り返しているように見える。
もう何度か書いたことだが。10年以上前、椎名誠の書いた南アメリカ最南端、パダゴニア地方への旅行記を読んでいるうちに、なぜか分からないが「タンゴを聴きたい」という焼け付くような欲求が生まれた。
何も分からず買ってきたCDのうちの一枚が、今回取り上げるマリア・ボロンテのタンゴ歌手としてのデビュー・アルバムである「タンゴとその他の情熱と」だった。
その、古臭いタンゴ曲ばかりをギターとバンドネオンのみの伴奏で歌った物寂しいアルバムが妙に心にフィットしてしまい、以来ずっと、私は時代遅れのタンゴ・ファンを続けているのだが。
この盤はそのマリアが昨年発表した今のところ最新作。もうすっかり彼女もタンゴ歌手の中堅どころとして貫禄を示すようになっている。
ほとんどの曲で、いわゆるタンゴ”のあの、タッタッタッと刻まれる四角四面のリズムの提示がない。代わりに、ほとんどフリーリズムで静かに和音を奏でるピアノやギターによる隙間の多い音空間がある。そこに一つ一つ言葉を乗せて行く様に語り歌うマリア・ボロンテがいる。非常に内省的というか瞑想的な歌唱である。
なんだかシャンソンかサンバ・カンシォンのような、あるいは深夜過ぎのジャズ・クラブのような感触も忍び寄る、文学臭の強い世界である。あらわな感情の表出はなく、すべては流れ過ぎた時の中で抽象化され、ジャケ写真を染めているのと同じセピア色に包まれて揺れている。
だから初聴きの際には、「これはどういう企画のアルバムなんだ?」と何度も歌詞カードの表記を検めた。
と言っても、そこにあるのはアルゼンチン盤だから当たり前と言おうか、私にはほんの少ししか理解の出来ない、スペイン語の文章ばかりである。
なんとか読める英語表記部分には、彼女がラプラタ河に面した家に住んでいた頃に心に行き来していた想いを記した詩のような言葉があるだけで、アルバムの音楽的狙いなどを知る助けにはならない。
フォルクローレの大物がプロデュースしているとのことで、タンゴの民謡的展開を意図したアルバムなのかも知れない。
などと戸惑いつつ聞き返すうち、冒頭の”マリア”なる曲、タンゴ界の大物、アニバル・トロイロの作だそうだが、この曲などは不思議な形はしているものの、じっくり味わえば実に深いタンゴ表現となっていて、気が付けば何度も聞き返している。
アルバム・タイトルは、ラプラタ地方を吹き抜ける荒風を表すとか。こんなに静けさに満ちた音楽世界なのに?この辺も深いものがある。のだろう。
などと適当な事を呟くうち、ふと脳裏に浮かび来るのは、吹き止まない荒野の風に晒され、すべての感傷を剥ぎ取られた貧しい土地の上の人生。壊れた船着き場と、地平線に沈んで行く遠い夕日。
遠い昔に見たタイトルも忘れた映画の記憶の断片。大地に置き忘れられた人々の物語と歌。