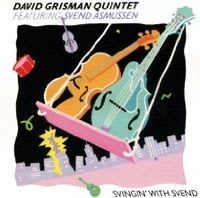”Cool Struttin' ”by Sonny Clark
相変わらず体調悪いわけですが。悔しいなあ。なんとか負けずに音楽日記も更新したいところなんだけど、そもそもCDを取り出してプレイヤーに入れる、なんてことが気が重くてできないんだから、どうにもならない。さらに、そのCDの音楽と今の体調の悪さに苦しむ気分の記憶とが分かち難く結びついてしまい、今後、それを聞くたびに記憶が蘇る、なんてことになったら嫌だから、そういう意味でもあまり積極的に聴く気になれずにいたりする。
まあともかく、音楽聞けなくっちゃあしょうがないです。結局、音楽ってのは健康な人のものなんだね。それが陽気なものであれ、陰気なものであれ。
それでも、深夜、一人で耳を傾けるラジオなんかから流れてくる音楽には時に心惹かれたりする。こちらが選んだのではない、あくまでも偶然流れてきたものゆえ、重さを感じずに済む、ということなのかもしれない。
そう言う意味でともかく一番ありがたいプログラムは、NHKラジオ深夜便で時たまやる”エンジョイ・ジャズ”のコーナーだ。毎回、テナー・サックス名演集とかコール・ポーター作品集とか、なかなかかゆいところに手が届く(?)テーマを流してくれる。
こちらもさすがにマイナーなミュージシャンに入れこんで偏屈なマニア道を歩き倒していた青春時代はもはや遠く、それら”普通の”テーマを素直に受け入れる気分になっている。というか、ジャズ再入門講座みたいなもので、若い頃粋がって聴かなかった演奏などがスイスイ心の中に入ってきて、逆に新鮮な気分なのだった。
いつぞや流れたハードバップ特集などまさにそれであって、時代のど真ん中、そのまた先端を突っ走っていた頃のジャズが躍動する姿がくっきりと浮き彫りになっているわけだ。このハードバップという音楽は。その、颯爽と肩で風を切る様子があまりにかっこよくて、何やら嬉しくなってしまった。
ジャズを聴き始めの頃は、この種のものを「そんなまともなジャズなんか聞いていられるかよなあ」とかうそぶきつつ、コルトレーンやアイラーの地獄の咆哮に入れ込んでいたはずなんだが。
まあ、それも時代、これも時代、ということなのかね、要するに。