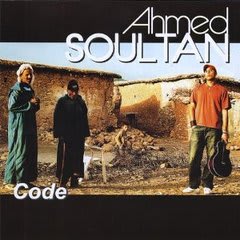”CCM for Consolation”
まるで信仰心なんてないくせに、宗教音楽となると変に入れ込んでしまう私が最近、気になっているのが、韓国のCCM(contemporary christian music)なのでありますが。
まあ、欧米のゴスペルの影響下に、その国なりのキリスト教系ポップスを作り上げた、なんてあたりはインドネシアのロハニなんかと同種のものかとも思えます。結構洗練された都会派ポップスの相貌を持っているのも共通している。
が、ロハニと比べると、あの南国の熱情とラテンの血の騒ぎみたいなものは見受けられません、韓国のCCMには。代わりにあるのは爽やかさ、でしょうか。ある韓国通の人のブログの表現によれば”パステル調のポップス”と言うことになる。朝の目覚めのBGMには、ちょうどいい感じ。胃にもたれない軽さで綺麗な、そしてちょっぴり切ないメロディがクリアな発声のボーカルによって爽やかに歌われて行きます。
とはいえ、先のブログでは「韓国語の分からない人には、気持ちよく楽しめるでしょう」なんて苦い(?)一言で紹介文は終わっているのであって。
なにしろ教会での礼拝の際にも歌われると言うCCM、歌詞はやはりディープなキリスト教信者のためのものであり、そうでない者にはかなりの違和感を与えるものなのであろうかと思われますな。
爽やかに聴いていられるのは、語学力なきゆえに韓国語をただの”サウンド”として聴いてしまえるのが幸いといえるのかも知れません。まあこれはロハニなんかも同じ、というかゴスペルだってカッワーリーだって同じことだろうけど。
ここに取り出しましたるは、”CCM for Consolation”なる、4枚組CD。わざと、一番俗っぽそうなのを買ってみました。
このタイトルといい、きれいなモデルのお姉さんがおしゃれにポーズをとっているジャケといい、どうもあんまり生真面目な宗教っぽさは感じません。なんか、リラクゼーションのためのアロマオイルのパッケージみたい。
で、収められているのが石鹸の匂いがしそうな健全な男女の歌手の爽やかポップスというわけで、もしかしたら現地では特にクリスチャンに限定せずに、普通に”癒しの音楽”として大衆に受け入れられているのかなあ、などとも思えてきます。まあ、歌詞の問題はひとまずおくとして。
でもいいのかなあ、こんな風に「疲れなくていいや」とか言いつつ気軽に聞き流していて。まあ、私が韓国語を理解できるようになる日は、もし来るとしても相当先のことにあるだろうしね、とりあえず、このまま。
下に試聴として、これはカバーもかなり多いし、韓国CCMを代表するナンバーと言っていいんじゃないでしょうかね、「愛されるために生まれた」なる曲を貼っておきます。画面に歌詞英訳が出るんで、その世界を理解する一助となるかと。まあ、この曲なんかは、あんまり賛美歌っぽくはないけど。