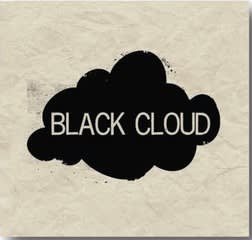”Black Cloud”by Davina Sowers & The Vagabonds
こいつは最近のアメリカの女性シンガー・ソングライターの中でも出色といっていいのではなかろうか。女傑、Davina Sowers。
女版ドクター・ジョンかトム・ウエイツか、といったノリで、ホーンセクションを含むオールドジャズ調のバンドを従え、ピアノの鍵盤をぶったたきながら、どでかい声でジャジィにブルージィに呻き、叫ぶ。ともかくそのエネルギッシュなパフォーマンスには敬意を表するしかない。
盤に収められている曲はすべて彼女の自作なのだが、見事に今の時代の流行とは関係がない。古道具屋の店先で見つけたSP盤の流行り歌をコピーしたのだといわれれば、たいていの人は納得するだろう。あるいは、”マスウエル・ヒルビリーズ”期のレイ・デイヴィスを想起させるものもあり。
アメリカの古いジャズやポップスへのオマージュなのか、皮肉なのか。Davina Sowers。の歌には、黒光りした苦味がその底に一貫して流れている。セピア色に彩られた時代錯誤のジョークの影に、現世に対する痛烈な批評がちらつく。それらが強力なスパイスとして作用しているからこそ、これらの歌、作り物のクセにこんなにもリアルに響き渡る。
それにしても、Davina Sowers。何者なんだ、この女は。その歌、ニューオリンズの古い通りの匂いまで伴って。もう何度、聴き返したか。