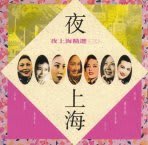フランク・チャックスフィールド楽団と言えば、1940~50年代を風靡したイギリスのムード・ミュージックの大御所ですが。と書いて自ら笑っちゃうんだけど。そんなものに興味を持つワールドミュージック・ファンなんかいるもんかってば。
でもまあ、話をはじめてしまったものは仕方が無いんで続けるのですが。この楽団の1952年の録音に「ハイ・ヌーン」ってのがある。ウエスタン映画の名作、”ハイ・ヌーン”のテーマ曲ですな。カントリーっぽいメロディの、のどかにしてなかなか切ない曲で、私も子供の頃、好きでしたねえ。
で、今回問題にするのは、それをチャックスフィールド楽団が、彼らのレパートリーとして吹き込み直したものなんですが。そのアレンジがなんとも奇怪なものでありまして。
まずボンゴが、”ぽっぽこすぽぽぽ♪”と間抜けた、と言ってよいリズムを奏でます。開拓時代のアメリカ中西部、というよりは、ハリウッド映画に出てくる”南海の原住民の村”を想起させる、場違いな雰囲気。
それに乗って、これはオーボエでしょうか木管楽器の音が、これもマヌケと紙一重ののんびりとしたタッチで曲の冒頭部分を吹き鳴らします。妙にコブシの回った、なんだかチャルメラの音一歩手前、みたいな印象を与えつつ、メロディは渡って行きます。
と、そこに”ボワ~~~ン!”と鳴り渡りますドラの音。
ここで他の管楽器も合流、合奏となるのですが、ここでアレンジの基本となっているのが6thの和音、中国の音楽を表す際に用いられる、”チャカチャカチャッチャッチャチャチャ~~~ン”なんてフレーズがありますね、あんな音の組み合わせが使われているんですよ。まあ要するに、どのようなメロディを奏でようと中国民謡に聞こえてしまう仕掛けになっている。
そして曲が佳境に入ると、さらに連打されるドラの音。おいおい。どう考えても楽団の主催者、チャックスフィールド氏は聞き手を完全にどこやら南の島に作られた中国街の一隅か何かへ連れて行くつもりのようだ。
いや実際、ちょうどこの頃、ムードミュージックの世界で人気を博していた、マーティン・デニー楽団の”エキゾティック・サウンド”ってのがあるんです。欧米人の異国幻想、南国幻想を音にして好評を博していたんですが。どうもチャックスフィールド氏も、そのサウンドをちょっと真似してみたくなったってのが本音じゃないですかねえ?
それにしても。私が面白いなあと思うのは、高度な教養を身に付けた英国紳士たる音楽家、フランク・チャックスフィールド氏にしてみれば、アメリカのカントリー音楽なんてものも、マーティン・デニーが採り上げた”南洋の土人の音楽”(当時の白人の人種意識を表現するため、あえて使ってますよ、この言葉)と同レベルの”低俗で無教養な大衆音楽”としか認識出来ていなかったんだろうなあ、ってことです。
この”ハイヌーン”の演奏に対するアメリカ市民の感想って、どこかに記録が残っていないかなあ?ぜひ、彼らの耳にどんな風に聞こえたか教えて欲しいものであります。南洋中華街風にアレンジされちゃった、彼らにしてみれば非常にドメスティックな流行り歌であるカントリー・ミュージックが。