東京・京橋にあるブリジストン美術館が本社ビル建て替えに伴い長期休館するということで、その前に「ベスト・オブ・ザ・ベスト」展を開催している。3月31日からは展示替えがあり、青木繁「海の幸」なども公開される。(5月17日まで。)3月17日から31日は、学生無料ウィークと銘打ち、大学生、高校生が何度でも無料で入れるとのことである。フランスや日本の近代美術を中心に、魅力的なコレクションを誇っていて、今までにも見た絵が多いんだけど、数年間休館するなら見ておこうかと思った。フィルムセンターの近くなので、最近ずっとアジア映画特集に通ってるので、その前に寄るのに好都合。


まず、最初の部屋にブリジストン美術館の開館(1952年)以来の歩みが展示されている。その前には彫刻の数々。あまり触れられないのだが、ここにはブールデルやロダンなどの近代彫刻、さらにエジプトやギリシャなどの古代彫刻がかなり多い。絵を見てると疲れてしまって、彫刻は通り過ぎてしまったりするが、すごくもったいない。さて、絵の展示室に入ると、モネ、シスレー、セザンヌ等の素晴らしい絵が並んでいて、さらに名を知る画家の作品が続々と出てくる。名前は誰かなと心で思い出しつつ見ていくと、ゴッホ、ゴーギャン、ルノワール、アンリ・ルソー、ルオー、マティス、ピカソ、クレー、モンドリアン等々、僕らが何となく知ってる画家の特徴に合うような絵が並んでる。逆に石橋の選択が、日本人好みを選んでいて画家の印象を作ってきた側面もあるのかもしれない。
先に載せた最初のチラシはピカソ《腕を組んですわるサルタンバンク》(1923)という作品で、ピカソの新古典主義時代の代表作だという。これは1980年の収蔵品だという。それより印象派やポスト印象派の作品群が強い印象を残す。特にセザンヌ《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》(1904~1906年頃)は、前にも何度か見てるけど非常に力強くて、またいかにもセザンヌ作品というイメージ。
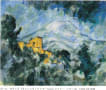
1987年に購入したルノワール《すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢》(1876)が絵葉書の売り上げダントツ1位だという。35歳のルノワールが出版業者のシャルパンティエに頼まれて描いた。ジョルジェットは当時4歳。父親は当時ゾラやモーパッサンの小説を出していたという。確かに実に愛らしい。一体、この子は近衛の後、どのような人生を歩んだのだろうと夢想を誘われる。1876年の絵で4歳だから、1872年生まれ。1914年の第一次世界大戦時には、42歳ということになるわけだが。

その後、日本近代絵画、特に藤島武二、安井曽太郎、藤田嗣治、岡鹿之助等の名品が続々と出てくる。最後に現代美術の部屋もあって、ついじっくり見なくなってしまうのだが、これももったいない。
ブリジストンというのは、もちろん世界的タイヤメーカーを作り上げた初代・石橋正二郎のコレクションに始まる美術館である。石橋は福岡県久留米の出身で、青木繁、坂本繁二郎と同郷である。若くして亡くなった青木作品の散逸を恐れる坂本のすすめで、青木作品を集め始めたのが始まりという。青木繁の絵は久留米の石橋美術館に収蔵されていたが、2016年9月をもって石橋財団から離れて収蔵品は東京に移るとされている。地方の名だたる美術館の役割をめぐって議論されているが、その是非はともかく、一度は見ておきたい絵ばっかりの展覧会。(チラシに割引券が付いてるが、ホームページにも100円引き券がある。)


まず、最初の部屋にブリジストン美術館の開館(1952年)以来の歩みが展示されている。その前には彫刻の数々。あまり触れられないのだが、ここにはブールデルやロダンなどの近代彫刻、さらにエジプトやギリシャなどの古代彫刻がかなり多い。絵を見てると疲れてしまって、彫刻は通り過ぎてしまったりするが、すごくもったいない。さて、絵の展示室に入ると、モネ、シスレー、セザンヌ等の素晴らしい絵が並んでいて、さらに名を知る画家の作品が続々と出てくる。名前は誰かなと心で思い出しつつ見ていくと、ゴッホ、ゴーギャン、ルノワール、アンリ・ルソー、ルオー、マティス、ピカソ、クレー、モンドリアン等々、僕らが何となく知ってる画家の特徴に合うような絵が並んでる。逆に石橋の選択が、日本人好みを選んでいて画家の印象を作ってきた側面もあるのかもしれない。
先に載せた最初のチラシはピカソ《腕を組んですわるサルタンバンク》(1923)という作品で、ピカソの新古典主義時代の代表作だという。これは1980年の収蔵品だという。それより印象派やポスト印象派の作品群が強い印象を残す。特にセザンヌ《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》(1904~1906年頃)は、前にも何度か見てるけど非常に力強くて、またいかにもセザンヌ作品というイメージ。
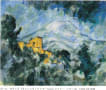
1987年に購入したルノワール《すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢》(1876)が絵葉書の売り上げダントツ1位だという。35歳のルノワールが出版業者のシャルパンティエに頼まれて描いた。ジョルジェットは当時4歳。父親は当時ゾラやモーパッサンの小説を出していたという。確かに実に愛らしい。一体、この子は近衛の後、どのような人生を歩んだのだろうと夢想を誘われる。1876年の絵で4歳だから、1872年生まれ。1914年の第一次世界大戦時には、42歳ということになるわけだが。

その後、日本近代絵画、特に藤島武二、安井曽太郎、藤田嗣治、岡鹿之助等の名品が続々と出てくる。最後に現代美術の部屋もあって、ついじっくり見なくなってしまうのだが、これももったいない。
ブリジストンというのは、もちろん世界的タイヤメーカーを作り上げた初代・石橋正二郎のコレクションに始まる美術館である。石橋は福岡県久留米の出身で、青木繁、坂本繁二郎と同郷である。若くして亡くなった青木作品の散逸を恐れる坂本のすすめで、青木作品を集め始めたのが始まりという。青木繁の絵は久留米の石橋美術館に収蔵されていたが、2016年9月をもって石橋財団から離れて収蔵品は東京に移るとされている。地方の名だたる美術館の役割をめぐって議論されているが、その是非はともかく、一度は見ておきたい絵ばっかりの展覧会。(チラシに割引券が付いてるが、ホームページにも100円引き券がある。)




























シスレーの絵画・版画を見ていくと風景画の中に点景としての人物がいて見る人に感情移入し易い面が特徴です。画面の奥行きや高い空、雲の表情、屋根の赤み、河面、海岸、舟、アヒルetc ,詩情溢れる至福の時間がそこに有りました。戸外で描いたのは事実にせよ少なくとも何度も何度も足を運んで、心象風景にまで昇華した作品だという気がします。マネもイマジネーションを重んじセザンヌのように風景を四角、楕円、線分に分解してから構成していた要素もあります。シスレーもまた、絵画の構成にそういう技法や想像力を駆使したのではないかー。ダイレクトに描いたと言うわけでは決して無くて、一度記憶の中に落としてから再構成した絵画のようにも思えた。