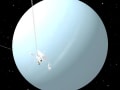茨城県で2019年に起きた殺人事件で埼玉県在住の男が5月7日に逮捕された。僕はその事件、あるいは容疑者については報道以上のことを知らないし、現在捜査中なので何も書く気はない。ところが、たまたま同じ市に容疑者と同姓の会社や議員がいて、全然無関係なのに関係者だと決めつけるデマが拡散されているという。そんな話は今までにも何度か聞いた。
最近ではキャンプ場で行方不明になった女の子の家族に関するデマ。あるいは2019年に起きた常磐道あおり運転事件の「同乗女性」のデマ。これは大きく報道され、裁判も起こされ、デマをSNSで拡散して人に賠償が命じられた。何も知らないのに憶測でネット上に書き込めば、刑事上、民事上の責任が生じる。そんなことは常識だし、なんで同じことを繰り返す人がいるのか判らない。これらを見ると、果たして「日本人の民度」は大丈夫なのかという気になってくる。
 (デマに賠償命令)
(デマに賠償命令)
「日本人の民度」と言えば、昨年の麻生副首相発言が思い起こされる。「日本人は民度が高いから、コロナの死者が欧米より低いという見解を述べた。「『おたくとうちの国とは国民の民度のレベルが違うんだ』って言ってやると、みんな絶句して黙る」んだそうだ。これに関しては当時「麻生『民度』発言と『オンライン申請』不備問題」を書いた。(2020.6.6)今の日本の感染状況を見て、麻生氏は何か思うところがあるだろうか。「緊急事態宣言」を出しては解除し、再び感染増が起きては再宣言する。これは民度が低いのか。
麻生氏と言えば、先頃「マスクはいつまでやるの?」と記者を問い詰めるかのように「逆質問」するという出来事があった(3月19日)。記者は反撃しないのかと思ったけれど、慣れてしまったのか、「こういう人」には腫れ物に触るように接するということにしてるのかもしれない。しかし、「日本国のナンバー2」が判らないことを、何で民間人が判るのか。麻生副首相こそが国民に伝えるべき立場でないか。一体どうなってるんだろう?
 (麻生氏のマスク発言)
(麻生氏のマスク発言)
現在の日本では「英国型変異株」が広まっている。では、それは何故日本に入り込んだのだろうか。外国から来た人は「2週間の自主隔離」をすることになっている。それがかなりの割合で守られていないという話をニュースでやっていた。連絡が付かなくなる人、公共交通機関を使って移動する人などが一定程度いるんだと思う。じゃあ、強制的に隔離すればといっても、人手も予算もない。だから、ある程度国民の良識に任せるしかない。しかし、現にこれだけ広がってしまった以上、外国から持ち込んだ人がいたということだろう。
持続化給付金の詐欺も2億円に達するという。大学生もいれば、競馬の騎手などがまとまって申請した例もある。自分でやってるわけじゃない。誰か指南役がいて、上納金がある。言われたとおりやって、貰えるものは貰おうと「軽い気持ち」でやってしまったという人が多いようだ。これは本人も悪いだろうが、「間違ったことにノーと言う」ことを教えられていないという問題でもある。「おかしいと思ったことに声を挙げる」というのは人生で最も大切なことの一つだ。しかし、日本では「自分だけガマンして黙っている」ことを親も教師も生き方で伝えてしまうことが多い。
 (持続化給付金詐欺)
(持続化給付金詐欺)
もちろん「民度」が高いとか低いとかいう発想自体に問題がある。民族だけでなく、それぞれの「地域」「家族」などにそれぞれの「文化」がある。ある一律の基準を作って、高い低いと評価することは出来ない。しかし、それでも社会を構成するメンバーとして、人に求められることがある。ゴミは捨てない、並んでる列に割り込まない、お店や公共交通機関など多くの人が利用する場所では他の客に配慮する、などなど。しかし、最近はこれが心配なことが増えている。実感としてそんな気もする。それを「民度」というならば、日本の民度は低くなっているのかもしれない。まあ、あまり他人のことも言えないかもしれないけど。
最近ではキャンプ場で行方不明になった女の子の家族に関するデマ。あるいは2019年に起きた常磐道あおり運転事件の「同乗女性」のデマ。これは大きく報道され、裁判も起こされ、デマをSNSで拡散して人に賠償が命じられた。何も知らないのに憶測でネット上に書き込めば、刑事上、民事上の責任が生じる。そんなことは常識だし、なんで同じことを繰り返す人がいるのか判らない。これらを見ると、果たして「日本人の民度」は大丈夫なのかという気になってくる。
 (デマに賠償命令)
(デマに賠償命令)「日本人の民度」と言えば、昨年の麻生副首相発言が思い起こされる。「日本人は民度が高いから、コロナの死者が欧米より低いという見解を述べた。「『おたくとうちの国とは国民の民度のレベルが違うんだ』って言ってやると、みんな絶句して黙る」んだそうだ。これに関しては当時「麻生『民度』発言と『オンライン申請』不備問題」を書いた。(2020.6.6)今の日本の感染状況を見て、麻生氏は何か思うところがあるだろうか。「緊急事態宣言」を出しては解除し、再び感染増が起きては再宣言する。これは民度が低いのか。
麻生氏と言えば、先頃「マスクはいつまでやるの?」と記者を問い詰めるかのように「逆質問」するという出来事があった(3月19日)。記者は反撃しないのかと思ったけれど、慣れてしまったのか、「こういう人」には腫れ物に触るように接するということにしてるのかもしれない。しかし、「日本国のナンバー2」が判らないことを、何で民間人が判るのか。麻生副首相こそが国民に伝えるべき立場でないか。一体どうなってるんだろう?
 (麻生氏のマスク発言)
(麻生氏のマスク発言)現在の日本では「英国型変異株」が広まっている。では、それは何故日本に入り込んだのだろうか。外国から来た人は「2週間の自主隔離」をすることになっている。それがかなりの割合で守られていないという話をニュースでやっていた。連絡が付かなくなる人、公共交通機関を使って移動する人などが一定程度いるんだと思う。じゃあ、強制的に隔離すればといっても、人手も予算もない。だから、ある程度国民の良識に任せるしかない。しかし、現にこれだけ広がってしまった以上、外国から持ち込んだ人がいたということだろう。
持続化給付金の詐欺も2億円に達するという。大学生もいれば、競馬の騎手などがまとまって申請した例もある。自分でやってるわけじゃない。誰か指南役がいて、上納金がある。言われたとおりやって、貰えるものは貰おうと「軽い気持ち」でやってしまったという人が多いようだ。これは本人も悪いだろうが、「間違ったことにノーと言う」ことを教えられていないという問題でもある。「おかしいと思ったことに声を挙げる」というのは人生で最も大切なことの一つだ。しかし、日本では「自分だけガマンして黙っている」ことを親も教師も生き方で伝えてしまうことが多い。
 (持続化給付金詐欺)
(持続化給付金詐欺)もちろん「民度」が高いとか低いとかいう発想自体に問題がある。民族だけでなく、それぞれの「地域」「家族」などにそれぞれの「文化」がある。ある一律の基準を作って、高い低いと評価することは出来ない。しかし、それでも社会を構成するメンバーとして、人に求められることがある。ゴミは捨てない、並んでる列に割り込まない、お店や公共交通機関など多くの人が利用する場所では他の客に配慮する、などなど。しかし、最近はこれが心配なことが増えている。実感としてそんな気もする。それを「民度」というならば、日本の民度は低くなっているのかもしれない。まあ、あまり他人のことも言えないかもしれないけど。