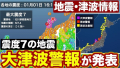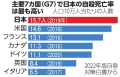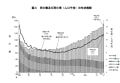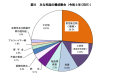2024年1月1日、よりによって元旦に起きた「能登半島地震」から、一週間経った。1月8日夜8時時点で、ネット上では、死者168人、安否不明323人と報道されている。能登半島では2020年12月以来群発地震が起きていたが、この地域には火山はなく地震の原因は「流体の上昇」などと言われていた。2023年5月5日に、マグニチュード6.5、最大震度6強の地震が起きたのを覚えている人も多いだろう。しかし、結局今回の大地震はやはり「断層が動いた」ことで起きたらしい。マグニチュード7.6とされている。

「マグニチュード7.6」と言われてもよく判らないかもしれないが、これは非常に大きな地震である。もちろん東日本大震災のマグニチュード9.0という超巨大地震とは比べられない。だけど、阪神淡路大震災(1995年)はM7.3、新潟県中越地震(2004年)はM6.8、熊本地震(本震、2016年)M7.3なので、今回の方が大きいのである。一番被害を受けた(と思われる)輪島、珠洲(すず)が震度7じゃなかったので、震度7を記録した(原発がある)志賀(しか)町が一番揺れたように思ったけれど、壊れ方を見ると輪島などでの震度7があったかもしれない。震度計が正確に動いていたかという問題がある。

同じことは津波にも言える。大津波警報が出て、数メートルに及ぶ巨大津波が来ると恐怖を感じたが(2011年のことが思い出されて)、その割に大きな津波にならなかった印象があるのではないか。もちろん大きな津波が来て被害はあったし、行方不明者も出ている。テレビを聞いて逃げたという報道もあるので、今までの経験が生かされたのも間違いない。ただ日本海の対岸でも相当の津波があったので(韓国で80㎝らしい)、震源間近の能登北部で津波が1~2メートルのはずがない。それは地震による地面自体の隆起があった影響があったのだと思う。輪島や珠洲は2メートル程度、最高では4メートルも隆起したというから、地面が高くなっただけ事前予報ほどの高さの津波にならなかったと思われる。(珠洲の津波計は壊れたという。)
 (津波)
(津波)
これだけのマグニチュードの地震が近いところで起きたのだから、家屋倒壊の被害が一番多いのも当然だ。阪神大震災型の地震である。その後耐震基準が変更されたわけだが、それ以後に建築された家でも倒壊があると言われる。詳しくは今後の調査が待たれるが、今までの地震、特に去年5月の地震でダメージを受けていた影響が大きいと思う。一部損壊では自治体からの補助がなく、また高齢化進行地域で経済的問題もあるし、建設業界の人手不足もあって、修理をしないまま正月を迎えた家が多いという事情があったらしい。しかも正月真っ只中で、帰省中の家族が集まったりしていたのである。
 (倒壊した家屋)
(倒壊した家屋)
帰省中や旅行中の人がいて、避難所は受け入れ予想を大きく超えた人数を受け入れたとされる。そのため備蓄した食料や水が早めに不足してしまった。今後は大雪も予想されるので、仮設住宅建設などが進む段階ではないだろう。むしろ寒い避難所で感染症が広がり、高齢者に多くの犠牲が出る可能性もある。ここは大胆に「二次避難」を進めるしかないと思う。過去に伊豆大島や三宅島、あるいは原発事故で避難したときのように、大規模な住民避難を行った方がよいのではないか。これは政府も考えているようだけど、他県でもよいし、条件が出来てくれば石川県内の温泉旅館などを大々的に借り上げることも検討するべきだ。
特に山間部の集落が孤立し、まだ情報が不明なところもあるらしい。輪島市長も道路が寸断されて市役所へ行けたのは3日だったという。さらに通信網も不通で、携帯電話が通じないという。電気が停まればテレビやパソコンも見られない。スマホの充電もいずれ切れる。日本の自然的、社会的条件から、このような高齢者が残る山間集落が大きな被害を受ける災害は、今後もっと増えるだろう。ここは「ドローン」の出番だと思うんだけど、何故無いんだろうか。「空飛ぶ車」なんか要らないから、水や食料を運べるドローンを開発することは日本に必要だろう。軍事費を増やすより、そういう開発に予算を掛けて欲しいと思う。
今回は様々な「想定外」が重なって、予想以上に多くの被害が起きている。阪神や熊本以上の規模の地震なんだから、大災害が起きることは当然だが、その後の対応には不十分なことも多いのではないか。津波警報など「東日本大震災」の教訓が生かされた点もあるが、全体的には問題点が多いような気がする。それらの問題点は今後も考えて行きたい。
ところで、僕は特に救助などのスキルがある人以外は、普通の生活を送っていればよいと思っている。救援や復興は税金でやるのに、皆が自粛していたら税収が減るばかり。「ふるさと納税」は以前何回か書いたように、制度自体がおかしくて反対。返礼品も用意出来ないだろうし。それに自分が住んでる自治体の福祉や教育に必要なお金を被災地に回すという発想そのものが理解出来ない。「善意」でやるのなら、幾つもある募金に送ればよい。

「マグニチュード7.6」と言われてもよく判らないかもしれないが、これは非常に大きな地震である。もちろん東日本大震災のマグニチュード9.0という超巨大地震とは比べられない。だけど、阪神淡路大震災(1995年)はM7.3、新潟県中越地震(2004年)はM6.8、熊本地震(本震、2016年)M7.3なので、今回の方が大きいのである。一番被害を受けた(と思われる)輪島、珠洲(すず)が震度7じゃなかったので、震度7を記録した(原発がある)志賀(しか)町が一番揺れたように思ったけれど、壊れ方を見ると輪島などでの震度7があったかもしれない。震度計が正確に動いていたかという問題がある。

同じことは津波にも言える。大津波警報が出て、数メートルに及ぶ巨大津波が来ると恐怖を感じたが(2011年のことが思い出されて)、その割に大きな津波にならなかった印象があるのではないか。もちろん大きな津波が来て被害はあったし、行方不明者も出ている。テレビを聞いて逃げたという報道もあるので、今までの経験が生かされたのも間違いない。ただ日本海の対岸でも相当の津波があったので(韓国で80㎝らしい)、震源間近の能登北部で津波が1~2メートルのはずがない。それは地震による地面自体の隆起があった影響があったのだと思う。輪島や珠洲は2メートル程度、最高では4メートルも隆起したというから、地面が高くなっただけ事前予報ほどの高さの津波にならなかったと思われる。(珠洲の津波計は壊れたという。)
 (津波)
(津波)これだけのマグニチュードの地震が近いところで起きたのだから、家屋倒壊の被害が一番多いのも当然だ。阪神大震災型の地震である。その後耐震基準が変更されたわけだが、それ以後に建築された家でも倒壊があると言われる。詳しくは今後の調査が待たれるが、今までの地震、特に去年5月の地震でダメージを受けていた影響が大きいと思う。一部損壊では自治体からの補助がなく、また高齢化進行地域で経済的問題もあるし、建設業界の人手不足もあって、修理をしないまま正月を迎えた家が多いという事情があったらしい。しかも正月真っ只中で、帰省中の家族が集まったりしていたのである。
 (倒壊した家屋)
(倒壊した家屋)帰省中や旅行中の人がいて、避難所は受け入れ予想を大きく超えた人数を受け入れたとされる。そのため備蓄した食料や水が早めに不足してしまった。今後は大雪も予想されるので、仮設住宅建設などが進む段階ではないだろう。むしろ寒い避難所で感染症が広がり、高齢者に多くの犠牲が出る可能性もある。ここは大胆に「二次避難」を進めるしかないと思う。過去に伊豆大島や三宅島、あるいは原発事故で避難したときのように、大規模な住民避難を行った方がよいのではないか。これは政府も考えているようだけど、他県でもよいし、条件が出来てくれば石川県内の温泉旅館などを大々的に借り上げることも検討するべきだ。
特に山間部の集落が孤立し、まだ情報が不明なところもあるらしい。輪島市長も道路が寸断されて市役所へ行けたのは3日だったという。さらに通信網も不通で、携帯電話が通じないという。電気が停まればテレビやパソコンも見られない。スマホの充電もいずれ切れる。日本の自然的、社会的条件から、このような高齢者が残る山間集落が大きな被害を受ける災害は、今後もっと増えるだろう。ここは「ドローン」の出番だと思うんだけど、何故無いんだろうか。「空飛ぶ車」なんか要らないから、水や食料を運べるドローンを開発することは日本に必要だろう。軍事費を増やすより、そういう開発に予算を掛けて欲しいと思う。
今回は様々な「想定外」が重なって、予想以上に多くの被害が起きている。阪神や熊本以上の規模の地震なんだから、大災害が起きることは当然だが、その後の対応には不十分なことも多いのではないか。津波警報など「東日本大震災」の教訓が生かされた点もあるが、全体的には問題点が多いような気がする。それらの問題点は今後も考えて行きたい。
ところで、僕は特に救助などのスキルがある人以外は、普通の生活を送っていればよいと思っている。救援や復興は税金でやるのに、皆が自粛していたら税収が減るばかり。「ふるさと納税」は以前何回か書いたように、制度自体がおかしくて反対。返礼品も用意出来ないだろうし。それに自分が住んでる自治体の福祉や教育に必要なお金を被災地に回すという発想そのものが理解出来ない。「善意」でやるのなら、幾つもある募金に送ればよい。