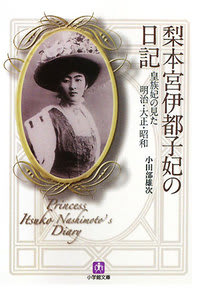 渋谷駅からほど近いわたくしどもの邸宅の敷地は、一周すると20分ほどかかります。使用人でございますか、執事を含めて30人ほどになりますでしょうか。日ごろは趣味を楽しみ、恵まれない方たちのボランティアもしておりますので、これでもけっこう多忙なのです。ええ、勿論、エステに通ってお肌の手入れも欠かせず、美貌を保つのも妻として当然でございます。夫を支え、こどもたちを育て、そんなわたくしの女子の本文はこんな感じになります。
渋谷駅からほど近いわたくしどもの邸宅の敷地は、一周すると20分ほどかかります。使用人でございますか、執事を含めて30人ほどになりますでしょうか。日ごろは趣味を楽しみ、恵まれない方たちのボランティアもしておりますので、これでもけっこう多忙なのです。ええ、勿論、エステに通ってお肌の手入れも欠かせず、美貌を保つのも妻として当然でございます。夫を支え、こどもたちを育て、そんなわたくしの女子の本文はこんな感じになります。「何事も せなにさきだつ ことなくて たゞその家を まもるべきかな」 伊都子
伊都子が現代に生きていたら、このように自己紹介をしたのだろうか。おそらくセレブな上流階級夫人としてマスコミにもてはやされるだけでなく、間違いないのは彼女が毎日更新を欠かさない人気ブロガーになっていたことだろう。
梨本宮伊都子妃は、明治15年(1882年)2月2日、鍋島直大侯爵の娘としてローマに生まれる。実家の鍋島邸は2万坪近い敷地にそれぞれ300坪ある日本館と西洋館が建っている。本書に当時の実家の写真が掲載されているが、とても個人の家とは思えない豪邸以上の破格のスケールだ。伊都子は世が世なら、鍋島藩のお姫様だった出自から、周囲に決められた皇族の梨本宮守正と19歳で結婚してめでたく別の豪邸の女主人、皇族妃となる。さまざまな戦争をへて、第二次世界大戦の敗戦後、夫の守正は皇室で唯一戦犯に指名され巣鴨拘置所に入るという危機も、無事に釈放されてのりこえたものの、占領政策により皇室費は大幅に削減され、特権を剥奪されて宝石や別邸を売却して初めて多額な財産税を納め、昭和22年に皇籍を離脱して”平民”となった。1976年8月19日、95歳の長い生涯を閉じるまでの彼女の道のりは、まさにお昼のテレビドラマをこえる波瀾の人生。
そんな梨本宮伊都子妃は生前、文章を書くのが大好きで手記、回想録、歌集も残しているが、驚くのは1899年から亡くなる二ヶ月ほど前まで、ほぼ毎日、77年以上もの長期間、日記を書き続けたことだった。皇族の一員、という庶民とはかけ離れた特殊な立場の方ではあるが、明治・大正・昭和の時代に渡って綴られた日記は、平成の今読み返してみると時代を反映した貴重な記録となっている。構成は、伊都子妃の日記に、著者によるその当時の歴史的事件や背景の解説が交互に記されていてわかりやすい。
現代の女性とそれほど変わらない伊都子妃の微妙な女心ものぞかれて、ちょっと微笑ましい文章もある。彼女は身長151センチと小柄であることが悩みで身長拡張器なる機械を購入してみたり、明治42年に初めて訪問したパリではファッションに夢中になり、日本橋高島屋でごひいきの歌舞伎役者を見かけると喜んでよい日だったと満足したり。側室を抱えるのが当然だった時代に、政略結婚した宮様とは仲睦まじく、すでに娘も生まれた21歳の時に宮様がフランスに留学した夜、彼女はインフルエンザにかかり発熱し、宮様と一緒に御湯に入りし夢を見るなど、なまめかしい告白もある。
その一方で、政略結婚した娘に初孫が生まれるが、複雑な政治の関係によって不可解な毒殺で命を落とす不幸にもあう。しかし、感情におぼれることもなく、初潮や出産時、病気の時など便通まで記述しているところなど、日記というよりもむしろ冷静な観察記録に近い。几帳面さと気丈さがありながら、年齢を重ね、平民になり受難の時代になると美智子さまのご婚約を「日本はもうだめだと考へた」と憤慨をあらわにしたりと、不快な感情を隠そうとしなくなる。
ところで、何故、彼女はこれほどまでの膨大な日記を残したのだろうか。
日々の生活に潜む没落の予感が伊都子に筆をとらせたのではないだろうか、と筆者は推測している。そればかりでもなく、皇族の妃殿下という誇りもあり、正確な日時、ものの単位など、数字が並ぶところから、宮家に嫁ぎ一族を継承していく嫁としての使命感もあったのではないかとも感じている。しかし、昭和25年、金婚式の翌日、渋谷の平凡な自宅前で夫と一緒に写真に納まる小さな老婆の姿には、懸命に激動の時代を生き波乱万丈の人生だったけれど、結局、庶民以上でもなく、またそれ以下でもないひとりの女性の平凡な表情が写っている。
■さまざまなお嬢さまたちの本
・「明治のお嬢さま」黒岩比佐子著











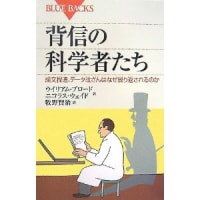

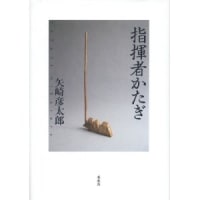
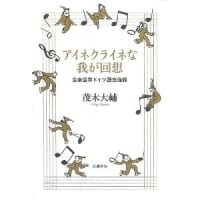
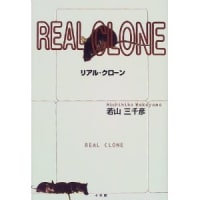
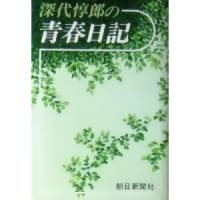
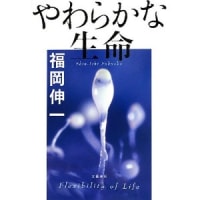
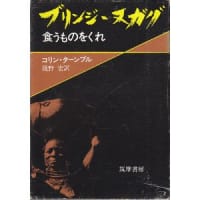
ご訪問ありがとうございます。死因が今でも謎なのですね。いずれにせよ、歴史にうもれた気の毒なお話だと思います。