 これは映画になる。絶対になる!
これは映画になる。絶対になる!1959年生まれの著者なのだが、何故か「終戦後から30年代の東京が好き」という奥田氏。そもそも年齢からいってそんな昭和の30年代の記憶なんかないだろ、とつっこみたくなるのだが、その昭和の東京にこだわり舞台にし忠実に時代の熱気と雰囲気を再現したのが本書の「オリンピックの身代金」。
1964年夏、日本は敗戦から立ち直り驚異的な復興を遂げ、世界に再生した「日本」をアピールする絶好の機会でもあるアジア初の五輪開幕を控えた東京で、謎の連続爆発事件が勃発する。あたかも警察を愚弄するような犯罪の捜査線上にうかんだ容疑者は、なんと秋田出身の長身で端正な容貌の東大大学院生、島崎国男。容姿端麗、頭脳明晰、将来を約束された天下のエリートが何故。しかも、彼は大胆不敵にも「東京オリンピック」を人質かわりに、国家に身代金を要求するようになる。
本書を知ったのは、新聞のエンターティメント系小説紹介の記事からだったのだが、タイトルが「40年前も『格差』の光景」だった。
小林多喜二の「蟹工船」が本屋で平積みになっているのは、世間の関心のキーワードが今「格差社会」だからであろう。現代の社会の片隅で多少なりとも働いている私自身も「格差社会」を実感する時がある、というよりも結局は、記事にあるように今も昔も格差社会であり、日本全体のGDPが順調な時はそれまでの日本全体があまりにも貧しかったためにその差も気にならず、やがてエコノミック・アニマルたちが東京オリンピックを足がかりに1億総中流社会に押し上げたよい時代が、たまたま続いたのだ。
マルクス経済学を専攻している島崎は、出稼ぎ先の現場宿舎で亡くなった兄の死をきっかけに、兄と同じ過酷な労働環境で日雇いの肉体労働をはじめるうちに、戦後の財閥解体や農地改革によって支配層がその勢力を弱めたかのようにみえて、実際は財産が一族から企業に移っただけであり、人民は一貫して貧しいまま、格差は年々広がっていると実感するようになる。島崎の勤務先の現場は、一流企業の下請けの、そのまた下請けの「会社」ともいえないようなところから派遣された炎天下。ここまで過酷な労働環境はさすがに今ではありえないが、労働の中身、休憩場所、弁当まで格差をつけられた秋田からの出稼ぎ労働者たちの姿は、悲惨さの違いはあっても最近の報道にみる現代日本の格差社会の構図とそっくりである。
「もはや戦後ではない」。有名な「経済白書」の宣言だが、秋田の寒村では、都会の繁栄から取り残され、こどもの高校進学もままならず、あまりにも生活が苦しくなんのために生きているのかわからない動物のような暮らしぶりである。出稼ぎで死んだ夫の葬儀のために初めて東京を訪れた妻が、東京タワーに上って「東京は、祝福をひとりじめしている」とつぶやく場面がある。東京の富と繁栄が、地方労働者の安価な労働力の搾取のうえに築かれていること、大企業が下請けを最大限利用することで利益を伸ばしている構図、その理不尽な社会に、島崎だけでなく、読者も憤りを感じて犯罪者にも関わらずつい彼に肩入れをしてしまう。すごくおもしろいのに、読むスピードが早い私なのに、この本を読むのに10日以上もかかってしまった・・・。それは、読むうちにやりきれなさと島崎の虚しさにからめられてしまったからだ。映画『三丁目の夕日』が、高度成長期へ向かう日本の青春期としたら、本書は青春期の闇と絶望だ。
そして、日本中の誰もがオリンピック開催を喜び成功を祈らずにいられない中、たったひとりオリンピックを「西欧的普遍思想の迎合であり、人民にかりそめの夢を与えて現実を忘れさせる支配層の常套句」という島崎の恩師への書簡を読んで、昨年の北京オリンピックを思い出した。劣悪なる環境で働く民工は、40年前の秋田からの出稼ぎと同じではないか。おしりも我が国でも石原慎太郎都知事が、2016年東京オリンピック招致運動をひろげているが、私はもうこの国でオリンピックはいらないと考えている。
「おめ、アカなんだってな。おめは東大行くぐらい頭さいいんだがら、世の中を変えてけれ。おらたち日雇い人夫が人柱にされない社会にしてけれ」
労働の実践は、知を揺るがす力を有している。島崎は、搾取構造の底辺にいながら現状を易々と受け入れる日雇い労働者を無抵抗と思っていたのだが、やがて彼らは単に戦う術を知らないだけだと認識していく。
昭和の雰囲気の驚嘆させられるリアリティな再現と熱気、オリンピックに願う人々の高揚感が活字の中からたちあがり、クライマックスにかけてのスピードと一気に高まる緊張感は、単なる社会派サスペンスの極上のエンターティメント以上に、著者自ら最高傑作との断言どおり。本当によくこんな内容を思いついたと驚嘆させられる。しかも、実際こんな”事件”があったとしても国家の威信の前に封印されたとできなくもない仕上がりのニ段組の500ページあまりの大作は、早くも今年度のナンバー1としたいくらいだ。
今年の正月休暇に、大好きな黒澤明監督の映画『天国と地獄』を鑑賞した。テレビでも昨年リバイバル製作されて観たのだが、妻夫木クンが携帯電話を片手に身なりのよい医学生役に扮したら、どんなに熱演しても本物の映画の山崎努の狂気と重みには遠く及ばなかった。ところで、当時の格差社会を描いた『天国と地獄』の中で、白黒映画なのにたった一度、あるモノだけを着色されて作られている。そんなことも思い出した、本書の日の丸の象徴を重ねた表紙もすぐれものである。
■こんな本も
・「東京物語」











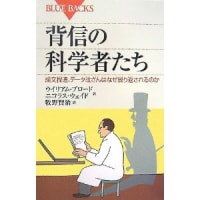

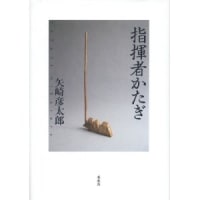
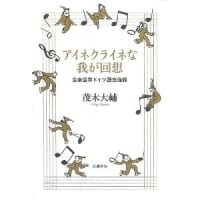
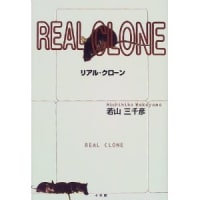
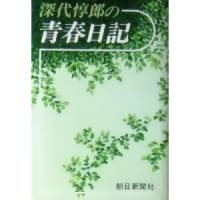
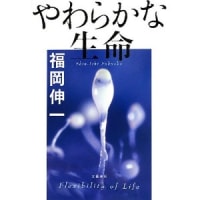
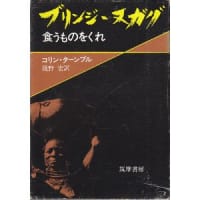
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます