 ヨハン・セバスチャン・バッハにはケーテンで過ごした時代に、鍵盤楽器のための6つの組曲からなる「フランス組曲」(BMV812-817)を残している。
ヨハン・セバスチャン・バッハにはケーテンで過ごした時代に、鍵盤楽器のための6つの組曲からなる「フランス組曲」(BMV812-817)を残している。30代半ばの彼は最初の妻を病気で亡くし、20歳の若い二番目の妻、アンナ・マグダレーナ・バッハへの結婚の贈物とも言われているが、簡潔ながら優美で気品のある曲である。
1940年6月4日パリ。前日の月曜日に、開戦以来初めてパリの爆弾が落ちてきた。もうすぐナチスがやってくる。
恐怖にとらわれたパリに住む人々は、いっせいに南の農村へと逃れていこうとする。裕福な上流階級のペリカン家一族、作家のガブリエル・コルトや銀行家たちは彼らなりのブルジョワ風流儀で、彼に雇われている者や労働者たちもそれなりの方法で危険から脱出しようとしている。
「六月の嵐」
駅には人が溢れ、道路も大渋滞、物資も不足してガソリンもなくなっていく。そんな非常事態の状況下で、ものを略奪する者もあり、だましてガソリンを盗む者もあり、人々は人間の本性をあらわしていくようになる。しかし、そんな戦局においても、己を見失わず、誇りを保ち愛情と思いやりを失わない善良なるミショー夫妻のような庶民もいるのである。作者は、様々な人々をさながらひとつの音符、音、小節のように描いていきながら、やがて彼らが繋がっていき、互いに共鳴しあって音楽が鳴っていく。私は、トルストイの「戦争と平和」を思い出していた。
「ドルチェ」
田舎町ビュシーで最も裕福なアンジェリエ家の屋敷に、ドイツ軍中尉ブルーノ・フォン・ファルクが宿泊するようになる。主人であるガストンは、1年前からドイツ軍の捕虜となっているため不在で、美しい妻のリュシルが冷たい義母のアンジェリエ夫人や召使とともに暮らしていた。意気揚々と、町を村を占領していくドイツ兵とフランス女性が親しくなるのは危険なことだったが、それでも若い娘たちは清潔で金髪のドイツ兵たちを見つめずにはいられない。ドイツ将校たちは、フランス人と友好関係を結ぼうとこどもたちと遊んだりする。ブルーノは礼儀正しくリシュリと親しい関係を築こうとしていくうちに、ふたりの間の恋がめばえていく。占領者と愛されていなかったとはいえ、その夫を捕虜に囚われている既婚女性。不条理な中で、激しい感情と理性の相克にひきさかれるようなふたりの精神を、観察者のように作者は描写していく。まるで映画を観ているように物語は緊迫の中に進行していき、「六月の嵐」とからみあっていく。474ページのどの文章も緻密で繊細、芸術性が高く、細やかな情を描いても決して感情のおぼれることにない作家の資質に感服する。
ただし、「フランス組曲」は5つの楽章からなるのだが、ここで未完で終わってしまっている。作者のイレーヌ・ネミロフスキーは、「ドルチェ」を書き終えた後、1942年7月13日にフランス憲兵によってユダヤ人であることを理由に連行され、アウシュヴィッツ収容所で亡くなった。残された当時12歳と5歳の娘たちは、翌年やはり同じように連れ去られた父からひとつのトランクを托された。
「決して手放してはいけないよ、ここにはお母さんのノートが入っているのだから」と。
重いトランクを懸命に運びながら、必死に憲兵から逃れ、名前を変え、逃亡を続けた少女たち。あまりにもつらくて、母が最後に残したノートを読む勇気がなかったそうだが、プライベートな日記だと思っていたノートは、作家として円熟に向かおうとしていたイレーネが、残された時間が少ないことを覚悟して執筆した最後の長編小説だったのだ。紙が不足してきていたために、原稿は小さな字でびっしりと書かれていたという。2004年、トランクの中に眠っていた物語は1冊の本となり、フランスで70万部、全米で100万部、世界で350万部の驚異的な売上を記録しているという。
こんな優れた小説が日本で出版されるのに何故8年もかかったのか、と思わざるをえないところもあるのだが、上記の作者自身のストーリという前置きなど必要ないくらい本書は読むべき価値がある。自然の描写が瑞々しく巧みで、ほのかにエロチックな描写も私のお気に入りだ。野崎歓氏の解説も充実していて、残された資料によると作者の中では様々な構想が交錯していたようだが、物語は私の予想外の大きな展開になりそうだったのだ。文才という才能だけでなく、祖父や父達がロシア革命を潜り抜けてきた経験から、彼女には冷徹な哲学があったようだ。そんな彼女の文章は、今でも充分に私たちを魅了する。











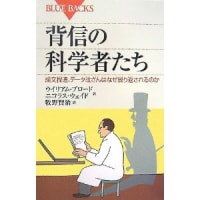

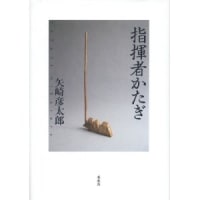
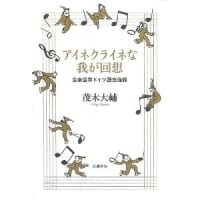
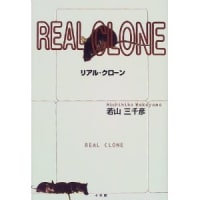
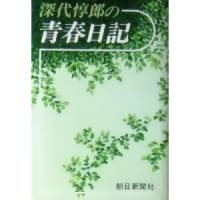
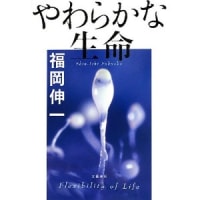
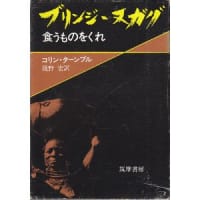
コメントをありがとうございます。
>タイトルの魅力
私もまさにそれが一番の理由でした。
予想外にこの調べはほのかに官能的で、私はとても気に入りました。
calafさまもお読みになられるとは、私としても嬉しいです!
最近、仕事以外にも活動をはじめてしまい、ブログが滞りがちなのが気になっています。
先日もギル・シャハムのVnリサイタルではさまざまに聴いて感じることがありましたのに・・・。
日々感じることはこれからも忘れずに大切に。。。