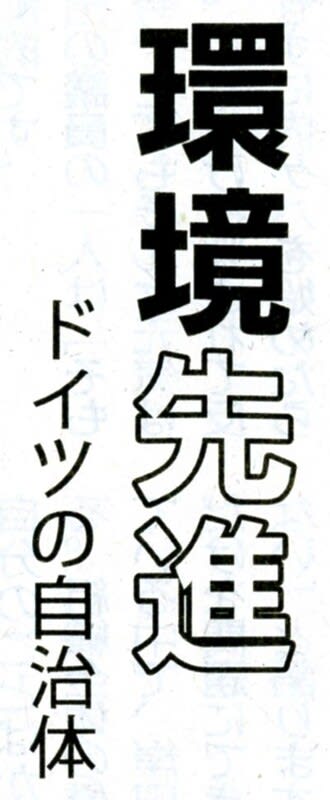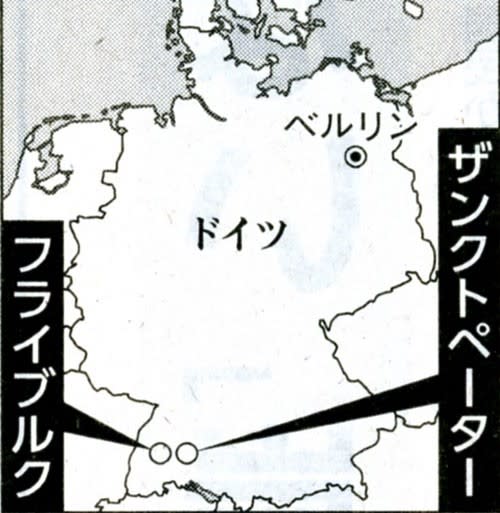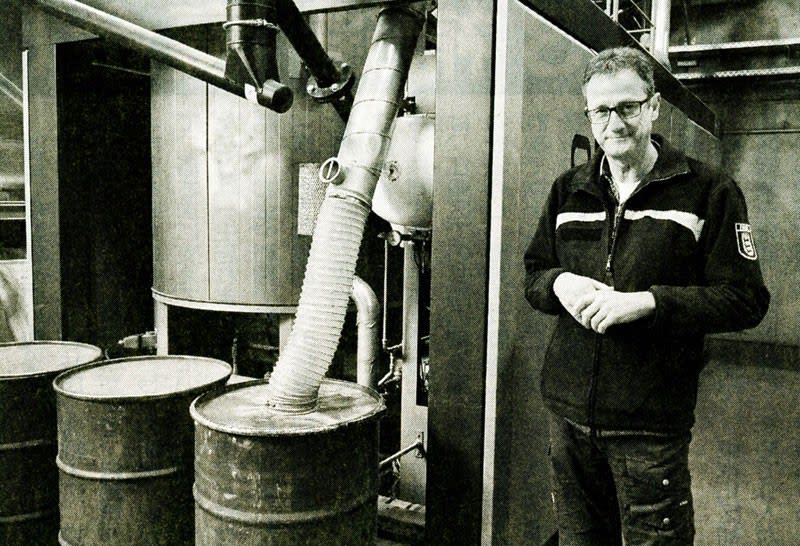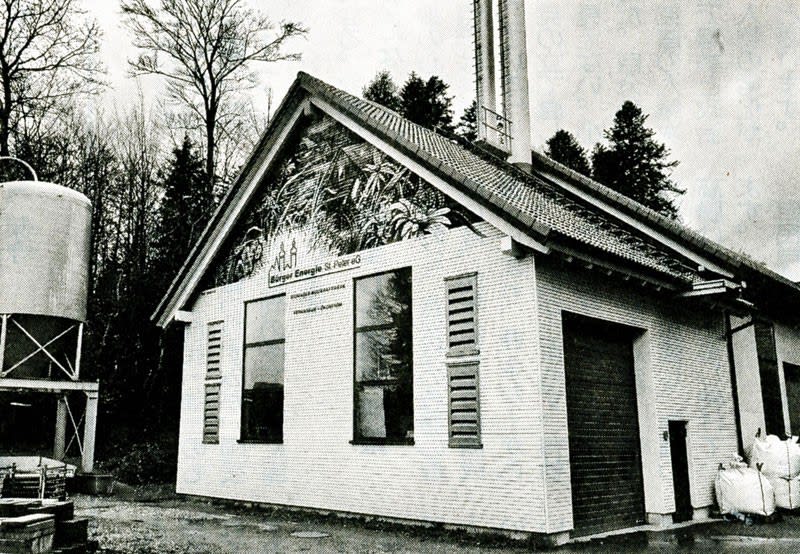再エネの力 長崎・五島市① 洋上風力 島の恵みを一大産業に

海にたくさんの風車を浮かべて、島の恵みである風の力で生み出した電気を一大産業にして発展してゆく壮大な未来像を描く自治体があります。長崎県の西方100キロメートルに浮かぶ63の島々からなる五島市です。浮体式洋上風力発電や太陽光発電を推進し、市内の電力需要の60%を再生可能エネルギーでまかなう再エネの先進地を訪ねました。
(細川豊史)

長崎市から高速船で1時間半弱、五島列島最大の福江島が近づくと、海に浮かぶ大きな風車群が遠目に見えてきます。東京電力福島第1原発事故が起き、従来の電力政策からの転換が迫られた2011年、五島市は環境省による日本初の浮体式洋上風力発電の試験地に選定されました。
試験後に現在も商用運転中の1基(出力2メガワット)に加え、26年1月には新たに五島フローティングウィンドファームによる8基(同各2・1メガワット)が完成し、商用運転を始めます。これによって市内の電力需要の80%をまなかえる発電能力となります。

福江商工会議所の清瀧誠司会頭=長崎県五島市

海上に浮かぶ浮体式洋上風力発電の風車=長崎県五島市
電気で経済循環
五島フローティングウィンドファームは、準大手ゼネコンの戸田建設など大企業が出資する合同会社。そのままでは、五島の再エネ資源が大企業に利益をもたらすだけになってしまいます。そこで五島市民は地域新電力の五島市民電力株式会社を立ち上げ、電力の販売による収益が地域経済を循環するしくみをつくりました。
「風力発電は設備の規模が大きく、大手にしかできない。地元は海を貸すだけで、利益をすべて持っていくのは東京や大阪の大企業では面白くない。島からお金が流れていくだけです。発電で生まれるお金を五島に残したいと思いました」
五島市民電力社長の橋本武敏さんはこう語ります。
五島市の再エネ推進の特徴は、地元経済界、中小企業、漁業者、行政の連携した力―島をあげてのとりくみです。それぞれの立場から再エネの大きな可能性に情熱を傾けて尽力してきました。中でも、経済人としてリーダーシップをとってきたのは、福江商工会議所の清瀧誠司会頭です。
「脱炭素は時代の流れとして間違いない。850の会員企業がどうこの変化を乗り切るか。商工会議所の責任者として、一日でも早く着手することで有利になるのではと考えました」
現在84歳の清瀧さんは、20代の頃に石炭から石油へのエネルギー転換で人々が翻弄されるのを目の当たりにしました。ガソリンスタンドの経営者として、今後の需要の減少、化石燃料から再エネへの新たなエネルギー転換に危機意識を持ち、ピンチをチャンスに変えようという思いを強くしてきました。
洋上風力発電設備の建設を担う戸田建設は当初、風車を乗せる浮体部分を長崎県の本土で建造予定でした。しかしそれでは「五島の経済にプラスにならない」と考えた清瀧さんらは同社に要請し、五島市に建造拠点を誘致することに成功しました。
コンクリートは地元企業から調達。同社と商工会議所が連携し、建造に必要な資機材なども市内で調達しました。風力発電の運転管理も市内企業を採用。
これらによって新たな雇用が生まれました。
清瀧さんらは関係者の間で議論を進めるうちに、五島で洋上風力発電をやるのなら、建造と維持管理だけで終わっては不十分だと考えるようになりました。「五島で発電した電気を五島で使って、資金を循環させよう」と、地域新電力の設立に動きました。
それが18年に設立された五島市民電力です。当時、清瀧さんは代表取締役会長を務めていました(現相談役)。市内53の企業・団体・個人が出資し、地域に密着した経営を行っています。
26年1月に完成予定の洋上風力8基の電気はすべて特定卸供給契約にもとづき五島市民電力が直接買い取り、販売します。
市民には九州電力よりも5%安くなる契約プランを販売。洋上風力と太陽光でつくられた「五島産の電気」によって、地域経済の循環が始まっています。
生活が国土守る
商工会議所として、再エネを推進する取り組みも進めています。21年から始めた「五島版RE100」の認定です。「RE100」は使用電力を100%再エネでまかなうことをめざす国際的な企業の連合体。環境への負荷が少ないエネルギーを使う企業を取引や投資の対象として評価する動きが世界的に広がっています。
「五島版RE100」では、五島市民電力の電気を使い、今後5年以内に再エネ100%を達成することを宣一言し、その根拠となる長期行動計画を作成することを認定条件としています。市役所や市内の小中学校などの公共施設はすでに認定済みです。市内を歩くと、認定の証しであるステッカーが入り口に張られた飲食店が見られます。
第1次認定企業の一つで、かまぼこなどの水産加工品を製造する市内の企業が、五島産の電気を100%使用していることが商品の買い付けをするバイヤーに評価され、取引につながる事例も生まれています。
今年3月、認定企業が最初の目標である50を超え、52に達しました。同月31日付の長崎新聞には、このことを知らせる全面広告が掲載されました。
五島の再エネの取り組みを視察しに訪れる全国の行政関係者などの数は増え続け、昨年は1300人にのぼりました。来島者の増加は、雇用の維持などの経済効果につながり始めていて、清瀧さんは手ごたえを感じています。
「五島に住んで生活すること自体が国土を守ることになる。五島は栄えていかなければならない。地方には地熱、風力など、資源があります。五島みたいなことは全国でできるはずです」
(つづく)(6回連載です。次回から経済面)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2025年6月4日付掲載
清瀧さんらは関係者の間で議論を進めるうちに、五島で洋上風力発電をやるのなら、建造と維持管理だけで終わっては不十分だと考えるようになりました。「五島で発電した電気を五島で使って、資金を循環させよう」と、地域新電力の設立に動きました。
それが18年に設立された五島市民電力です。当時、清瀧さんは代表取締役会長を務めていました(現相談役)。市内53の企業・団体・個人が出資し、地域に密着した経営を行っています。
26年1月に完成予定の洋上風力8基の電気はすべて特定卸供給契約にもとづき五島市民電力が直接買い取り、販売します。
市民には九州電力よりも5%安くなる契約プランを販売。洋上風力と太陽光でつくられた「五島産の電気」によって、地域経済の循環が始まっています。

海にたくさんの風車を浮かべて、島の恵みである風の力で生み出した電気を一大産業にして発展してゆく壮大な未来像を描く自治体があります。長崎県の西方100キロメートルに浮かぶ63の島々からなる五島市です。浮体式洋上風力発電や太陽光発電を推進し、市内の電力需要の60%を再生可能エネルギーでまかなう再エネの先進地を訪ねました。
(細川豊史)

長崎市から高速船で1時間半弱、五島列島最大の福江島が近づくと、海に浮かぶ大きな風車群が遠目に見えてきます。東京電力福島第1原発事故が起き、従来の電力政策からの転換が迫られた2011年、五島市は環境省による日本初の浮体式洋上風力発電の試験地に選定されました。
試験後に現在も商用運転中の1基(出力2メガワット)に加え、26年1月には新たに五島フローティングウィンドファームによる8基(同各2・1メガワット)が完成し、商用運転を始めます。これによって市内の電力需要の80%をまなかえる発電能力となります。

福江商工会議所の清瀧誠司会頭=長崎県五島市

海上に浮かぶ浮体式洋上風力発電の風車=長崎県五島市
電気で経済循環
五島フローティングウィンドファームは、準大手ゼネコンの戸田建設など大企業が出資する合同会社。そのままでは、五島の再エネ資源が大企業に利益をもたらすだけになってしまいます。そこで五島市民は地域新電力の五島市民電力株式会社を立ち上げ、電力の販売による収益が地域経済を循環するしくみをつくりました。
「風力発電は設備の規模が大きく、大手にしかできない。地元は海を貸すだけで、利益をすべて持っていくのは東京や大阪の大企業では面白くない。島からお金が流れていくだけです。発電で生まれるお金を五島に残したいと思いました」
五島市民電力社長の橋本武敏さんはこう語ります。
五島市の再エネ推進の特徴は、地元経済界、中小企業、漁業者、行政の連携した力―島をあげてのとりくみです。それぞれの立場から再エネの大きな可能性に情熱を傾けて尽力してきました。中でも、経済人としてリーダーシップをとってきたのは、福江商工会議所の清瀧誠司会頭です。
「脱炭素は時代の流れとして間違いない。850の会員企業がどうこの変化を乗り切るか。商工会議所の責任者として、一日でも早く着手することで有利になるのではと考えました」
現在84歳の清瀧さんは、20代の頃に石炭から石油へのエネルギー転換で人々が翻弄されるのを目の当たりにしました。ガソリンスタンドの経営者として、今後の需要の減少、化石燃料から再エネへの新たなエネルギー転換に危機意識を持ち、ピンチをチャンスに変えようという思いを強くしてきました。
洋上風力発電設備の建設を担う戸田建設は当初、風車を乗せる浮体部分を長崎県の本土で建造予定でした。しかしそれでは「五島の経済にプラスにならない」と考えた清瀧さんらは同社に要請し、五島市に建造拠点を誘致することに成功しました。
コンクリートは地元企業から調達。同社と商工会議所が連携し、建造に必要な資機材なども市内で調達しました。風力発電の運転管理も市内企業を採用。
これらによって新たな雇用が生まれました。
清瀧さんらは関係者の間で議論を進めるうちに、五島で洋上風力発電をやるのなら、建造と維持管理だけで終わっては不十分だと考えるようになりました。「五島で発電した電気を五島で使って、資金を循環させよう」と、地域新電力の設立に動きました。
それが18年に設立された五島市民電力です。当時、清瀧さんは代表取締役会長を務めていました(現相談役)。市内53の企業・団体・個人が出資し、地域に密着した経営を行っています。
26年1月に完成予定の洋上風力8基の電気はすべて特定卸供給契約にもとづき五島市民電力が直接買い取り、販売します。
市民には九州電力よりも5%安くなる契約プランを販売。洋上風力と太陽光でつくられた「五島産の電気」によって、地域経済の循環が始まっています。
生活が国土守る
商工会議所として、再エネを推進する取り組みも進めています。21年から始めた「五島版RE100」の認定です。「RE100」は使用電力を100%再エネでまかなうことをめざす国際的な企業の連合体。環境への負荷が少ないエネルギーを使う企業を取引や投資の対象として評価する動きが世界的に広がっています。
「五島版RE100」では、五島市民電力の電気を使い、今後5年以内に再エネ100%を達成することを宣一言し、その根拠となる長期行動計画を作成することを認定条件としています。市役所や市内の小中学校などの公共施設はすでに認定済みです。市内を歩くと、認定の証しであるステッカーが入り口に張られた飲食店が見られます。
第1次認定企業の一つで、かまぼこなどの水産加工品を製造する市内の企業が、五島産の電気を100%使用していることが商品の買い付けをするバイヤーに評価され、取引につながる事例も生まれています。
今年3月、認定企業が最初の目標である50を超え、52に達しました。同月31日付の長崎新聞には、このことを知らせる全面広告が掲載されました。
五島の再エネの取り組みを視察しに訪れる全国の行政関係者などの数は増え続け、昨年は1300人にのぼりました。来島者の増加は、雇用の維持などの経済効果につながり始めていて、清瀧さんは手ごたえを感じています。
「五島に住んで生活すること自体が国土を守ることになる。五島は栄えていかなければならない。地方には地熱、風力など、資源があります。五島みたいなことは全国でできるはずです」
(つづく)(6回連載です。次回から経済面)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2025年6月4日付掲載
清瀧さんらは関係者の間で議論を進めるうちに、五島で洋上風力発電をやるのなら、建造と維持管理だけで終わっては不十分だと考えるようになりました。「五島で発電した電気を五島で使って、資金を循環させよう」と、地域新電力の設立に動きました。
それが18年に設立された五島市民電力です。当時、清瀧さんは代表取締役会長を務めていました(現相談役)。市内53の企業・団体・個人が出資し、地域に密着した経営を行っています。
26年1月に完成予定の洋上風力8基の電気はすべて特定卸供給契約にもとづき五島市民電力が直接買い取り、販売します。
市民には九州電力よりも5%安くなる契約プランを販売。洋上風力と太陽光でつくられた「五島産の電気」によって、地域経済の循環が始まっています。