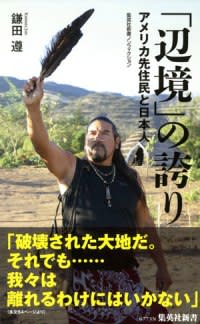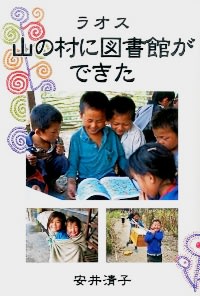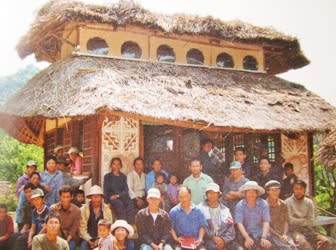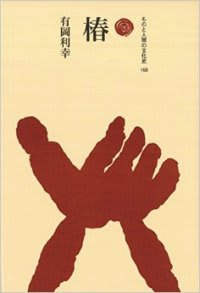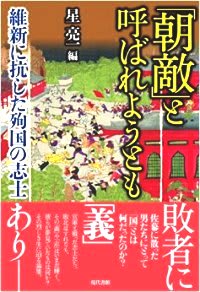【野島智司著、誠文堂新光社発行】
表紙上部の「日本に800種!」の下に赤字で「コンクリートをかじって栄養補給!?」。えっ、ホント? カタツムリは雨の日、ブロック塀に集まって二酸化炭素を含んだ雨水がわずかに溶かし出すコンクリートを食べるという。カタツムリの殻の主成分は炭酸カルシウム。カタツムリは殻づくりに必要なカルシウムを、石灰石を主原料とするコンクリートから摂取するというわけだ。

カタツムリには天敵が多い。とりわけ繁殖期の野鳥にとってカタツムリは貴重なカルシウム源。野鳥の卵殻は成分の約95%を炭酸カルシウムが占める。「土壌中のカルシウムが少ない地域ではカタツムリも少なく、その結果、野鳥の卵の殻も薄くなる」という傾向があるそうだ。オサムシの仲間で日本固有種のマイマイカブリはカタツムリを主食とする。頭が小さく首(正確には前胸部)が長くて、楽器の琵琶に似る。だから別名「琵琶虫」。カタツムリの殻の入り口から頭を突っ込み、口から出す消化液で溶かして食べてしまう。
トカゲは敵に襲われたとき、自ら尻尾を切る〝自切(じせつ)〟で相手の気をそらして逃げる。カタツムリの1種イッシキマイマイはヘビに噛まれると同じような行動を取る。尻尾はトカゲ同様、しばらくすると元に戻るという。ノミガイという小さなカタツムリは鳥に食べられてもフンの中に潜んで生き延び生息地を広げているともいわれる。実にしたたか!
その生態には他にも不思議がいっぱい。ツノ(大触覚)の先にある眼はものの形を見ることができず、光の明暗を感じる程度。雌雄同体で、おとなになるとツノの間に頭瘤(とうりゅう)というコブができる。このコブから性フェロモンを出しているらしい。交尾は2匹が「8」の字を描く形で行う。そのため構造的に右巻きのカタツムリは右巻きのカタツムリと、左巻きは左巻きとしか交尾できない。
殻の表面には無数の微細な溝があり、雨どいのように水が流れることで汚れが浮き上がって落ちやすい。その殻の応用研究から、汚れにくい外壁用タイルや台所、トイレなどが生まれている。常に体を地面に密着させて動くカタツムリの移動方法を応用したロボットの開発も進んでいるそうだ。これまで知らなかった様々の謎に触れて、デンデンムシがより身近な存在に思えてきた。