引用画像は、3日1時51分頃発生した地震の震央位置です。気象庁HPより引用。

3日、1時51分頃、八丈島の南およそ180㌔の鳥島近海の深さはごく浅い個所で、マグニチュード5・9の地震が発生しました。
この地震で、国内の地震観測地点で震度1以上を観測した地点はありませんが、地震発生からおよそ40分ほどした2時31分頃、震源からおよそ北に180㌔離れた八丈島八重根で、高さ50㌢の津波を観測し、気象庁より、伊豆諸島に、津波注意報が発表されましたが、4時10分、津波注意報は解除されるに至りました。
通常、この地震の規模では、震源がごく浅くても、津波は発生しないものですが、この地震の震源地付近は、七島・硫黄島海嶺と呼ばれる、海嶺と言って、地下のマグマが上昇して、その上の地殻の割れ目から湧き出ている地域に位置しています。このため、この地域周辺では、比較的やわらかい地質が分布し、地質内に割れ目など多く、地震発生に伴って、震源地周辺での海底周辺では、地層崩壊などの2次的な地殻の変動が発生しやすいと推測され、このため、当該地殻変動に伴って、予想以上の津波が発生したと私は考えています。
地震は、地殻の変動により地震波が発生して、当該地震波が伝搬して地震動を引き起こすものですが、地震に伴う津波は、地震が発生した海底での地殻変動により発生するものです。で、この地震が発生した海底での地殻変動は、地震を引き起こす地殻変動のみならず、地震が引き起こされた結果、2次的に発生する地殻変動(海底での傾斜地の致道崩壊など)も含まれます。
当該2次的の発生する地殻変動は、地震が発生した地域の地層が比較的新しくやわらかい地層がより多区分布しているほど発生しやすく、海嶺と呼ばれ地地域周辺や、海溝近くに付加体(陸地から流れこんだり、海溝でのプレート活動で堆積した堆積物が集まっている地層)が多く分布している地域では、当該2次的の発生する地殻変動発生にうってつけの地域と言えます。
このような原因と、地震波を発生させる地殻変動の加減(滑るような変動だった場合など)で、で、地震動よりも津波が顕著である地震波発生する場合がありますが、こういったタイプの地震を、津波地震 と呼ばれています。今回の鳥島近海の地震、津波地震 だったと私は考えています。

3日、1時51分頃、八丈島の南およそ180㌔の鳥島近海の深さはごく浅い個所で、マグニチュード5・9の地震が発生しました。
この地震で、国内の地震観測地点で震度1以上を観測した地点はありませんが、地震発生からおよそ40分ほどした2時31分頃、震源からおよそ北に180㌔離れた八丈島八重根で、高さ50㌢の津波を観測し、気象庁より、伊豆諸島に、津波注意報が発表されましたが、4時10分、津波注意報は解除されるに至りました。
通常、この地震の規模では、震源がごく浅くても、津波は発生しないものですが、この地震の震源地付近は、七島・硫黄島海嶺と呼ばれる、海嶺と言って、地下のマグマが上昇して、その上の地殻の割れ目から湧き出ている地域に位置しています。このため、この地域周辺では、比較的やわらかい地質が分布し、地質内に割れ目など多く、地震発生に伴って、震源地周辺での海底周辺では、地層崩壊などの2次的な地殻の変動が発生しやすいと推測され、このため、当該地殻変動に伴って、予想以上の津波が発生したと私は考えています。
地震は、地殻の変動により地震波が発生して、当該地震波が伝搬して地震動を引き起こすものですが、地震に伴う津波は、地震が発生した海底での地殻変動により発生するものです。で、この地震が発生した海底での地殻変動は、地震を引き起こす地殻変動のみならず、地震が引き起こされた結果、2次的に発生する地殻変動(海底での傾斜地の致道崩壊など)も含まれます。
当該2次的の発生する地殻変動は、地震が発生した地域の地層が比較的新しくやわらかい地層がより多区分布しているほど発生しやすく、海嶺と呼ばれ地地域周辺や、海溝近くに付加体(陸地から流れこんだり、海溝でのプレート活動で堆積した堆積物が集まっている地層)が多く分布している地域では、当該2次的の発生する地殻変動発生にうってつけの地域と言えます。
このような原因と、地震波を発生させる地殻変動の加減(滑るような変動だった場合など)で、で、地震動よりも津波が顕著である地震波発生する場合がありますが、こういったタイプの地震を、津波地震 と呼ばれています。今回の鳥島近海の地震、津波地震 だったと私は考えています。














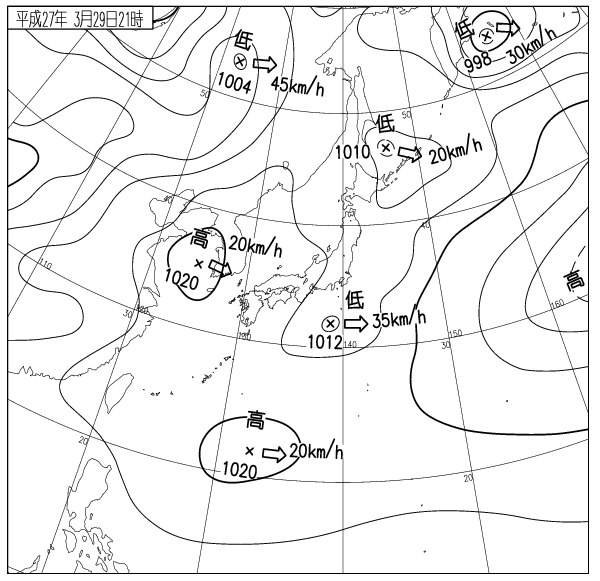




 東北地方太平洋沖地震では、震度7を観測した宮城県栗原市(栗原市築館)での最大加速度(南北、東西、上下3成分合成)で、2933ガルなのに対し、20年前の兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)発生時の、
東北地方太平洋沖地震では、震度7を観測した宮城県栗原市(栗原市築館)での最大加速度(南北、東西、上下3成分合成)で、2933ガルなのに対し、20年前の兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)発生時の、
