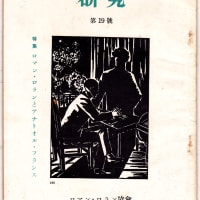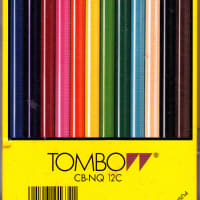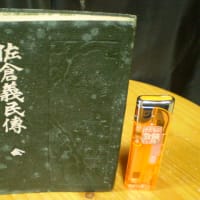この一揆をはじめて本として出版し、世に広く知らしめたのは河村吉三という人の書いた「天保義民録」。
明治26年の出版。100年以上も前だ。
著書の河村氏は、近江の野洲の人で、嘉永5年生まれ。代々庄屋職をつとめてきた素封家の出だそうな。維新前後のころは文武修行のため、藩の城下や京都に遊び、維新後は自由民権運動に飛び込んだそうな。出版はちょうど一揆後50年がたったときで、顕彰運動も盛り上がり始めたとき。河村氏は自ら馬にまたがり、甲賀、野洲、粟太、蒲生4郡の旧家を歴訪して資料を集め、古老に話を聞き、と寝食を忘れて研究に没頭した。そのとき、河村氏が集めた資料は、空襲で焼けてしまったそうで、今では、この本が一揆の基本文献となっている。刀江書房の「百姓一揆叢談」(上)で読むことができる。
もう1冊が、松好貞夫「天保の義民」。岩波新書です。1962年の出版。これも45年前の本。岩波新書1冊がすべてこの近江甲賀の一揆について書かれ、背景から発端、経過、終結まで詳しい。前記の「天保義民録」を参考にした、と書いてある。学者が書いた本だけど、行間から著者の思いがあふれ、名著だと思う。なぜ他の一揆でもこのような本を書いてくれないのか。歴史学者は今、何をしてんの?といいたいくらいだ。ほんらいななら、こんな昔の本はとっくに絶版だが、なぜか今でもときどき本屋で目にする。なんでも滋賀県の一女性実業家がこの本の復刊に力を出したとか。
画像は、甲賀の矢川神社の参道。ここに約2000人の人が終結。
明治26年の出版。100年以上も前だ。
著書の河村氏は、近江の野洲の人で、嘉永5年生まれ。代々庄屋職をつとめてきた素封家の出だそうな。維新前後のころは文武修行のため、藩の城下や京都に遊び、維新後は自由民権運動に飛び込んだそうな。出版はちょうど一揆後50年がたったときで、顕彰運動も盛り上がり始めたとき。河村氏は自ら馬にまたがり、甲賀、野洲、粟太、蒲生4郡の旧家を歴訪して資料を集め、古老に話を聞き、と寝食を忘れて研究に没頭した。そのとき、河村氏が集めた資料は、空襲で焼けてしまったそうで、今では、この本が一揆の基本文献となっている。刀江書房の「百姓一揆叢談」(上)で読むことができる。
もう1冊が、松好貞夫「天保の義民」。岩波新書です。1962年の出版。これも45年前の本。岩波新書1冊がすべてこの近江甲賀の一揆について書かれ、背景から発端、経過、終結まで詳しい。前記の「天保義民録」を参考にした、と書いてある。学者が書いた本だけど、行間から著者の思いがあふれ、名著だと思う。なぜ他の一揆でもこのような本を書いてくれないのか。歴史学者は今、何をしてんの?といいたいくらいだ。ほんらいななら、こんな昔の本はとっくに絶版だが、なぜか今でもときどき本屋で目にする。なんでも滋賀県の一女性実業家がこの本の復刊に力を出したとか。
画像は、甲賀の矢川神社の参道。ここに約2000人の人が終結。